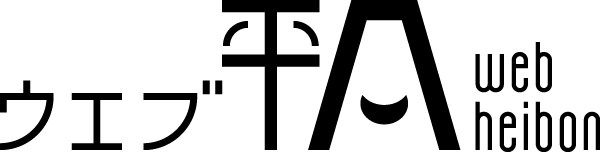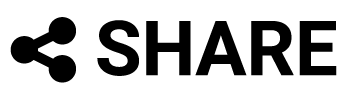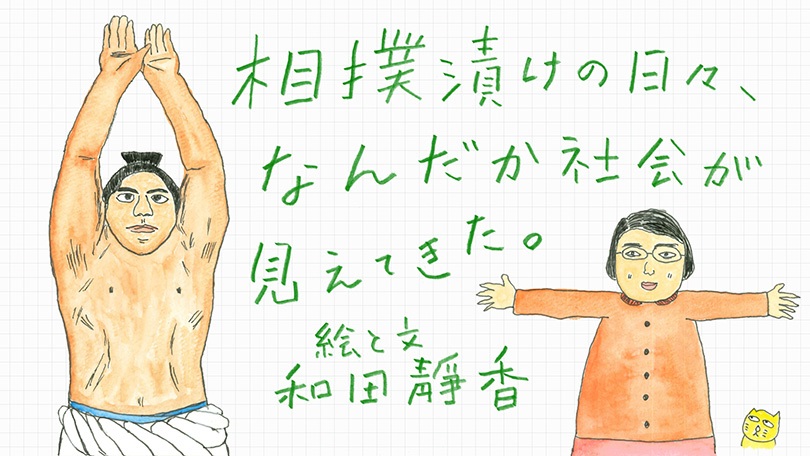
第5回
おすもうさんの「親方株問題」から「高齢者の再雇用」について考えた その②
[ 更新 ] 2023.12.22
鈴木剛さんが執行委員長を務める「東京管理職ユニオン」の事務所は、新宿の雑居ビルにあった。エレベーターで上がり、中へ入ると大勢の人たちが何やら真剣に話し込んでいる。ユニオンに集まる人はどんな人で、何を話しているんだろう? 横目で見ながら鈴木さんにご挨拶し、向き合って座ると、開口一番に「僕がこうして労働運動の道を歩むきっかけとなったのは、実は大相撲なんですよ」とニコニコおっしゃるではないか。えっ? 鈴木さんは相撲ファンだけじゃなく、元おすもうさんなんですか? ビックリしてアホなことを聞き返すと、ワッハハハと笑って、「和田さんは大相撲の春秋園(しゅんじゅうえん)事件って、ご存じですか?」と言う。春秋園事件? なんか、聞いたことがあるぞ。
「天龍(てんりゅう)という、おすもうさんがいました。1932年(昭和7年)に天龍を中心にしておすもうさんたちが東京・大井町にあった『春秋園』という中華料理屋に籠城(ろうじょう)して待遇改善を相撲協会に求めたんですよ」
あ、それ、前に読んだことがありました。はい、はい、なんとなく知ってます。
「当時としては革新的な要求を協会に出しました。会計制度をしっかり作ること、興行の時間を定めること、入場料を下げる、相撲茶屋の廃止、年寄制度も廃止、養老金制度を作ること、力士協会を作るなど、今見てもすばらしいものでしたね。彼らはこれを持って交渉するとして春秋園に32人で立てこもったんです。ストライキですね」
でも、たしか、うまく行かなかったように記憶しています……。
「当時の親方衆らが慌てて天龍らの説得にあたりましたが、天龍たちは少しも揺るがず、と。しかし、結果的には満足のいく回答を得ることができなくて、彼らは新たに『新興力士団』を結成して独自の相撲興行を行っていきます。でも、しだいに興行の人気は下火になり、半数は元の相撲協会に戻り、残りの人は引退、廃業しました。天龍自身はその後、ラジオで相撲解説者として活躍していたんですから、大した人です。天龍が相撲界の待遇改善、改革を試みての運動をおすもうさんたち30人以上とやったことを知って、学生時代の私は大いに影響を受けました。それが労働運動の出発点になったんです」
なるほど~。昭和の初めのおすもうさんたちによる労働運動が、今こうして日本の労働運動を率いるリーダーのひとりである鈴木さんへ大きな影響を与えてるというのが素晴らしい。私の持論「大相撲は日本の社会を映す鏡」って、まさに、これじゃないか!
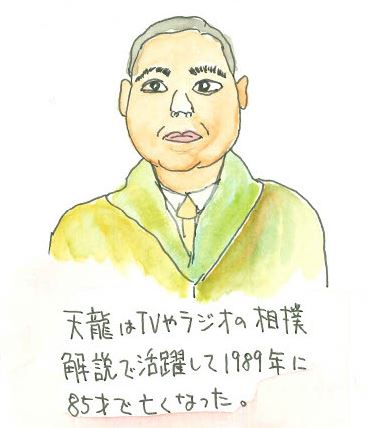
私もおすもうさんも「労働者」なんだ
出だし快調。それじゃ、鈴木さん、かつて労働運動もしたおすもうさん、「労働者」と言っていいんですか? それとも「フリーランス」ですか?
「ストレートな雇用労働者であるとは言えませんが、『準委任契約』という形で建付けは面倒でも『労働者性はある』と確認されています。裁判でもそういう判例がいくつも出ていますから。有名な例では、今は親方になった蒼国来(そうこくらい)ですね。2011年に八百長(やおちょう)をしたとして解雇されたことを不服として裁判を起こし、東京地裁で地位確認が証明されています」
労働の法律用語はなかなか難しい。難しいけれど、「労働者性が拡張されている」という認識があるんで、労働者だと言っていいんだそう。拡張とか言われると、何やら自分の身体がビヨ~~ンと引き延ばされる感じがして、蒼国来の身体もビヨ~~ンと伸びているのを想像する。しかし拡張されたからこそ、蒼国来の解雇も不当とされて土俵に戻ってこられたんだな。じゃ、今までそうやって解雇されたあの人もこの人も、もし裁判を起こしていたら? もし鈴木さんに相談していたら? そしたら土俵に戻れていたのか? そう言ったら、
「いつでも来てくれたら、一緒に戦いますよ!」
と胸を張る鈴木さん。あの人もこの人もユニオンという存在を知っていたら、人生が変わったかもしれない。
それで、ふと考える。おすもうさんにも労働者性が認められるなら、フリーランスの私も労働者なんですかね? 私に何かあったら、一緒に戦ってもらえるんですか?
「労働基準法と労働組合法がありますが、労働組合法では労働基準法上の労働者性よりも緩やかに認められるんです。和田さんにも労働者性は認められますよ」
そうか! この私も労働者なんですね! そうなると、がぜん、問題は身近になる。自分はフリーランスという宙に浮いた存在で、自分勝手に自由に生きるセ・ラ・ヴィな人生♪ 誰も守ってくれないと思い込んできた。そうじゃないのか!
ちなみに労働基準法は「労働条件の原則や決定についての最低基準を定めた法律」で、労働組合法は労働者が「労働組合を結成する権利」「使用者(会社)と団体交渉する権利」「要求実現のために団体で行動する権利」の「労働三権」を保障するために定められている。まずはこういう基本から学び直していかなきゃ、と今さらながら思う。
昭和の初め、まだ日本国憲法がなく、労働組合を結成する権利「憲法(28条)」もなくて、労働組合法もなかった頃に、団体交渉を試みた天龍たち、おすもうさん。法律で守られていない中にありながら、働く自分たちの権利のために立ち上がり、団体交渉を試み、結果的にはその職(おすもうさん)を追われた人もいるし、交渉は成功しなかった。でも、自分たちの権利のために自分たちで戦うおすもうさん―――土俵の外でも。その姿を知ると、そもそも私たちの多くは労働者なのに、働く私たち自身に関する法律や憲法やらを知らないで、自分が持っているチカラも権利も分からないまま日々働いていることに驚く。
私たち、ほんとはもっともっと力があるし、その力を使うべきなのに、ほとんど使うことがないのでは? あまつさえ、労働運動は「なんか、かっこ悪いよね」「みんなの迷惑になるよね」などというような思い違いをして、排除してしまいがちなことに気づかされる。何一つ良くならない社会、そこで働き、文句は言うし、絶望も十分している。けど、知ろうとしない、動かない。連帯しない。でも、でも、それじゃ、どうにもならないのかもしれない。私たちは、つながっていくべきなんじゃないか? 徐々に考え始めた。

「同一労働 同一賃金」の視点が抜け落ちていた
さて、話は最初の疑問へ。再雇用の話だ。
おすもうさんに労働者性が認められるなら、親方もそうなんですかね? 鈴木さんに尋ねる。
「親方は日本相撲協会との雇用関係があるので、労働者ですね」
となると、親方たちが65歳定年後にも70歳まで参与として再雇用されるのは、問題ないということになりますか?
「ありえることです。日本では1971年に中高年齢者の雇用に関する法律ができて、1986年には『高年齢者雇用安定法』と改称されました。それがさらに2021年に改正されて、70歳までの就業機会を確保するか、定年制そのものを撤廃することが努力義務になっています」
ああ、そうでした。私もそれ、前に読んで、学んだことがあります。相撲ファンのみなさん、そうなんですって、法律なんですって。
「ただ問題があります」
えっ?
「現役のときと変わらない仕事、もしくはよりきつい仕事をしていても、賃金が定年後は激減する、そのことが今あちこちで紛争になっているんですよ」
あああああっ! それってまさに、さっき、ついさっき私が再雇用の親方たちに押しつけようとしていたことじゃないか。
「日本では年金制度が崩壊し、定年後も働かざるをえないのが今の大きな問題です。望ましい姿ではありません、労働者にとって。しかも今、定年以降の労働条件は会社側のフリーハンドになっているんです。たとえば運送業界は人材不足が言われてますが、若い人を雇いたいがためにベテランの人を再雇用して、難しいコースを走らせてりするんです、賃金を半分とかに下げて、ですね」
そんな酷いことが起こってるんですか? 思わず言う。ついさっきまで自分の考えていたことは棚に上げて……。
「同じ仕事をしていたら『同一労働 同一賃金』にすべきところ、60歳でガクンと賃金が下げられた裁判があったんですが、労働者側が負けてしまっているんです。『社会通念上、60歳を過ぎたら処遇が下がるのは容認される』って。酷いでしょう? 社会通念上、ですよ。最高裁で確定しちゃったんですね。ベテランのドライバーさんが最高裁まで争ったのに」
私は言葉を失った。そんなことがあっていいのか? でも、でも、でも、私も同じことを言っていた。同じことを親方たちに押しつけようとしていた。
「社会通念上ということだけで確定されたのは、非常に問題です。法的な判断を放棄していますからね。労働事件一筋に取り組んでこられた故・宮里邦雄弁護士が生前に代理人で就かれていたんですが、厳しく批判されていました」
思い出せば、スーパーのバイトでも60歳以上になると同じ仕事をしているのに時給を下げられるのを見て、私も怒っていたじゃないか。そうだ。同一労働 同一賃金、すごく大事なことだった。なのに親方株の問題となると、それ、すっかり抜け落ちてしまっていた。
鈴木さんはさらに「同一労働 同一賃金」の観点から少しずつ高齢者の労働の改善について話してくれる。
「基本給を現役世代と同じにする権利を高齢者はまだ勝ち取れていませんが、手当においては差別してはいけないというのは権利を獲得しているんですよ。たとえば関東にあるとあるバス会社では基本給は安く、『なんとか手当』みたいなものをたくさん付けて『見た目総額』をかさ増ししていました。その会社には『金庫着脱手当』というのがありまして、これはバスに乗るときに代金を支払いますよね、あの金庫の部分を一定ルートの業務終了時に外して事務所に納品する仕事を『1回いくら』と決めていたんです。ところが60歳以降の再雇用者にそれが払われてなかった。それはさすがに裁判でも、年齢による差別はダメという判決が出ました」
そういう細かいところまで刻んでいくんですね?
「そうですよ。細かいところもしっかり話し合って権利を要求していかないと、経営者は削れるところは削り、社会通念上ということで高齢者には妥当な賃金を支払わなくていいとしてしまいますからね」
そういうことだよな。その論で行くなら、大相撲の親方再雇用も「あまり目立った仕事はしてないんだから、安くてもいいよ」とか「若い人の方がいいから、雇わなくていい」としてしまうと、結局は「高齢者は社会通念上でアンフェアな雇用でいい」ということにつながってしまう。「でもさ、大相撲の親方は105人しかいないのだから、後進に道を譲るために仕方ないんじゃない?」と言われかもしれないが、待て待て、それ、どこの会社にでも当てはまってしまう。「わが社は常に正社員は100人。高齢者の再雇用で5人雇うが、若い人も雇いたいので賃金はこれまでの5分の1にします」と、高齢者が以前と同じように働いているにもかかわらず、安く雇われる社会になってしまう。
それって、やっぱり問題だよね?