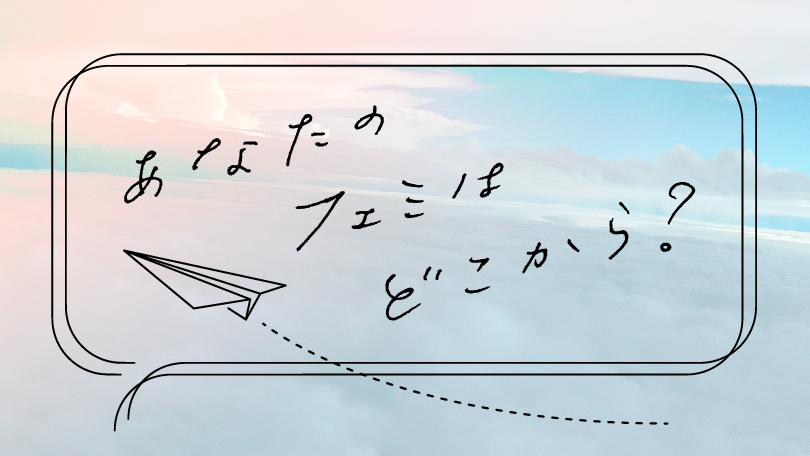
第12回
BLとフェミニズム(のようなもの) 水上文
[ 更新 ] 2024.09.13
わたしが中学に入学し、BLに出会ったのは2005年である。
それはつまり、ジェンダーやセクシュアリティに関する先進的な取り組みを妨害し、前に進もうとする人々を押し止め、押し戻そうとする動きが猛威をふるった時代に思春期を過ごした、ということである。バックラッシュとその余波の時代、そしてバックラッシュを稼働させる保守的な価値観がごく当たり前のものとして主流化していった時代。その頃、「フェミニズム」とはあたかも蔑称のようだった。
でも、わたしにはBLがあった。
フェミニズムはわたしに、抑圧を作り出す社会構造を把握し、構造をこそ批判することの重要性を教え、そして性とは避けがたい運命ではなく思考の対象になり得るものだということを、教えてくれた。けれどもわたしにとって、まずもって「フェミニズムのようなもの」として存在したのは、BLだったのだ。
どうしてBLが、「フェミニズムのようなもの」として感じられたのだろう?
それはわたしにとって、BLとはいったい何かを問うことそのものが、ある種のフェミニズムのレッスンだったからである。
中学生になってBLを知った時の解放感は、わたしにとって計り知れないものがあった。
幼い子どもとして過ごすこの社会は、端的に言って危険に満ちていた。
ひとりでいれば大人の男性がスカートに手を突っ込んできて、雑踏の中を歩いていればすれ違いざまにお尻を撫でられる。学校では男子たちが楽しげにスカート捲りに興じていて、混雑する電車に乗れば痴漢がいて、街を歩けば露出狂がいる。
性とは何かを知るよりもずっと前から、至るところに危険ばかりがあった。
だけどBLの世界でありさえすれば、そうした危険を忘れることができた。
このキャラクターたちは、どちらが「受け」で、どちらが「攻め」だろう? カップリングの好みはどんなものか、セックスの好みはどんなものか? こうした性的な話題の全てが、BLを読む女性同士であれば自分とはまったく関わりのない事柄として語れるのである。
いくら話しても自分が脅かされない安心感は格別だった。何も知らない頃から植え付けられた恐怖を意識することなく、性に関わることができるのだから。
ただ楽しかった。BLはわたしに、性を「楽しむ」ことが可能だと教えてくれたのだ。
けれども、この楽しみに疑問はつきものだった。
わたしは女性なのに、どうして原則として女性にスポットライトのあたらないファンタジーであるBLを求めるのだろう? ジェンダーやセクシュアリティをめぐる問題とBLへの偏愛は、いったいどんな風に絡まっているのか?
考えだすと止まらなかった。
思えばBL二次創作にハマった当時のわたしは、「女の子」向けの物語が、常に「男の子と女の子」をめぐるものへと変化していくことへの違和感を抱いていた。
たとえばわたしが幼い頃に愛読していた児童書は決まって、登場人物が成長するにつれ、異性間の恋愛が物語の重要な要素になり、私が大好きだった少女のキャラクターは少年のキャラクターと付き合うようになっていた。『赤毛のアン』では、アンがあれほど嫌っていたはずの少年となぜか恋に落ちていた。幾度となく読んだ『大草原の小さな家』シリーズも『少女ポリアンナ』も『ペギー・スー』も、あらゆる物語がそうだった。
どうして常にそうなるのか? なぜあらゆる物事は異性愛に収斂されていくのか?
自分がいったい何にそれほど戸惑っているのかさえ理解できないまま、中学生のわたしは、少年漫画のBL二次創作に夢中になった。
なぜなら、かつて少女たちが常に「素敵なレディ」になっていく一方で、少年たちは「素敵なレディ」になりはしなかったから。それに気がついた時、かつては見向きもしなかった少年漫画を、わたしは読み始めたのである。
少女漫画とは違って、少年漫画では異性間の恋愛が主軸として描かれることは稀だった。彼らは「友達」であり、「ライバル」であり、「同志」であった。そして世界を再解釈する技法としてのBL二次創作において、友情やライバル関係等の親密性と恋愛/性愛の境界は踏み越えられ、恋愛/性愛は異性間のみに限定されたものではなくなり、ジェンダー役割は男性間に置き換えられることで相対化され、解体される。
恋愛/性愛が自明視されることへの違和感、異性愛のみが唯一無二の道であるようなことへの違和感、そして成長と共に習得していくとされるジェンダー規範への違和感──なぜお転婆だった少女たちが成長するにつれ「素敵なレディ」になるのか、恋愛するようになるのか、それも決まって相手は男性なのか、わたしには理解できなかった。けれども世の中に溢れる物語では、それがまるで「自然」なものとして描かれていて、BLは当時のわたしにとって、唯一その「自然」から逃げさせてくれるもののように思えていた。
要するにBLは、異性愛/恋愛/性愛の規範や、女性ジェンダー規範に対するわたしの違和感を確かに掬い取ってくれていたのだ。
そしてBLにおける女性の不在は逆説的に、女性ジェンダーの不自由を浮き彫りにする。
たとえば、BL作品には、本当に幅広く様々な職業の男性たちが描かれる。
医者や弁護士、マフィアにヤクザ、教師、会社員。こうした設定のBLはありふれている。清掃業も、声優も、アイドルもいる。BLにはあらゆる職業が登場するのだ。では少女漫画では存在しない職業的多様性が、なぜ男性の物語であるBLでは可能になるのか? 女性を描く物語が「少女」ばかりなのはどうしてだろう? そもそもBLを読む前のわたしは少女漫画を読んでいたけれど、少女漫画が主に異性愛を主軸とするのはなぜなのか? いわゆる「女性向け」の物語において、少女たちはなぜこんなにも「男性から選ばれること」ばかりを夢見させられているのか?
問いのすべてはBLと共にあった。
だからわたしにとってBLについて考えることは、世界について考えることと同義だった。大袈裟に過ぎるように聞こえるかもしれないけれど、でも本当にそうだったのだ。
BLによって出発したフェミニズムのレッスンは、友人と共にさらに進んでいった。
BL好きであるという共通点によって仲良くなった同級生の友人が、フェミニズムという言葉をすでに発見していたのだ。
本格的なレッスンがいよいよスタートする。わたしたちは共に、フェミニストであることを公言しているBL作家・よしながふみの対談集を読む。そこで、バックラッシュが吹き荒れていたその頃、一般的にイメージされていたものとはずいぶんと異なるフェミニズムを発見する。あるいはBL文化の先駆者で評論家の中島梓(栗本薫)の本を読み、女性に対する社会的抑圧とBL文化の関係、BLによる解放について話しあう。中島が語る消費される少女の痛みに共感し、性的客体化からの避難場所としてのBL、という議論に胸を打たれる。レッスンは進む。社会の中にある、そして自分の中にもある女性嫌悪、異性愛規範、ジェンダー規範に気づかされる。BLを通してクリアになるものが、実にたくさんある。BLには現実のゆがみを映し出しながら、同時にそれを超えていくものがあるような気がする。
第一次安倍政権による保守的な空気が蔓延していたゼロ年代後半当時、BLを通してフェミニズム的に物事を考えるというレッスンは、革命的なものに思えていた。
もちろん、BLは基本的にはただ「楽しい」から存在している文化であって、特定の政治目標を持ったものでもなければ、性に関する体系的な理論を提供するものでもない。要するに、言葉の狭い意味で「フェミニズム」なわけではまったくない。
BLが常に先進的なわけでも、差別的ではないわけでもない。問題はたくさんある。今から振り返れば、当時のわたしたちの未熟なレッスンには確かに問題が多く含まれている。
だけどそれでも、そこには新しい何かがあるような気がしていた。
少なくともわたしにとってBLは、フェミニズムと無縁ではありえないものだった。何しろまさにBLを介して友人と話し合い、経験を分かち合い、痛みや違和感を言葉にすることを学んだのだから。これまでの議論を知り、言葉の狭い意味での「フェミニズム」にもたどり着き、そしてわたしの考えは形作られていったのだから。
あらゆるはじまりはBLだった。
わたしがフェミニズムに出会ったのは、BLのオタクだったからなのである。
水上文(みずかみ・あや)
1992年生まれ、文筆家。主な関心の対象は近現代文学とクィア・フェミニズム批評。『文藝』と『学鐙』で「文芸季評」を、朝日新聞で「水上文の文化をクィアする」を、柏書房webマガジン「かしわもち」で「クィアのカナダ旅行記」を連載中。『SFマガジン』で瀬戸夏子氏と「BL的想像力をめぐって」を共同連載中。企画・編著に『われらはすでに共にある──反トランス差別ブックレット』(現代書館)。

