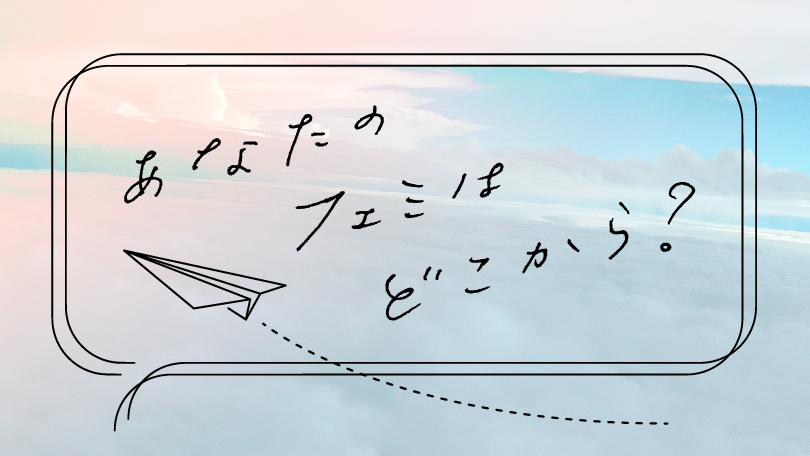
第7回
聞こえているから自分も言える 野中モモ
[ 更新 ] 2024.07.12
なので、このたび「あなたのフェミはどこから?」というお題をいただき、書きます書きます書かせていただきます、と軽率にお引き受けしたものの、改めて考えてみると思っていた以上に難しい! 当然ながらそれはこの社会に深く広く浸透している性差別に気づくところからはじまるものだから、どうしたって楽しい話にはなりようがない。自分がそうした認識を深めるきっかけになった出来事として思い浮かぶ経験はいくつかあるけれど、改めて向き合うには気力と体力が必要だ。さらに、それらを公にすることには、家族や友達、取引相手など、これまで関わってきた人々を気まずくさせたり、自分の立場を悪くしてしまったりするリスクも伴う。なんだろうな、銀行の口座に5億円ぐらいあってもう人生怖いものなしならどんなことだって言えるのだけど……。たぶんそれはみんな同じで、人間の経験のいちばん暗くて重い部分はまだ十分に語られていないのだ。
このように人生のさまざまな段階で性差別による不利益を被り、それを意識せざるを得なくなってしまったのは不幸なことに違いない。だがそれと同時に、自分がいまフェミニストだと人前で言えるのは、ある意味で特権的な立場にいるからでもある。たとえばイランでヒジャブ着用の義務化に抗ったり、タリバンが実権を握るアフガニスタンで女子教育の再開を求めたりしている人びとは文字通り命がけで行動しているわけで、仮に自分がそういう環境に置かれたとしてあんなふうに勇敢でいられるかどうか正直心もとない。そこまであからさまに権利を制限されていなくても、日本で生活するにあたって自分の身を守ろうと思ったらフェミニスト的な主張なんて大っぴらにはとてもできない、という人もまだまだ少なくないだろう。「なんとか現状に適応して日々を生きる」以上のものを人生に求めることが贅沢と言われてしまいかねないほどの疲労と諦念が社会に蔓延っているのをひしひしと感じる。
そこで性差別を黙って受け入れるのをよしとせず、勇気を出して異議申し立てをすることが決して無駄ではないと思えるのは、つまりまだ社会への信頼がほんの僅かでも残っているということ、絶望していないということだ。そう、驚くことに私はまだ生きていたいし、地球がいますぐ滅びるのは嫌だと思える。そもそも都会に生まれて大学を出て本とか出している時点でそうとう恵まれている。こんなに恵まれているのにこのていたらくですみません……と申し訳ない気持ちにならざるを得ない。
そういうわけで、洒落にならないほどつらい経験も自分が幸運にも出会えた立派な人たちや素敵な経験の話もなかなか書く気になれないのだ。だからここでは、たまたま学校という同じ空間で同じ時間を過ごした何人かの友達による、私の目にうつる世界をほんの少し変えたちょっとした発言や行動をいくつか紹介しておきたい。人間は衝撃的な事件をきっかけに変わることもあるけれど、そこに至るまでにはなんてことない小さなできごとがたくさん積み重ねられているものだ。決定的な啓示の瞬間は、ぱちんとスイッチを押して電気が点灯するというより、少しずつ掘り進めていたトンネルがついに開通して光が射し込むように訪れるのだと思う。この比喩もまだドラマチックすぎるかもしれない。
まずは私が東京の区立小学校に通っていた80年代半ば、5年生の秋のこと。参考までに書いておくと、団塊ジュニア世代で最も人口の多い学年で、児童数は一学年に200人ほどだったと思う。名簿が男女で分けられていた時代だ。
その秋、学芸会の演し物として学年全体でソーラン節を合奏することになり、各自担当する楽器は児童の希望をもとに決定された。私は特に演奏力に自信がなかったので、大勢いるリコーダーのひとりに収まった。そこで当時仲がよかったSさんは大太鼓を希望したのだけれど、なんと女子だからという理由で男子に譲るよう教師に説得されたのだ。お若いかたがたには意味不明だと思うが、その頃には「いちばんの花形ポジションは男子がやるもの」とされていたわけだ。この衝突が結局どんなふうに着地したのかは覚えていないけれど、何それひどい、納得いかない! と女の子たちで不満を語りあったことは忘れられない。
ちなみにSさんは自分と違ってすらりと背が高く運動神経が良くて成績も優秀な女の子で、地域でよく知られた高級マンションに住んでおり、後に東大に進学した。のびのびと育って波風を立てることを恐れない彼女の存在は、いろいろなことに気づくきっかけを周囲の子どもたちにもたらしていたように思う。
次に思い出されるのは、地元の公立中が荒れまくっているという噂に怯えて進学した中高一貫教育のミッション系私立女子校でのこと。ちょっと変わった宗派の学校だったのだけれど、毎朝の礼拝や週に一度の聖書の授業などで、日常的にキリスト教の教えに触れる機会があった。そこでクラスメイトのあいだで論議の的となったのが、新約聖書のマルタとマリアのエピソードである。
一行が歩いて行くうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女が、イエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足もとに座って、その話に聞き入っていた。マルタは、いろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。「主よ、わたしの姉妹はわたしだけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。」主はお答えになった。「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。」(ルカによる福音書 一〇章三八―四二節)
いや、マルタがんばってるのに可哀想すぎない? どう解釈すればいいの? 働きをアピールするのは押し付けがましいってこと……?
困惑にざわつく休み時間の教室の片隅で、クラスメイトのKさんは「そんなのマリアのほうが若くて美人だったからに決まってるじゃん!」と言ってのけたのだった。ジーザスだって男だから若い美人に傾聴されたら贔屓したくなるんだよ、という不謹慎ジョークである。
当時の私たちはまだ「ルッキズム」も「エイジズム」も言葉としては知らなかったと思う。けれど、そういったものさしでひとを値踏みする視線は日々感じ取っていたのだ。別のクラスメイトがある教師について「30過ぎてすっぴんはキツいよね」と言うのを聞いて、自分にそんな発想はまったくなかったから驚いた記憶もある。人気者で利に聡い彼女は、周りにいる人や普段見ているテレビを通じてそういう価値観を身につけたのだろう。それに、制服姿で電車通学している私たちは、えぐい痴漢に遭うことも珍しくなかった。自分たちのような子どもに一方的に絡んでくる一部の男性たちの不気味さ、得体の知れなさに日常的に直面せざるを得なかったのだ。
Kさんはいわゆる古き良きおたくだった。当時ロングラン上映されていた映画『モーリス』をひとつのきっかけに、『アナザー・カントリー』などのイギリスのゲイ映画や文学にどんどん詳しくなっていくのを、同じ熱は共有できなかったけれど近くで眺めていた(ちなみに『モーリス』がシネスイッチ銀座で公開されたのが1988年1月。近代映画社のムック『英国映画の美しき貴公子たち』が出版されたのが1989年の夏)。森茉莉の本もケン・ラッセルの映画もあの子が教えてくれたっけ……。権威を笑いとばしてもいいんだ、正しいとされているものを疑ってかかってもいいんだ、という態度を、彼女は控えめながら目の前で見せてくれたのだ。
この頃の友達ではもうひとり、Iちゃんにも恩がある。彼女はあるときプラトンの著作からタイトルを借りた映画ファンジン/同人誌を貸してくれた。当時はインターネットがまだ一般に普及していない時代、そうした自主制作メディアは自分よりちょっと年上のお姉さんたちの生の声を聞くことができる貴重な場だったのだ。今ではそういうのはSNSでいくらでも聞き放題だけれど。さて、その“薄い本”には映画のパロディ漫画や小説に並んで2〜3人の執筆者たちによる筆談も掲載されていて、その本編の「おまけ」的な手書き文字の何気ない一節が、私に強い印象を残すことになった。そこでは私も名前を知っていたある映画評論家が「わかってないよねー」と批判されていたのだ。そして、その記述そのもの以上に、それを読んだIちゃんに「そうだよね、わかってないよね!」と前のめりで同意を求められたことが、自分にとって画期的な体験だった。
その時にはまだはっきりと言語化できていなかったけど、あれは「発信すれば誰かに伝わる、黙っていたら伝わらない」という確信を心に芽生えさせたできごとだったと思う。電波メディアや報道機関や大出版社の上層部は2024年現在でも圧倒的に男性多数、いわんや20世紀に於いてをや。商業出版された本や雑誌には基本的に出版社の偉い人たちの承認を得た意見しか載っていないのだから、自主制作して自分の意見を表明することには意義がある。私はそういうことを10代の頃に、今より狭くて今ほど大々的には商業化されていなかった同人誌の世界でいつのまにか学んでいたのだと思う。たとえ直接的にフェミニズムを謳ってはいなくても、彼女たちの実践は確かにフェミニズムに通じていた。
以上、自分にとって印象深い思い出を書いてみたら、結局のところ都会育ちの恵まれた人の話になってしまった。そしてこれを言うと自分の甲斐性のなさがバレてしまってお恥ずかしいのだが、SさんもKさんもIちゃんもずっと会っていないし、今は何をしているのか知らない。けれど、彼女たちから教えてもらったことは確実に私を作っているし、感謝している。そういう薄くて細いつながりがたくさん撚り合わさって、「ここから」と点を打つことは不可能なフェミニズムを私の心に形作っているんじゃないかと思う。
野中モモ(のなか・もも)
東京都生まれ。翻訳者、ライター。訳書にキム・ゴードン『GIRL IN A BAND キム・ゴードン自伝』(DU BOOKS)、ロクサーヌ・ゲイ『バッド・フェミニスト』『飢える私』(亜紀書房)、ルピ・クーア『ミルクとはちみつ』(アダチプレス)、ヴィヴィエン・ゴールドマン『女パンクの逆襲 フェミニスト音楽史』(Pヴァイン)、ナージャ・トロコンニコワ『読書と暴動 プッシー・ライオットのアクティビズム入門』(ソウ・スウィート・パブリッシング)など。著書に『野中モモの「ZINE」 小さなわたしのメディアを作る』(晶文社)、『デヴィッド・ボウイ 変幻するカルト・スター』(ちくま新書)などがある。

