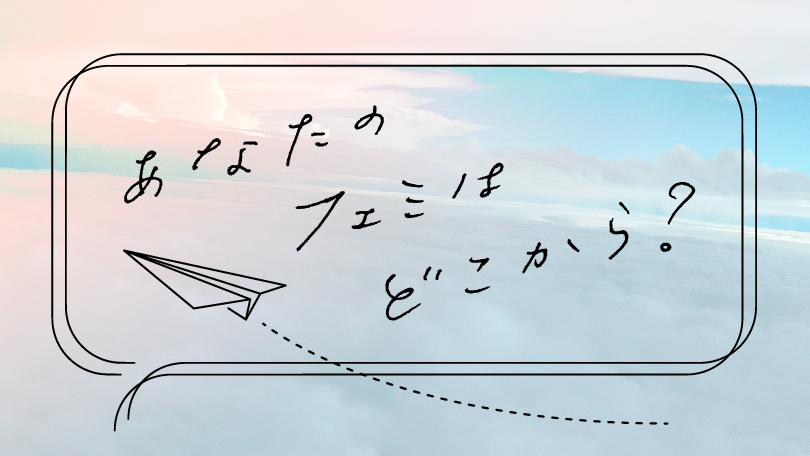
第4回
風が吹く野原が心の中にある 小川たまか
[ 更新 ] 2024.05.14
私の心の中にある心地よい場所の話。たぶんそれは、私の中のフェミニズムの土台を支えている。
◆校庭の向こうに国会議事堂の見える校舎で
登校初日から山手線の中で痴漢に遭い、それはしばらく誰にも言えないほどグロテスクな経験だった。1990年代の半ば、あの時代の高校生の多くがそうだったように頻繁に痴漢被害や、「援助交際」の声かけはあった。
けれど、それは当時の私にとって外の世界の話で、ドラクエで言ったら町や村ではない場所だから魔物が出るのは当然だった。学校の門を一歩くぐればもう、そこは楽園みたいに楽しかった。楽園に大人の捕食者がいなかったわけではないだろうが、大体の捕食者は陰気なので、なるべく群れて奇声を発したりバカでかい声で笑っていれば近寄られずに済んだ。
永田町に近い都立の進学校だった。グラウンドの向こうには国会議事堂が見えた。
校風はリベラルで生徒会は学生運動の頃に解散して以降ないまま。校則もあってないようなものだった。制服は一応あるのだが、着崩しても、当時流行っていたルーズソックスを履いても、他校のプリーツスカートを履いても、教師たちは何も言わなかった。部活のジャージで登校してきて、そのまま授業を受けてさえ問題なかった。
3年生になってからジャージのままで予備校へ行き、他校の生徒に「ジャージ着ている人がいる……」とヒソヒソ声で話されて初めて、あの学校で見て見ぬふりされている様々なことは他で通用しないのだと悟った。
校舎には下駄箱がなかった。外履きのままで校舎に入り授業を受ける。2階と3階は吹き抜けになっていて、休み時間には2階のちょっとしたスペースから3階の廊下にいる友達と話をしたりした。
授業は大学みたいに休講が多くて、私たちはそのたびに校庭の近くにある芝生とか、教室の外にあるバルコニーで寝転んで過ごした。校外のマックに行くこともあったような気がする。
ライターになってからいじめの取材をしたとき、ある研究者の人が言っていた。今の学校現場は、まるでいじめ実験をしているようなものだと。壁で囲まれた教室の中に40人を詰め込み、大人が校則によって縛る。受験や将来へのプレッシャーがあり、均質性の高い集団に見えて、だからこそそれぞれの家庭の経済格差や個体差が顕著になりやすい場所でもある。
そういう中で人間がヒエラルキーを作ったり、誰かをいじめたり、排除しようとしたりするのはむしろ当然で、まるでいじめを発生させるために人間を箱の中に閉じ込めているようなもの。そういう話だった。
私の通った高校にいじめがまったくなかったとは言わないが(私の知らないところであったかもしれないから)、90年代後半のガチャガチャした暗い世相の中、気難しい年齢の人間が集まっていたわりにはかなり落ち着いていた。そしてその理由は、放置主義に近いゆるい校則や、開放感のある校舎の構造、校庭の向こうに見える広い空と無関係ではなかったような気がしている。
東京には空がないと智恵子は言ったというけれど、東京の真ん中には、実は空がぽっかり空いている。あの頃の私はそんなふうに思っていた。
かつて名門だった母校の進学率はその時期目に見えて低迷していて、私たちが卒業した後に大きな改革が図られたと聞く。あれだけ多かった休講は、今はないはずだ。
◆女子が「女子らしく」ない共学の理由
「女子校育ち」がフィーチャーされるたびに少しだけ私の胸に去来するのは、私は共学だったけれども、共学もまちまちだぞという思い。
私の通った高校はなんだか女子がやたら元気だった。
男子生徒の多くが藤井聡太さん(竜王・名人)みたいな雰囲気で、つまりオラオラと正反対のタイプの人たちだった。男子が強がっていないと、女子が「女子らしく」しなければならない空気が薄くなる。
オラオラ系やスカしたタイプの男子(あるいは女子)がいないわけではなかったが、少なかった。校則があれだけゆるいのに、当時で言う「ギャル男」や「コギャル」は学年に1人いるかいないかの希少種だった。
温厚な生徒の割合が分水嶺を超えるとオラオラな人たちがオラオラしなければならない理由がかなり薄まる。そしてオラついた人がいないと、オラつく人の機嫌を取ろうとする子分も発生しない。
「温厚な」と書いたけれども、今振り返ってみてもっとぴったりとした言葉を探そうとするのであれば、あれはつまり、人と自分の区別がついている人間が多かったということなのだと思う。基準となる物差しは一つではないし、絶対でもないとなんとなく理解していると、人は誰かにマウンティングを取らずにすむ。
それぞれに得意分野があり、目標があり、好きなことや趣味があり、それぞれがそれぞれを頑張ればいいのであり、時と場合によってリーダーが順番に変わっていく、それは当たり前のことで、誰かと比べて優劣をつけている場合ではない。根底の部分で他人の目標へのリスペクトがあり、そうなると「スクールカースト」なんて意識している方が恥ずかしい、となる。
制服をどれだけセンス良く着こなすかとか、どの男子校のバッグを持っているか。そこで決まる何かがないわけではなかったが、流行に乗らない人たちに対しても尊重があった。
globeっぽく言うなら「みんなもそれぞれRULE持っていた」。くだらない男を取り合い、したことはあったかもしれない。
教師は楽だっただろうと思う。
彼らが多少ざわついたのは友人の女子2人が頭を丸めたときだった。屋上で、バリカンで。
理由は「水泳部なので、なるべく流線形に近づきたい」というギャグだったのだが、普段おっとりとした教師たちが、このときばかりは「女の子が頭を剃るなんて、何かよっぽどの……ことがあったのではないか」と気を揉んだらしい。
今思い出したが、当時大きな話題になった人気俳優さんのヌード写真集をお金を出し合って買って教室に置いたことがあった。これは担任教師が「ダメだぞ」と言って持ち去ったが、教員室に抗議に行った私たちと教師はお互い笑っていて、そこまで含めてイベントの一環みたいなものだった。
校舎内で鬼ごっこやかくれんぼをして、七夕には笹を教室に持ち込んで、ハロウィンでは仮装をしたまま授業を受けて、誰かの誕生日には後ろの黒板にバースデーメッセージがあり、クラス全員が一言ずつ手紙を書いた。毎日何人もの女友達とつるんで、ふざけ倒していた。
誰かに彼氏ができても、女友達の輪の中からそこへ出かけていくような感覚だと私は思っていた。ホームが女の輪で、彼氏との関係はアウェイ。それが逆になったのは高校を卒業してからだと思う。
◆風が吹く野原が心の中にある
私はといえば高校入学の頃は「スクールカースト」を内面化していた人間だったし、女友達に対しての期待をあまり持っていなかった。
小学校時代は男子児童を中心とする、誰かを順番に無視するタイプの大人が気づきにくいいじめがクラスを支配していて、いじめグループも含め誰もが怯えていた。中学校は少しマシだったけれど、クラスでいつも一緒にいる女子が陰で私の悪口を言っているのは知っていた。私も彼女を内心ではバカにしていたのだから同じようなものだ。
自分のいないところで何か言われている。
持ち物のダサさで笑われる。
ある朝、急に無視されて、考えても原因がわからない。
でもそれは自分が悪いらしい。
そういうことに怯えなくていい人間関係というのは、風が吹く野原のように心地良く、自由で、自分の心を解放する土台になってくれる。自分の心を守りながら毎日を過ごさなくてもいい人間関係があることを知ったのは、私の場合、高校に入ってからだと思う。
高校1年生の春、クラスの中で最初に友達になった子が、少し離れたところにいるグループと仲良くなりたいと言った。あ、そうやって仲良くなっていいんだ、なれるんだという発見は私にとって大きかった。女子は2、3人で固まってなくてもいいんだ。
こんなことは取るに足らないと思う人が多いかもしれないけれど、私にとっては人生の中の忘れられない一瞬だった。
大学生や社会人になってからの人間関係に、辟易したことはもちろんある。けれど、あの当時の経験があることで、私は人を信用することができていると思う。
逆に言えば、あの3年間の経験がなければ、人をヒエラルキーの中で順位付けして誰はどのぐらいだろう、自分より上か下かと考えることや、その競争に身を置くことに無自覚なままだったかもしれない。
まるで永遠のような3年間で、私は卒業後に人生が続くことが信じられなかった。
楽園は温室でもあり、温室から出た後の肌寒さで大学に入学した頃はよくくしゃみをしていた。ジャージを着て予備校に行ってドン引きされたように、私は私立のおしゃれ大学の中で浮いていた。温度差のバランスを取るために試行錯誤しているうちに20代半ばになった。
◆対等を習得した社会を
最近、話を聞いた80代のフェミニストがこんなことを言っていた。「人との関係が対等であること。運動の中でも対等であること、それが大事だ」と。
人間は組織やコミュニティの中でどうしようもなくヒエラルキーに飲み込まれていくことがある。社会運動の中での、権力勾配を利用したハラスメントや、誰がより自分を犠牲にして活動に貢献しているかといったマウント合戦のような応酬を見聞きすることもある。若い人の運動の中でも、フェミニスト同士でも。
対等な関係とは、どうしてこんなに難しいのだろうと思う。まずお互いが対等な状態というものを経験、理解していないと成り立たないし、その上での継続的な努力が必要だ。
私と同年代の、医療の専門家であるフェミニストから聞いたのは「対等な関係の構築は性格ではなくスキルの問題」という話。これはいいことを聞いたと思った。どんな風に生まれてどんな境遇で育ったとしても、対等な関係はいつからでも習得することができる、そう思いたい。多くの人が自分の性格や運命を呪わずにすむのであれば、それに越したことはない。
子どもたちが意地悪の呪縛から自由になって、大人たちがマウンティングやヒエラルキーから解き放たれた社会を私はいつか見たい。そのヒントはすでにあると思うから、人間の知恵を信じていきたいのだ。
小川たまか(おがわ・たまか)
ライター。1980年東京生まれ。Yahoo! ニュース個人「小川たまかのたまたま生きてる」などで、性暴力に関する問題を取材・執筆。著書に『たまたま生まれてフィメール』(平凡社)、『告発と呼ばれるものの周辺で』(亜紀書房)、『「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。』(タバブックス)、共著に『わたしは黙らない――性暴力をなくす30の視点』(合同出版)など。『エトセトラvol.11 ジェンダーと刑法のささやかな7年』(2024年5月28日発売/エトセトラブックス)で特集編集を務める。

