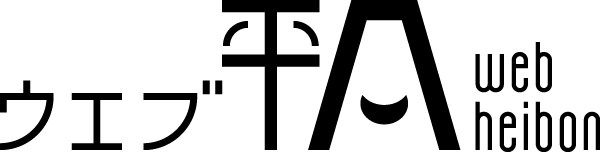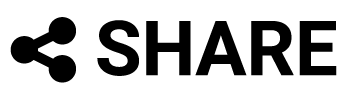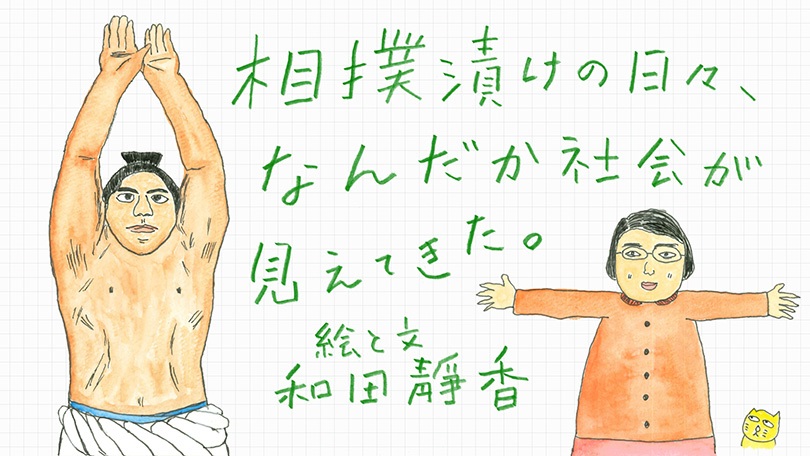
第9回
「差別」を理解していなかった
[ 更新 ] 2025.08.08
そうか、“差別”とは? からスタートしないといけなかったのか。
今さらそれを知る、2025年夏である。
唐突に始めてしまったが、いつの間にか前回の更新から1年と3カ月が経っていた。更新しなかったのではない、更新できなくなってしまったのだ。何せここのタイトルは「相撲漬けの日々」だし。前回の原稿を書いた時点で私は2003年から20年以上見続けてきた大相撲をピタッと見るのを止(や)めた。“漬け”から飛び出て、体中に付いたアカを落としたというか。白鵬を追い出そうとする団体の興行など見るものか、と鼻息を荒くしていたのだ。外国人への差別を平気な顔して行う団体は許せない、とこぶしを挙げてきた。大相撲を見ることは自らも「差別に加担することになる」と強く思って、嫌悪感さえ抱き、テレビのニュースで大相撲のことが始まると、躊躇(ちゅうちょ)することなくテレビの電源を消した。
ところが、そんな私の決意をよそに周囲の相撲ファンたちはこれまでと同様に大相撲を見ているようだった。あれれ? そうなの? 白鵬をあんなに応援してたのに、見るの? なんだかひとりでずっこけていたんだけど、でも、誰にでも自分の心を決める自由はある。自分がどうするか、決められる。憲法第十九条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」を、1年と少し前に書いた第8回の原稿でも引用した。人がどう思ってもどう感じても、それが他者の人権を脅かさない限り自由でいい。私が「見るの止めなよ」なんて言うのは違う。違うんだけど、モヤる。モヤモヤと私の正義が、私のなかで葛藤していた。
白鵬に迷惑をかけたくないから黙っていた
そして大相撲は見なくても、「いつ白鵬は師匠として復帰できるのか? 宮城野部屋はまた独立した部屋として復帰できるのだろうか?」ということだけは、ずっと見守っていた。でも、それが徐々に私のなかではあきらめに変わっていった1年だった。
ここで相撲ファンについてちょっと説明したい。相撲ファンには「後援会」なるものに属し、「タニマチ」となって相撲部屋と濃い付き合いをする人がけっこういる。その人たちによる寄付があるからこそ、親方と弟子が衣食住を共にする相撲部屋の運営が廻っていくのだ。相撲協会からの育成費だけじゃ、十分じゃないだろう。相撲部屋へ稽古の見学に行ったとき、寄付で寄せられた米俵だの、大根山盛りだの、とんでもない量を何度か目にしたことがある。ある意味
で彼らは大相撲を育ててきた人たちだが、代わりに「力士と仲良くなる」という権利を手にする。それがいいことなのか悪い事なのか私には判断しかねるが、若い力士がタニマチのおじさんやおばさんのお酌に回ったり、自慢話を聞かされて大げさにうなづいたりしなきゃいけないのは、大相撲という興行の興行たる部分なのかもしれない。
で、そうした人たちから閉鎖中の宮城野部屋について「どうも宮城野部屋は戻らないんじゃないかと言われているよ」「宮城野部屋の再開時期については、相撲協会の理事会で議題にも上がらないらしい」という情報が、コソコソと耳に入ってきた。いや、正確にはLINEで送られてきたから、目に入ってきたんだ。私はそれをパソコンで読んで(ふだん、LINEはパソコンで見ている)、ふざけんな! と怒りに震えた。
そして同時にタニマチな彼らから、「今はおとなしくしておいた方がいい」という声も聞こえてきた。あ、これもLINEだから目に入ってきた。
「宮城野部屋を擁護し、相撲協会を叩く記事が出たり、騒ぎが大きくなったりすると、白鵬が呼び出されて八角(はっかく)理事長に激怒られるらしいよ。部屋の再興が遠のくからさ……」
それを聞いて、えっ? となった。そんなのひどい。でも、たしか以前、現役時代の白鵬が、自らのことが書かれている記事について理事長に謝罪に行ったというのを週刊誌で読んだことがある。白鵬自身が書かせてるわけじゃないのに、白鵬を擁護し、協会を批判する記事が出たら、白鵬が謝罪に行かなきゃならない。なんじゃ、そりゃ?
じゃ、でも、もし、そのとおりだとすると、ここで私がむやみに動いて記事化したり、キャンペーンなど張って騒いだりしたら白鵬に迷惑がかかるかもしれない? ここはおとなしくしていた方がいいのかもしれない? そう思ってしまい、私は何もしないことにした。大相撲も見ていないことだし、声を上げることはせず、黙っていることにした。
陳情に行き、国会で取り上げてもらった
でも、そうやって黙る前に、ひとつだけ私は自分にできることをした。
宮城野部屋の閉鎖が発表されてまだザワザワと騒がしかった2024年4月、参議院議員の杉尾秀哉(ひでや)議員に陳情に行ったんだ。杉尾議員は当時、内閣委員会に属していて、ちょうど公益法人法の改正について委員会で質疑をするということを耳にした。
さっそく事務所に電話をしてお願いし、予算委員会に出席していた杉尾議員の時間が空く夕方に、議員会館を訪ねた。陳情とは「国や地方公共団体などの公共機関に対して、その実情を訴え、一定の措置を行うよう(または行わないよう)要望する行為のこと」。私たちの権利。日本相撲協会は公益財団法人であり、内閣府が公益財団法人の管轄である。
執務室の小さなテーブルをはさんで椅子に向かい合って座ると、私の「宮城野部屋が不当に閉鎖されている」という「国会でそんな話すんの?」というような、なんだかちょっと場違いにも感じる話を杉尾議員は真面目に聞いてくれた。これまで白鵬が受けてきたバッシング、それが外国人差別に起因するのではないかということ、「入日本化」のこと、白鵬だけが書かされた誓約書のこと、今回のことが過去に例がないこと。私は友達に聞きながらまとめた資料を手渡し、いささかアワアワと慌てて話すと、「わかりました!」と、内閣委員会の質問に織り込んでくれることになった。
実は、エラソーに言いながらも陳情に行くのは初めて。何を持って行けばいいのか? どう話したらいいのかまったくわからないままだったのだけど、とにかく杉尾議員は真剣に話を聞いてくれて、そして公益法人法改正の質問に、このことを組み込んでくれることになった。みなさん、市民の声は国会に届けられるのですよ!!
そして当日、国会中継を見ていると、杉尾議員はまず加藤鮎子大臣(内閣府特命担当大臣/当時)に公益法人のガバナンス強化の視点などを質問し、それから宮城野部屋の閉鎖という処分について公益法人の行政担当室長(当時)に聞いた。
「暴力事件で部屋の閉鎖というのは初めてだと私は聞いております。処分の基準自体が極めて曖昧。そもそも、公益法人というのは自律的なガバナンスの充実を求められているわけですけれども、これができていないからこういうことになっているんじゃないですか」
これに対し、「再度の報告要求を行い、監督措置を適切に講じてまいりたいと考えます」という答弁があり、何度か質疑と答弁があって、最終的に杉尾議員から「最低限、日本相撲協会に記者会見をさせてください。お願いします、監督官庁として」とスポーツ庁への要請が行われた。そして、スポーツ庁からは
「私どもが作っておりますガバナンスコードを踏まえまして、引き続き、そのコンプライアンスの徹底、ガバナンスの確保を求めるとともに、必要に応じた説明を求めるということで、私どもの方からも引き続き相撲協会の方にも対応していく」
という答弁があり、加藤大臣からも「集中的な立入検査、これを行ってまいります」という答弁を引き出したのだ(第213回国会 参議院 内閣委員会より)。
す、す、すばらしい!!! 行政担当室長からの「再度の報告要求」、スポーツ庁からの「説明を求める」、大臣からの「立入検査」という答弁を得て、私はパソコンの前で小躍りした。か・ん・ぺ・き! ありがとうございます杉尾議員、これで相撲協会もしっかりとした検証と報告をしないとならないだろう。記者会見を開く! 市民のチカラを舐(な)めんなよ! と思った。
白鵬が日本相撲協会を退職
ところがだ。監督官庁が求めたにもかかわらず、日本相撲協会は記者会見を開かなかった。代わりになのか? 懇意にしている(?)スポーツ新聞に八角理事長のインタビューを載せて、お茶を濁して終わってしまった。加藤大臣の言った「立入検査」が行われたかどうかは不明だ。国会で質問してもらい、議事録は残った。しかし、公益法人であるはずの日本相撲協会は、何もしなかった。
ものすごくガッカリした。自分の非力を痛切に感じた。市民のチカラは及ばないのか? そして、こうした行政からの求めに、公益を重んじるべき団体でさえも応じない、以前なら考えられない「やったもん勝ち」とか「言ったもん勝ち」がまかり通ってしまっている社会になってるんだということも、改めて感じた。
そして1年3ヵ月。私は大相撲を見ることはなく、押し黙る日々が続いた。大相撲は2003年から見ていた。1年に6回、2ヵ月に1度、2週間ある。その間はソワソワしながら楽しく見ていたんだから、見なくなるのは大きい。他にこれといった趣味もなく、手持ち無沙汰になり、私はすっかり“X廃人”へとなり下がった。私から大相撲をとりあげたんだよね、今の相撲協会執行部の行いがさ。本当にくやしい、本当にくやしいよ。くそっ。
そして、その日がやってきた。2025年6月2日、白鵬こと、宮城野親方が相撲協会から退職するとメディアが一斉に報じた。この1年、私たちファンや、白鵬本人にも全く当てがないまま時間が過ぎた。それは刑期がわからないまま牢獄に入れられているようなものだったと思う。そもそも協会の思惑で決められた閉鎖だった。
「宮城野親方は最近、『もし戻れたとしても、次に何か(周辺で不祥事が)起きれば、また厳しい処分になると思う。私は(協会から)目をつけられているから。ハラハラしながら過ごすのは、もう耐えられない』と言うようになっていた」(「朝日新聞デジタル」2025年6月2日付)
これを読んで、涙が出た。どれだけ辛かったろう。この間、私は相撲を見ずとも、相撲を見ているスモ友らのXやインスタへのポストはしっかり見ていた。それで彼女らが国技館などで撮った白鵬の顔から“表情”というのが消えたというか、ペタッと貼りついたような顔をしているのがずっと気になっていた。ついに耐えがたくなっての決断だったんだな、とよくよくわかった。
それで私は白鵬のこれが「退職」であったことから、相撲部屋の親方は日本相撲協会と雇用関係にあり、白鵬がこのような目に遭うのは労働問題としてあり得ないという原稿をウエブ記事として発表した。多くの人に「納得」と言ってもらえ、その問題点を伝えることはできたけど、実は私は意図的にここから「差別」という言葉を省いていた。ずっと差別だ、差別だ、と言ってきたのに、あえてそれを抜いていたのだ。
「差別」という言葉を避けた
どうしてか? 労働をテーマにした記事であるため混乱するといけないから抜いたというのもあるけど、それは自分への言い訳になる。宮城野部屋が閉鎖になってこの1年あまり、いや、ちがうね。白鵬が現役の頃からずっとずっと、私がXなどのSNSに「白鵬への外国人差別がある」と書くたびに「こんなの差別ではない」「差別、差別うるさい」「差別と言い張るのは無理がある」「差別とかいう人、うざい」と言われ、白鵬に特定した迫害があることは認めながらも、「差別ではなくて、これは協会によるただのイジメじゃないか」とか、「差別とかいう人と一緒にされたくない」というリプライがきた。イジメではあっても、そこに差別はない。差別という言葉をなぜかあらゆる人が忌避(きひ)する。一般の人だけじゃなく、好角家の作家が「いちいち差別という人たち」というようなことを書いてるのもXで読んだことがある。
こうなると、人間って、自分が思ってるよりずっと弱い。
そう言われ続けると、もしや私が間違えてる? 私が悪いのかも? と思ってしまう。そして、私がまた問題を大きくしたらいけないのではないか? と考えてしまう。
宮城野部屋閉鎖の際に私は「毎日新聞」の取材を受け、入日本化について言及し、「これは外国出身の力士が相撲を取るには日本の文化に染まりなさい、というかつての日本の植民地政策に似た考え。それらを考えると、宮城野親方に対する処分には恣意(しい)的なものを感じる。外国出身力士に対する差別から目をそらしては、今の日本社会は良くならないと思うのです」と話した(2024年4月21日付)。その記事を引用しながら、差別があるとXにポストしたときには、また「差別なんかじゃない」「これは貴乃花のときと同じでイジメだろう」「いちいちなんでも差別にするな」とたくさんのリプライがきた。なにより大相撲ファンから、そういうリプライが山のようにきたのだ。差別だ! と言う私が間違えているとされ、信用できない人にされてしまった。
そんなことがあったから、ここでまた「差別だ」と書いて事(こと)を荒立てるより、労働問題にしぼって白鵬への共感を高めた方がいいかも? と私は考えた。その方が白鵬への共感が集まり、白鵬のためにもなる。差別という言葉は使わないようにしよう、そう決めたのだ。
そして、差別という言葉を一切使わない原稿を書いた。結果的に多くの人に読まれ、共感も得た。「この人の言うとおりだ」と、私の記事はたくさん引用され、Xでポストされていた。けど、私のなかではモヤモヤが大きく残った。
これでよかったんだろうか?
「差別」への理解不足
それから1ヵ月もしないうちに、参議院議員選挙がやって来た。本当だったら、物価高やコメ不足からの消費税減税とか、年金問題、就職氷河期世代の支援、政治資金規正法、防衛費拡大問題などが争点となるはずだったのに、いざ始まってみたら、参政党による「日本人ファースト」という、とんでもないキャッチコピーが垂れ流され、「外国人は優遇されている」というありもしない作り話が真実のように語られ、争点に祭り上げられてしまった。「外国人が生活保護を不当に受けている」「外国人が日本に治療目的できて国民健康保険を悪用してる」など、ありもしないデマに煽(あお)られた。上がらない賃金、物価高、生活は苦しい。それなのに大勢の外国人が「安い安い」と日本にやってきては、豪遊している。外国人という敵が設定され、大勢が真実を知ったと目を輝かせた。信じる人に「優遇なんてされてないよ」と反論すると、「でも外国人は怖いから」と言われた。そう感じてしまうその人の感情を、どうしたらいいんだろうか。
分からないまま、それでもともかく、差別的なデマを打ち消していこうと、SNSでファクトを表示して反論すると、驚くことに「日本人ファーストのどこが悪い?」「ここは日本なのだから日本人がファーストであるのはあたりまえだ」「いい外国人なら居てもいいけど、悪い外国人は出て行け」と、ファクトは無視され、デマが肯定され、差別の上塗りをする発言がSNSにあふれた。何度リプライを送っても「これは差別ではない」「日本で日本人が優遇されてあたりまえだろう」と言われた。それはデマだから、と繰り返し言ってもまったく通じなかった。
意見の違う人とも対話をする必要性はすごく感じている。差別を煽る政治によって、市民が分断されるのは良くないとわかっている。でも、どうしてもSNSでは話が通じない。リアルでの知人にもうまく伝えることはできなかった。
そうなんだ。
差別とは何か? まず、そこから理解されていなかった。その事実に驚き、全身がワナワナと震えるような気がした。
私がずっと「白鵬が差別されている」と言えば言うほど、「それは差別じゃない」と言われてきた。そこにリプライすれば、「日本人の横綱が誕生してほしいと言ってるだけだ」「白鵬は相撲の手が汚いからダメだ」「大相撲は日本のもの。国に帰れ」とさらに反論された。こちらがいくら「差別ですから」と伝えてもまったく伝わらず、ののしられた。ちょっと過去のXを検索してみたら、「今白鵬が非難されるようになっているのは、所作(しょさ)、暴力的な相撲の取り口、的外れな言動などが原因である。そこを理解しようとしない直(す)ぐに人種差別とかいう」と、私に対して主張するポストが検出された。2018年の投稿だ。こうやってずっと変わっていない。
大相撲の土俵は、日本社会の鏡。そもそも、差別とは何か? がよく理解されていない。だから、どんなに白鵬は差別されていると言っても言っても通じなかった。そして今、「日本人ファースト」という言葉は差別そのものだと言っても言っても理解してもらえない。「差別ではない!」と胸を張って反論されてしまう。こちらがどんなに「それは違う」と言い、理由やファクトを述べても、いつまでも平行線で対話が成り立たない。
そうか、そうだったんだ、差別だ! とどんなに言ったところで差別が何かが理解されていなければ話は通じない。それに今さらのように気づかされた。そうか、差別そのものが理解されていなかったんだ。
私は差別に加担した
じゃ、差別ってなんだろう? 「区別」とどう違うのか?
『差別の哲学入門』(池田喬・堀田義太郎、アルパカ)という本を手繰(たぐ)れば、人は色々な場面や環境で人を区別して、その扱いを変えていくが、そのすべてが差別にはあたらるわけではない。しかし、区別をする一方の人にだけ「不利益を与える」のであれば、差別となる。さらに性別とか人種、国籍、宗教、出身地、障害、年齢、貧困といった「特徴に基づいた区別」をするのは、「悪質な差別」となる。「差別とは、人々の間に何らかの特徴に基づいて区別をつけ、その一方にのみ不利益を与える行為である」という。
書いていて、これはきちんと教えてもらい、学び、経験を積まないと、理解するのが難しいかもしれないと思った。私自身も思い返せば色々なところで差別をしてしまっているし、そのたびにハッとして、反省し、正してきた。一朝一夕にはいかない。繰り返しの学びがたいせつだ。
そして今回、改めて差別についてあれこれ考えることになり、「差別を許さない」と声に出すことは自分自身に対する戒めになると気づいた。誰かがXで『「差別する」の反対語は「差別しない」ではなく、「差別を許さない」だ』と書いていた。その通りだと思った。差別をしないために、私たちは差別を許さないことがたいせつだ。差別があれば、常にそこには声を出せない被害者がいる。だから、声高に「差別を許さない」と叫ぶ必要があるんだと思う。
ああ、それなのに、なんてことだろう。この1年3カ月、私は黙り込んでいた。白鵬に迷惑がかかるといけないからという理由をつけて。しかし、黙り込んでいた挙句、結果的に白鵬は「もう耐えられない」と言って退職した。大相撲界から排斥されたのだ。
白鵬がスポーツ界ではありえないほど酷い差別を受け続けていたのに、私は黙り込んでいた。
この事実に気づいて、私はガーンとなった。
むろん、私が黙り込んでいたからこうなったわけではない。でも、私は「黙り込んでいたワンオブゼム」だ。もし、今回のことを、「これは差別である」と大相撲ファンみんなが理解し、立ち上がり、「差別を許すな!」と声を上げていたら? たとえばサッカーのファンのようにバナーを作り、国技館に掲げ、抗議の声を上げていたら、どうなっていたか?
そんなことを誰がする? でも、サッカーのファンで、やってる人はいる。大相撲ファンがやれない、やらなくていいってことはない。そこまで出来なくても、もっともっと私たちが「これ差別だよね。おかしくない?」と言えていたら?
これだけ長く、外国人が大相撲の力士として働くことの問題点が指摘されてきているのに。外国籍の人も部屋に入門できるが、各部屋ひとりだけとか。親方になるには日本国籍をとれとか。入日本化とか。明らかに外国人に対する差別は存在しているのに。そして白鵬は排斥されたのに。
「これでよかったんだろうか?」
と書いたが、いや、よくなかった。
少なくとも私は、反論し続けるべきだった。白鵬は差別されてる!と怒り続けるべきだった。中継を見るのを止めるとか、知らん顔を決め込んでちゃいけなかった。だって私は「これは差別だ」と明確に思っていたんだから。思っていながら、誰かの反論を恐れ、声を挙げるのを止めて、あきらめた私は、結局はその差別に加担したも同じだ。排外主義の考え方で白鵬を排斥したその責任の一端を、私も担った。なんてこった。
今回の白鵬の退職で、私は痛みとともに、改めて差別について考えさせられた。私たちが断固として、差別を許さないことがたいせつだ。そのためにはまず、差別について学ぶことが必要になる。私もさらに学び続けていきたい。