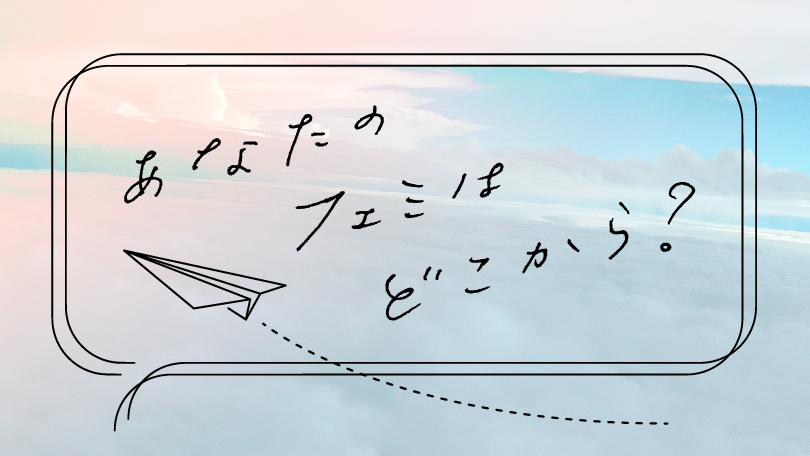
第14回
シルバニアで遊べない子 長田杏奈
[ 更新 ] 2024.10.18
野猿のような子どもだったが、着せ替えごっこは好きだった。同じお人形でも装いが違えばキャラクターやライフスタイルまで違って見える。オーロラ色のチュールドレス、ブラックのレオタード、ギンガムチェックのヘソ出しシャツにデニム……。リアルでは味わえないおめかしの振り幅を、自在に行き来しながらロールプレイするのが楽しかった。ある日を境に、人形遊び仲間が一斉に「シルバニアファミリー」に鞍替えした。ファッションに重きを置く着せ替え人形とは異なり、シルバニアで大事なのは家と家族。戸建てにミニチュアの家具や小物を集めて配置するドールハウス的要素と、家事・育児・ご近所付き合いといった家族ごっこが遊びの核になる。これが私にとっては全く面白くなくて、一瞬で飽きて「あーつまんない!」と不貞腐れた記憶がある。くまやうさぎのお人形はファミリー単位で販売されていて、父母に男女1人ずつの子どもがいる設定。初期のお母さんはエプロン姿が標準装備で、着道楽とは程遠かった。
私のフェミの萌芽は、スカートめくりにムカついて用心棒を買って出たり、「ジェニーちゃん」や「エリーちゃん」の世界からエプロンの「お母さん」(実はうさぎのお母さんには「テリー」という公式名称がある)への移行にどうにも馴染めなかったあの頃にきっとある。おめかしで自己表現するのは好きだけど別に「ケン」のためじゃない。「家」や「家族」の名の下に個が消える空気やジェンダーロール(おばあさんは洗濯、おじいさんは芝刈りのような性別役割分業)にモヤる。この感覚は、子どもの頃から今までずっと地続きだ。
母はシングルマザーで、美容部員として働きながら私を育ててくれた。家にはシーズン毎の新色のサンプルを重箱のようにまとめたパレットがあり、留守番の間に鏡台の前でおままごと感覚であれこれ試すのが楽しみだった。当時はイエベやブルベ(美容好きの間でお馴染みの、似合う色を判定するカラー診断)などの概念はなく、いつもとりあえず全色塗ってみるところから始めた。目の形は同じでも、グリーンのアイシャドウを塗るとどこか知的に、ブルーだとクールに、パープルは妖艶に、ピンクだと可愛らしく見えるのがひたすら不思議で、そこには目を大きく見せたいという願望はもちろん、「きれいになりたい」という気すらなかった。海外のお土産で100色近いクレヨンセットをもらい、とりあえず画用紙に全色書いてみよう! となった、あの衝動に近いのではないか。美醜への刷り込みやこだわりの前にカラーバリエーションへの好奇心があり、画用紙の代わりに自分の顔があった。おめかしの振り幅を楽しむという意味では着せ替え人形に近いけれど、メイクは直に塗って自分と一体化させることで生じる変化がより面白く感じた。家で1人で塗って遊ぶだけで満足だったので、高校生になっても週末だけ色付きのリップを塗るぐらいで、本格的にメイクをして外に出るようになったのは大学に入ってからの話だ。
なお、スキンケアの重要性を感じ始めたのは、小学校3、4年生の頃。アトピー性皮膚炎になり、小さい頃から通っていたスイミングをやめた。お医者さんの薬でひどい症状は治っても、肌がカサカサしたり、皮膚が部分的に脱色してしまう「はたけ」になったりで、微妙な不調や不快をどうにかしたかった。母に買い与えられて、ティーン向けの保湿美容液を使うようになるとコンディションが安定したし、何より自分の肌に触れている時間はホッと安らいだり時にはシャッキリしたりと気分が良かった。
私にとっての美容は見たり触れたりの感覚的なものだけでなく、毎度言葉と結びついていた。子どもの頃から、絵本にとどまらずお菓子の箱に書いてあるコピーや説明まで、印刷されている文字をいちいち読んでしまう癖があったので、母が持ち帰るたくさんの雑誌や社内向けのテキストを、とにかく一言一句漏らさず読んでいた。メイクが時代でどう変遷してきたかの年表、パーツのバランスを変えることで印象がどう変わるか(例えば眉を長くするとエレガント、短くするとフレッシュ)などの基本的な知識、限られた文字数の中でプロダクトの魅力やメイクのHOW TOを伝える言葉がじわじわと蓄積され染み込んだ。他の国の言葉や惑星の配列なんかも最初に触れたのはコスメを通してだったはずだ。母から何か具体的なことを教わった記憶はないが、自然と美容のことが一通りわかる門前坊主に仕上がった。
美容は好きだがあくまでも生活のオプションであって、人生設計の主軸にはかすりもしない予定だった。けれど結局、働き始めた私を助けてくれたのは、日に12時間勉強していた法律とか先輩に怒られながら暗記した営業トークではなく、努力のどの字もなく身につけた美容とそれにまつわる言葉だったのだ。暗黒期とも言える会社員時代を経て、週刊誌で5年。いろいろな題材の記事を書いたなか、いちばん勘所がわかってスラスラ取り組めたのは、子どもの頃から親しんできた美容。20代後半でフリーランスに転身したのをきっかけに美容ライターを名乗り始め、以来約20年ずっと続けている。ただしアクセントは「美容」ではなく「ライター」にある。私自身が美容のすごい人なのではなく、美容の達人に取材した内容を書くのが仕事。相手の話や魅力のエッセンスをお節や幕の内弁当のように隅々まできっちりきれいに詰め、シンプルで簡素なのに全てあるような小宇宙を構築し、フルーツそのままをいただくよりフルーツの本質が引き立つ巴裡小川軒のケーキ職人(食べればわかる)みたいなライターになりたい!
要は自らの気配を消して相手のエッセンスを伝える黒子に徹することにこだわりがあったのだが、職歴を積むに連れて世の中でニーズがあるとされている王道の美容にまつわるメッセージと、私が好きな美容にはズレがあることに気づいた。例えば、高くて狭い美意識をベースに毒舌でダメ出しをしてイマイチに撮ったBeforeと盛れてるAfterを並べる、「愛され」「モテ」というキーワードをつければアクセスを稼げる、「マイナス◯歳」「美魔女」か「オバ見え」の極端に振れる「アンチエイジング」、「浮かない」「イタくない」、「母として妻として女として〇〇(職業)として」の役割網羅型コピーとセットの「ごきげん」ブーム、プレステージブランドのイメージモデルはなぜか白人女性、カバーガールはパッチリとした目の二重ばかり……。どれもメディアやメーカーが悪代官顔で仕組んだのではなく、読者やユーザーのニーズや熱気と呼応し、良かれと先読みしマーケティングすることで生み出されたものではある。でも、私の好きな美容って、これだった⁉ そういうんじゃない美容の話があってもいいんじゃないかな? 問題意識やフラストレーションをじわじわ溜めた結果、いよいよ黒染めの頭巾を脱いで自分の言葉で自己表現やセルフケアとしての美容についてまとめたエッセイが『美容は自尊心の筋トレ』だ。帯には「モテようとも若返ろうとも、綺麗になろうとも書いていない」、「“反骨の美容ライター“が『みんな違ってみんな美しい』時代におくるメッセージ」とある。自虐をやめて自分を大切にすること、美の多様性やボディポジティブ、ルッキズムやエイジズムへの抵抗。刊行した2019年の時点では勇気が必要な“反骨”だったけれど、2023年には「当たり前のことしか書いてない」という感想を見かけた。たぶん褒められてはなかったけど、自分の書いた内容が当たり前になるくらい時代は変わったんだなと感慨深かった。
美容をめぐる言葉は、変わった。少なくとも建前上は。私は建前が変わることは大事だと考える派だ。例えば差別を止めるには、個人を説得して改心させるよりも、差別禁止法を作って「これは差別に当たる」「差別はいけない」という建前を先に構築した方が、早く広く守れるものが多い気がするから。「差別は禁止」という建前さえあれば、内心ではどんなに差別していても、面と向かってあからさまな差別はしなくなる。
「見た目の話」について脳科学の先生が「こういう話をするとルッキズムって言われちゃうかもしれないけど、だって本当のことだもん」と呟いていたことがある。確かに、科学的に人間は視覚情報に左右されやすく、見た目で判断するルッキズムの奴隷なのかもしれない。しかし「他人の見た目について、あれこれジャッジして本人に伝えるのはよろしくない」という建前が浸透すれば、容姿を貶められてその後何十年も傷つき屈託を抱える人が減り、みんなが見た目への不安に囚われずもっと伸び伸びできる日が来るのではないか。また、美容と資本主義の結びつきは絶望ワードのイメージが強いが、現代は大きい企業になるほどESG(環境・社会・企業統治への責任を考慮した企業活動)やSDGsへの取り組みが注視され企業価値に直結するようになり、予算とパワーとイノベーションを活かして、競うように社会を良い方向に変える取り組みに励む一面がある。例えば日本には、「色の白いは七難隠す」という言葉があるように、平安から続く白粉文化の影響で美白信仰が強い。「美白」=「白人信仰」とされがちだが、白人至上主義の伝来よりもずっと古いのだ。雑誌では毎年5月号にもなると美白特集を組んだりするのだが、「美白」への思いはそれぞれでも、ナショナルクライアントが「美白という言葉を使わないでください」と表明すれば、自然と「美白」を使わない方向に舵を切る。文化軽視や検閲のように感じる人もいるかもしれないが、何も歌舞伎や舞妓さんの白粉をやめようという話ではなく、小手先に思えても白肌こそは美しいという固着を緩める試行錯誤によって、多様な肌トーンを肯定する土壌を育む建前が築かれるのは素敵なことなんじゃないか。
建前の話をしたのは、社会課題としてのルッキズムはより巧妙で深刻になっているんじゃないかと危惧する面もあるからだ。思いつく具体例をつらつら挙げてみよう。まず、人を全体で受け止めずに顔を見る傾向がさらに進んで、意識がパーツにズームしすぎている気がする。「鼻翼」ってどこだかわかりますか? 「中顔面」、「人中」は? どれもメイクや美容医療で縮めるのが流行っているパーツ。あまりにも細部ばかりにフォーカスしてしまうなら、いっそミュートワードにした方が精神衛生に良さそう。美容医療市場の急成長とアルゴリズムによるサジェスト機能が組み合わさり、細分化されたパーツについて検索するとそれに関する情報や広告ばかり表示されるようになり、無意識のうちに歪んだ美意識の泡に取り込まれるリスクがある。ボディポジティブで検索すると「気持ち悪い」「開き直り」とサジェストされるが、日本は先進国ではいちばん痩せた女性の割合が多く、健康に深刻な影響を与える恐れがある。女性に多い摂食障害が低年齢化しているのに、対応できる医療機関が少ない。重篤な糖尿病患者のための薬がダイエット薬として出回り、思わぬ副作用に苦しむ人がいるうえに、糖尿病患者への供給が不足し、社会問題になったのも記憶に新しい。K-POPアイドルの体型に憧れてダイエットに励む若年層は多いが、韓国国会では練習生の人権保障が議題になり、元アイドルが「28歳なのに骨密度が80歳」と証言したり、「無月経が多い」という調査結果が発表されたばかりだ。「ハイリスク、ハイリターンなドバイでのパパ活」のルポで、ドバイ入りする理由でいちばん多いのがホストの売掛代金のため、次が美容整形資金のためだと読んだ。個人の決断についてはジャッジできないとしても、その背景にある社会の圧をスルーしてはいけないのではないか。山手線が美容外科の“「美しくなる」は、人間の権利だ。”という車内広告でジャックされていた。その「権利」とやらを行使するために払われた大金を元手にしたメッセージが、通勤通学途中の私たちを取り囲む。ちなみに、個人的にいちばん気になっているのはエイジズムで、今や理解者からすっかり当事者になったので言いたいことはいっぱいあるが、今回は割愛させてください。
美容はもちろん、最近だとフェムケア・フェムテックは、ジェンダー視点が必要なはずの分野なのに、わざとかと疑うほどその視点が抜け落ちていることがあり、業界の中や語る人にもっとフェミニストが必要だと切実に感じる。実際、女性向けのメディアでまさかの今どき「フェミニズムは炎上リスク」と語る意思決定権者がいたり、フェミニストに取材するときに「“フェミニズム”という単語を使わないことはできるか」と打診されることもあったりなかったり。一方で、美容ライターがフェミニストを自認するなんてルッキズムと資本主義の犬(犬は最高!)のくせにって批判を受けたり受けなかったり。疲れている時はちょっと気にしてこだわっちゃうこともあるけど、今後とも鼻歌交じりにけしからん上等でやっていきたい。
長田杏奈(おさだ・あんな)
1977年神奈川県生まれ。ライター。雑誌やWEBで美容やフェムケアにまつわる記事、インタビューを手がける。著書に『美容は自尊心の筋トレ』(Pヴァイン)、責任編集に『エトセトラ VOL.3 私の私による私のための身体』(エトセトラブックス)。podcast『長田杏奈のなんかなんかコスメ』、ニュースレター『なんかなんか通信』も定期的に配信中。

