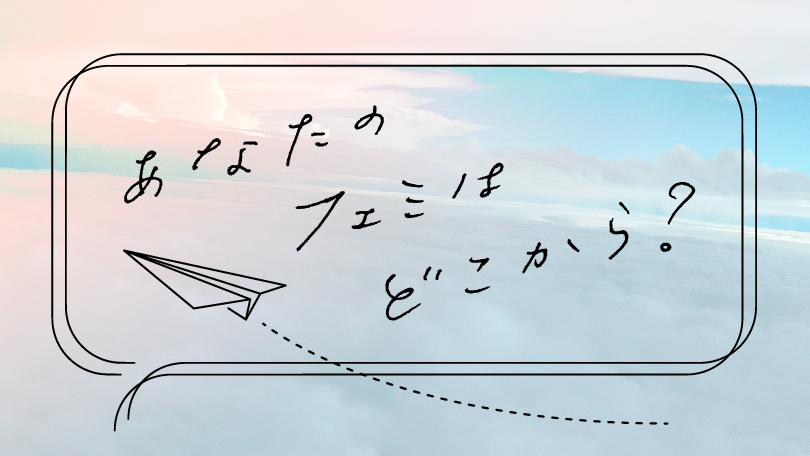
第13回
ぬるっと出会って、ずっと繋がって 森山至貴
[ 更新 ] 2024.10.01
「ゲイなのにほかのゲイといっしょにいることが苦しい、ほかのゲイがやっていることが僕にはできない」という苦しさでいっぱいいっぱいだった当時の私にとって、自分の生きづらさに対処するには、「自分以外にゲイが(あまり)いない、でもゲイに安全な場」が必要で、フェミニズムに関する授業はそんな私にとってまさにうってつけの場だった。研究者になりたいとも思っていた私は、そんな授業をいくつもそれなりに熱心に受講し、フェミニズムの思想を貪欲に吸収していったと思う。学生時代にはセジウィックの『クローゼットの認識論』やバトラーの『ジェンダー・トラブル』の読書会も定期的におこなっていたし、食うや食わずの専業非常勤講師時代には、フェミニズムを教える授業も任されることがあったから、その準備という意味でもよく勉強はしていた。
「勉強」という言葉に否定的なレッテルは貼らないでほしい。学ぶことはいつだって重要だし、当時の私はフェミニズムを血の通った思想として、自分なりの実感を伴うかたちできちんと受け取っていたと思う(今もそれは変わっていないという自負もある)。ただ、かつての実感は、ある種の「お隣さん」意識に基づくものであることは言っておかなければならない。「ゲイも大変だけど、女性も大変なのね」とか「ゲイが苦しんでいるようなことに女性も苦しんでいるのね」といった経験と想像力に基づく類推こそ、私がフェミニズムにアクセスする唯一の経路だった。
ここまでが前置きで、私が本当に語りたいのはその先のこと、つまり私がフェミニズムと出会い直す過程の話だ。といってもここから先の話にも残念ながら劇的なところは何もない。
専業非常勤講師になる少し前、つまり博士課程を満期退学する少し前に、父が倒れた。脳幹出血だった。一命はとりとめたものの、体を動かすことも声を発することもままならず、病院での寝たきりの生活がはじまった。
機嫌が悪いと無口になり、母にとてつもない我慢を強いてばかりいた父のことを私は嫌いだった(父が亡くなった今も父を好きになったわけでも許したわけでもない、念のため)。ただ、介護を母に、つまり女性に任せっきりにすることの罪深さは理解していたので、足繁く見舞いに行き、手足を拭くなどの簡単なケアには自分なりに熱心に励んだ。
見舞いに行く私は、いつも「森山さんの息子さん」だった。至貴という名前を持った存在でもなく、「森山さんの親族(あるいは子)」という漠然とした存在でもなく、性別(と子という属性)だけをあてがわれた半透明の存在。男役割に安住してなるものか、と必死に時間をやりくりしながら見舞いに行くたびに、むしろ「お前は男なのだ、男であるということ以上の個別性を周囲に把握してもらおうとしてはならないのだ」と突きつけられる経験は、老い衰えゆく父のそばにいることのしんどさと相まって、私をすっかり打ちのめした。気が遠くなるほどの長い介護期間を経て、父の葬儀で「故人のご長男」として振る舞うことを繰り返し求められるところまで、この息苦しさは続いた。
今から思い返してみると、社会の求める「普通」の生き方から全力で逃げ続けることで自由気ままに生きていたつもりだった私が、社会の中に「男」という鎖でどうしようもなく繋ぎ止められていることをはじめて真剣に意識したのがこの時期だったのだと思う。今までさんざん「ゲイなんてろくな男ではない」と私に吹きこんで罪悪感を植え付けようとしてきた社会が、手のひらを返したかのように「いや、お前は男ですから、それ以外の何者でもないですから」と私を鎖で繋ぎ止め、都合よく飼い慣らそうとする。ふざけんな、と思う。
それから私は、「私自身が自覚し実感している以上に、周囲の人は私を男だと意識していて、そのことによって何らかの鋳型に私をはめているのではないか」と注意深く観察するようになった。いくつものエピソードが今でも思い出せる。たとえば今の職場ではこんなことがあった。私が厄介な仕事をしなければならないと知った同僚の教員が私に同情してこんな風に声をかけた。「『なんで俺がこんなことやんなきゃいけないんだ』って感じですよね!」ああ、この人は私のことを「自称が『俺』」であるような男性だと思っているんだ。私の自称は若い頃は「僕」で今はほとんど「私」、なんなら小中学生の頃には「うち」などと自分のことを呼んでいた時期もあるくらいで、自称で「俺」を使うことがどうしてもできない。それは私には「男」過ぎる自称なのだ。「自称が『俺』」と思われることは私にとってはかなり屈辱的なことでもあって(私はそんなに臆面もなく男なわけじゃない!)、その日はちょっと落ち込んだ。
けれども、これらの経験は反転するかのように私に反省を促した。つまり、「私自身の自覚以上に、私は周囲の女性を女性だと意識していて、そのことによって彼女らを何らかの鋳型にはめているのではないか」と真剣に意識するようにもなったのである(この反転を可能にしてくれたのは、私の中にあったフェミニズムの知識だったのだと確信している)。そう考え始めると、私が「男扱い」される経験だけでなく、私が女性を「女扱い」した経験が苦々しくいくつも思い出される。とりわけ大学院生時代の私は、自分が少しばかり賢いと思っていたので、マンスプレイニングのそこそこの常習犯だった気もするのである。そして、今はそんな状態を脱することができているのかと問われても、胸を張って「はい」と答えられる自信は、正直なところ、ない。
「加害者性への気づき」といった単純な言葉でこの反転を片付けないでほしい。いや、自らの加害者性に気づくという経験はたしかに私にもあるのだが、単純に反転だけしたわけではないのだ。私は今でもゲイとしての自分は差別されていると思っているし、ある面においては、男らしくあれと要求される私は、性規範の充満するこの社会において、女性とともに同じ構造の被害者である、と言いたい気分もある。性別にまつわる不条理や問題の構図をどう捉えるのか、その構図の中での自分の立ち位置はどこなのか、その答えを一通りに収斂させることができない自分がそこにいる。そのことにこそ私は気づいたのだ。
そんな迷いの中でフェミニズムの著作を(まさに「勉強」として)読んでいると、記述の細部が鮮烈な実感を伴って理解できる経験がずっと増えていることに気づいた。私の逡巡も煮えきらなさも、フェミニズムの著作の中にすでに書いてあるではないか。今までのわたしは何を読んでいたのか。「お隣さん」気分を私に感じさせる、それゆえ私にとって救いとなる一文がそこにはある。でもそれだけじゃない。加害者としての私に問いを突きつける一文もそこにはある。私たちが苦労させられているこの構造を、ともに打破しようと呼びかけてくれる一文もそこにはある。それらはときに渾然一体となっていたり、互いにぶつかってきしんだりしながら、いつもそこにある。
私がみずからの体験から類推できるところだけを拾って吸収していたとき、私にとってフェミニズムはある意味で単純に理解できるものだった。むしろ今のほうが、フェミニズムは私にとって茫漠としたものにも思える。そして、茫漠としたものにも思えるフェミニズムは、それゆえに私にとってますます切実なものになっている。きっとこれからも、私はフェミニズムの渦の中に時折、いやしばしば飛び込んではもがくことを繰り返しつつ、自分の生を生きていくことになるのだろう。かつてはひとつしかなかった私のフェミニズムへのアクセス経路は、今では何種類にも増えている。そして、今後も(私がその努力を怠らなければ)増えていくのだろう。それは本当に幸福なことだと、私は思う。
だからこの話に劇的なところは何もない。ぬるっとフェミニズムに出会った私が、人生の途中でフェミニズムと少しずつ出会い直していって、これからもずっとフェミニズムと繋がっていたいと思うだけの話である。ただ、そう思うだけでちょっと元気が出てくることは、付け加えておいてもよいかもしれない。だから今の私は、まあまあ、いやけっこう、元気です。
森山至貴 (もりやま・のりたか)
1982年神奈川県生まれ。早稲田大学文学学術院教授。専門は社会学、クィア・スタディーズ。著書に『「ゲイコミュニティ」の社会学』(勁草書房)、『LGBTを読みとく――クィア・スタディーズ入門』(ちくま新書)、『10代から知っておきたい あなたを閉じこめる「ずるい言葉」』『10代から知っておきたい 女性を閉じこめる「ずるい言葉」』(WAVE出版)、『慣れろ、おちょくれ、踏み外せ――性と身体をめぐるクィアな対話』(能町みね子との共著、朝日出版社)などがある。

