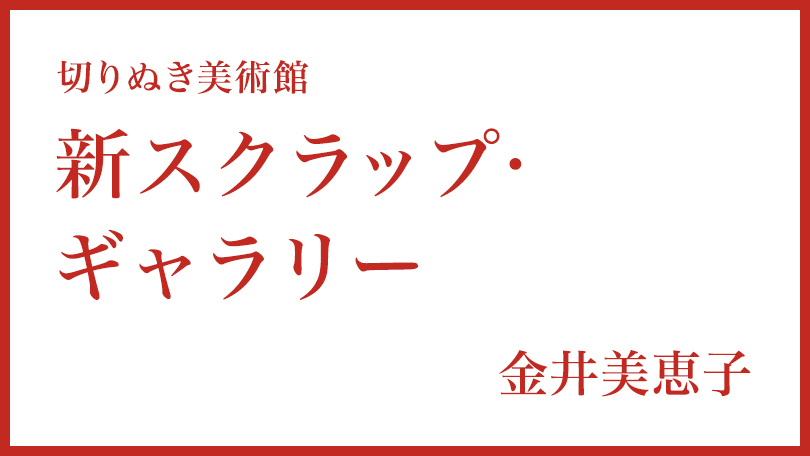
第11回
入浴図
[ 更新 ] 2017.02.17
あたたかいお湯の充たされた浴槽に身体を沈めて、あふれ出して流れるお湯の音を聞きながら、深いため息を吐いて眼をつぶると、たぷたぷと微かに表面が波打つお湯と、皮膚によって外界から隔てられている身体の内部の境目が曖昧な気がしてくる。
浴槽が大きければ大きいほど身体の感じるお湯の圧力も大きくなるから、私たちはあたたかな液体の中に浮かびつつ、あたたかなお湯の波に柔らかく皮膚を打たれ、液体の中に溶け出してその一部になってしまいそうな浮遊感に包まれる。
十六世紀のフォンテンブロー派の、湯浴みするバストショットの構図で描かれた二人の貴婦人がお互いの乳首を指で抓みあっている不思議に官能的な絵はいわゆる「ヌード」と言うよりも、お湯に浸った半身のあたたかさと汗ばむ乳首の擽(くすぐ)ったさが〈お風呂〉に入ることの気持良さという官能性を伝えている絵のような気がする。
ルノワールが好んで描いた〈浴女〉たちも、バラ色に染まった白い豊満な体を性的な快楽というよりも、着物を脱いで裸になった体が味わう解放感や、心地良く気持の良い快適なお湯や水との親和性の官能に軽く溜息をつきながら浸っているように見える。
しかし画家は、お湯の中(風呂桶、湯船、浴槽、バスタブと、そのお湯をたたえる容器を何と呼ぶにせよ)で身体の輪郭が溶けてしまいそうなうっとりとする汎性欲的官能を視覚化しなければならないので、自分がお風呂に入っている時の、あの柔らかくもやもやした霧状のあたたかい湯気や、タイル張りの浴室に差し込む明るい日のひかりや、薄い緑色の入浴剤の入ったお湯ごしに光が屈折して歪んで見える手脚といったものを描くのは、唯の、と言うかいわゆる裸体画を描くためではなく、お風呂の官能的で豊かな感触なのだ、とこの二人の日本画家の描いた絵は語っている。
高山辰雄が戦時下の1940年代に描いた一連の小さな子供たちと母親の入浴図と、それより少し前に小倉遊亀の描いた二枚の『浴女』を見ていると、入浴にまつわる様々な感触(お湯に浸されている身体感覚だけではなく、風呂場の音や空気を含めて)が呼びおこされるのである。小倉遊亀の『浴女 その一』(1938年)に描かれているのは裕福な家庭の家族用の風呂場なのかもしれないが、それより高級温泉旅館の家族風呂と思われる、タイル張りの大きな浴槽と壁面で、小石を埋め込んで濡れた足がすべらないように作られている微かな凹凸(おうとつ)のある床の洗い場のある広々とした清潔な空間で、この絵と対になっている『浴女 その二』(1939年)は、市松をななめに編んだ柄の花茣蓙(ござ)を敷いた床と漆塗りのついたて式衣桁(いこう)と、左側壁面には大きな鏡が張め込まれている脱衣所に、湯あがりの身づくろいをしている三人の女性が描かれている。
小倉遊亀「浴女 その二」1938(昭和13)年
小倉遊亀の浴女たちは、女同士一緒にお風呂に入るという親密なのびやかさが繊細に描かれていて、贅沢で豊かな浴室でゆったりとくつろぐ女たちの浴衣の柄は当然のこと、腰紐や手拭い、ブラシやクシ、後姿の女の持つキセルといった選び抜かれた小物の描き方が、画面の奥行を深めていて、女たちの決して騒々しくない会話が聞こえて来そうだ。『浴女 その一』の大きな白いタイルが張られた浴室の淡い緑色のお湯は、二人の若いほっそりした裸体の女たちの身体の動きのせいで微かに揺れ動いて波打ったせいと、画面には描かれていない窓から差し込む光のせいで、浴槽の内側のタイルの格子状の線を歪ませて見せ、軽く波打つお湯の揺れ女たちの肌をお湯の重さと一緒に圧迫し、ここでも女たち(母子か姉妹か、あるいは若い叔母と姪)は決して騒々しくならない声で短い会話をかわしているようだ。
小倉の『浴女』の豊かな浴室空間を見ていると思い出されるのが谷崎潤一郎の『蓼喰ふ蟲』である。
『陰翳礼讃』の空間論が小説化されたような描写のあるこの小説の中の、語り手の家のモダンなタイル張りの浴室と、語り手の妻の父親がことさら古風に日本風に妻と一緒に暮している家の「湯殿がおそろしく陰気な建て方」の「高いところに無双窓(むそうまど)があるだけだから晝間でも厭にうすぐらい」「長州風呂」が比べられる小説の最後の方(と言っても、これは未完の作品だが)の部分である。
谷崎の文章から、日本の昭和初期の家庭の風呂場事情がある程度わかるので、もう少し引用することにしよう(PC画面上で横組み旧仮名を読むのは妙なものではあるけれど)。
「上方に普通な長州風呂と云ふ奴で、一人の体が満足には漬からないくらゐ小さな釜の、周りの鉄の焼けて来るのが東京風のゆつくりとした木製の湯槽に馴れた者には肌ざはりが気味悪く、なんだか「風呂へ這入った」と云ふ心持がしない」し、この古めかしい湯殿は語り手にとって「自分の家でタイル張りの浴室にばかり這入りつけてゐるせゐか穴蔵へでも入れられたよう」なのだ。妻の父親と暮している古風な日本的女であるお久さえ、語り手に、「肩流しておくれやすんやけど、あんまり暗おすので、前とうしろと間違へたりおしやしてなあ」と、「不便をかこつ」くらいだ。このエピソードは、お久という古風な上方女のほっそりした体つきを語っているとは言えるが、前と後の区別がつかないほどほとんどふくらみのない乳房を、谷崎は落語のようにナンセンスな笑いとして書いているわけではないのである。
それはそれとして、谷崎の書いている長州風呂というのは、五右衛門風呂とも呼ばれる風呂で、鉄製の桶の底を直火で焚くもので、風呂用の木の桶が普及する以前によく使用されていたらしい。小倉の『浴女 その一』のタイル張りの浴槽と『蓼喰ふ蟲』の語り手の家の浴室の広さは家族構成から言っても同規模とは思えないが、裕福な家庭ではタイル張りの明るい窓のある風呂が使われていたわけである。
1932年、現在の北朝鮮の永興で、ストーブを売る商店に生れた後藤明生は、小学校四、五年生の時、同じ町の税務署長官舎に住む女子の同級生の家で風呂に入った経験を書いている。「風呂場にも太陽はさし込んでいた。ぴかぴかしたタイル貼りの風呂が珍しかった。また羨しかった。わたしの家の風呂は五右衛門風呂だった。丸い木の板を足で沈めて入るやつだ。風呂場は昼間でも薄暗かった。/「木枯しや合間々々に猫の声」/そういって父は、薄暗い五右衛門風呂の中で、ニャーオと猫の鳴き真似をした。」(連作集『夢かたり』の中の「片恋」)
お久といい、後藤明生の父親といい、五右衛門風呂に入ると、人は、なにかちょっとおかしなことを言ってみたくなるらしいし、私としては次の二つを思い出すのである。「膝栗毛」の弥次さんだったか喜多さんだったかが、下駄をはいて五右衛門風呂に入って底を踏みぬいて失敗する挿話と、手もとに本が見つからないのだが、ペリーの来航で日本に来たオランダ人通詞の日本日記で読んだ、街道に面したところで五右衛門風呂に入っている小さな二人の裸の子供を見て、通詞が、咄嗟に、子供が大鍋で煮られている! と思ったという、非常に野蛮な西洋的東洋観が素直に語られているエピソードである。
さて、高山辰雄の『夕べ』(1942年)には、木製の湯槽に、まだ薄明るい光の残っている夕方、もちろん夕食の前にお風呂に入っている幼い姉妹が淡い灰色とベージュの色調で描かれている。
幼い女の子たちが入っているのは、谷崎が書いていた「東京風のゆつくりとした木製の湯槽」で、高山は同じ時期に何点かの幼い少女たちがお風呂に入ったり、若い母親が幼い少女と湯気の立つお湯の入った盥(たらい)で行水をしている絵のシリーズを描いている。風呂の湯から立ちのぼる、白いもやもやした湯気の描写は、後の高山調とでも言うべき輪郭の曖昧な画風の、たとえば祖母と若い母親とその幼い子供を描いた家族像のシリーズにあえて宗教的ムードの「聖家族」と名づけた絵にも、ある意味でつながってはいるのだろうが、私は、1930年代後半から40年代にかけての入浴図を含めた少女像の方が断然好きである。
たて長の画面に半円形に描かれたサワラ材の風呂桶に入っているのが幼いお河童頭の二人の少女なので、風呂桶が「ゆつくり」としていることが際立つし、谷崎の使用したこの言葉がまさしくたっぷりとあたたかなお湯に浸かる心地良さを示していることが実感されもするのだが、幼い子供特有の柔らかなにこ毛と呼びたいような湿った髪の毛の前髪を金属製の小さなビンどめでとめた女の子が立ち上って桶の縁に手をかけている様子、画面の手前の女の子が片腕をお湯の外に出している様子を見ると、小さな少女たちがお湯に浸っているのにあきて、少しのぼせ気味で出たがっていることが想像される。一から百まで数える時間、お湯に浸っていなければいけないのだが、とっくに、百は数えてしまった気がするし子供の体はすぐにあたたまって体温が高くなるし、なにしろ、もうお風呂に入っているのはあきてしまったのだ。絵のモデルになっているのにもあきたのだろう。
次回は小倉遊亀と高山辰雄の描いた少女たちと女たちを見ることにしよう。

