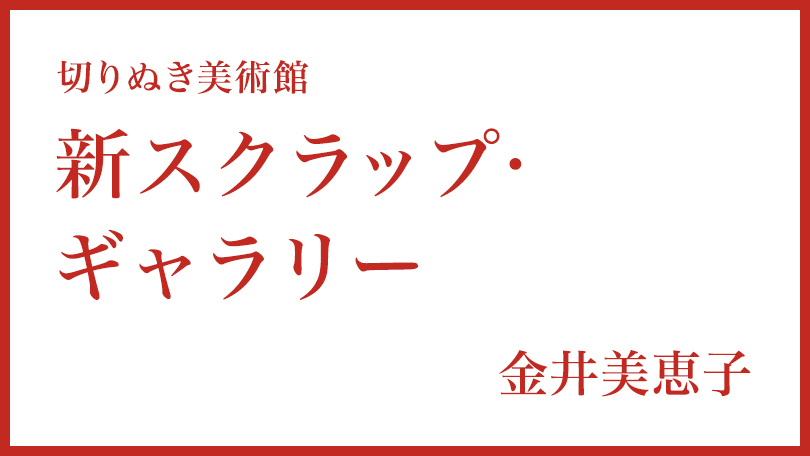
第7回
文芸雑誌「海」の表紙②
[ 更新 ] 2016.08.04
雑誌「海」(1970年6月号)表紙作品・加納光於 表紙構成・田中一光
原作の小説よりスタンリー・キューブリックによる映画化作品の方が有名な『時計じかけのオレンジ』('71)の原作者、アントニー・バージェスの英米文学史(『バージェスの文学史』'79)はそれが書かれた現在の、いわば20世紀の同時代の文学者たちから書きはじめられ、時代を遡行して古英語の時代にたどりつく。
「史」と呼ばれるものは、ほとんど全てが古いオリジンから語られ、時代の順序どおりに出来事や事物が示されて、現在にいたるのだが、バージェスの文学史は、その逆なのである。考えてみれば、というか、思い出してみれば、私たちが若い読者や観客として、小説や詩や絵画に触れるのは、学校教育的な正統的歴史性にもとづくものではなく、その時代の「現在」に「流行」しているものではなかっただろうか。それは、芸術史や文学史上のモダンという概念よりも、マスコミ(メディアというより、マスコミュニケーションというべきだろう)上の今日性によって、若い読者や観客や消費者であった私たちは、様々な新しい(あるいは、新しいというだけではなく、その時代に、再発見された過去の)作品に出あい、そこから時代を遡行して、過去の歴史を様々なやり方で学ぶことになるのだが、1960年代半ば高校生だった私が遭遇してしまったのは、現代詩と、ネオ・ダダと呼ばれていたアメリカのモダン・アートの旗手、ジャスパー・ジョーンズとロバート・ロウシェンバーグをはじめとして、日本のネオ・ダダ、あるいは反芸術と呼ばれたアーチストたち、ハイレッド・センターの路上ハプニング(現在では、パフォーマンスと呼ばれる)、アンダーグラウンドの芝居や舞踏、小説であればアンチ・ロマン、ヌーヴォー・ロマンというものだったし、映画についてならば、60年代はじめのまだ小学生だった頃、ヌーヴェル・ヴァーグの映画に遭遇してしまったのだ。ヌーヴェル・ヴァーグ映画のあの大人びた表情の主演男優は、私よりたった三つ年齢が上の少年だったのだ! 日本映画の子役、設楽幸嗣や小畑やすしとの何たる違い! 新鮮な驚き!
雑誌「海」(1970年5月号)表紙作品・加納光於 表紙構成・田中一光
そうした時代であったにもかかわらず、純文学系文芸雑誌はいかにも保守的な、近代文学的価値感(戦後民主主義と混りあった)と、権威主義が混在したような、先に例をあげた、現在の文学・芸術上の動向とは無縁という印象が強かったから、後に富岡多惠子(現代詩の書き手から、小説、評論の書き手へと変化したのだが、彼女が最初に小説を発表したのも「海」誌上だった記憶がある)は、当時の文芸雑誌について、自分を含めて誰も読まなかったし、自分たちの興味や関心のある読みたいものも書きたいものも別のところにあった、という意味のことを発言していたが、まったく、その通りだった。
とは言え、文芸雑誌的な権威主義的価値感は、当然、先進性のある新しいものをとりあえず無視しつつ、様子を見て、時代の流行や風潮に、少し遅れて、鷹揚に追従しながら生きのびてきたものなのだから、何年も後に、すでに、前衛的だったり、アングラでも反芸術でもなくなって、少し変り種の小説を書く、感性のいい新人作家として、唐十郎や赤瀬川原平を正式に認知し、すり寄るように芥川賞を与えるわけで、ましてや、版画家の池田満寿夫の芥川賞受賞小説などは、保守的と言ってもいい伝統的な純文学だった。
「海」の創刊号から一年後の表紙が加納光於の版画が採用されたことは、新鮮な驚きと言っても、決して大仰ではなく、当時の時代的背景を考えてみると、文芸雑誌の表紙に版画を使うのなら、モーリス・ブランショの『文学空間』や大岡信の第一評論集の装丁が印象的だった、文学的でもある豊かな感性が知られていた駒井哲郎と考えるのが、いわば常識的な文化意識というものではなかっただろうかという気がするのだ。戦後派的な硬質なイメージが、一種重い思念の痕跡を線描する駒井のエッチングに比べると、加納光於の版画は、鮮やかで明快な色彩とコラージュの技法を大胆に使用した金属的な物質感や鋭角的抒情性と詩的なリアルさが特徴だった。
3年目(1971年)には中西夏之のオブジェのシリーズが採用されるのだが、一年間十二冊分の表紙を改めて見ると、その頃、毎月の表紙として見ていた印象と、1973年、銀座の南画廊の個展に出品された実物を含めてかなり違った印象を受けて、少し驚いている。姉に言わせれば、「こんなにマッチョだった?!」ということになるのだが、たしかに、そのとおりなのだ。
'73年の個展から、すでに半世紀近い時が過ぎ、改めて十二個のオブジェを見て思い出したのが、詩人の吉岡実が中西の「海」の表紙シリーズを「こわい」と言った言葉だった。吉岡実が所有している中西夏之のコンパクト・オブジェは、「沈む鋏」というタイトルで、透明なポリエステル製の「卵」の中に、中西の作品でおなじみの砂鉄を、奇妙にうごめく微生物のように生やしている磁気を帯びた両刃の開いた洋鋏と、赤い木綿の糸が水の中を繊細に舞うように沈んでいるというか閉じ込められた作品である。
雑誌「海」(1970年9月号)表紙作品・加納光於 表紙構成・田中一光
十二の表紙のオブジェ(1985年の中西夏之展――北九州市立美術館――のカタログの個展年譜を見ると、73年南画廊の個展に出品された、「海」表紙シリーズ作品は十一点である)は、砂鉄、ガラス器具の一部、――砂時計であろうか――、鎖、コンパス、機械部品らしい歯車、針金、赤いビニールのコードや緑の毛糸や紐、三角やハート型の金属片、棹ばかりの部品や分銅、石膏で形どりをした、ニワトリの猛々しい蹴爪のついた足や、切り取られたように見える人の手や足(皺や爪の周囲のささくれまでがうつしとられている)や靴や植物の葉といったものに、金属の黒味をおびた鉄色や、赤味のある銅色が塗られて、様々に組みあわされ、ハート型や正三角という安定と不安定な動きが並列する中西好みの形態の破片も登場している。
切断された金属の手や足の指や金属片や鎖を組みあわせたオブジェは、不吉な不穏さで見る者を不安にさせるし、どこか中世というかSFの未来の暗黒世界というか、戦場に残された残骸のようでもあり、詩人が端的に短い日常語で言ったように「こわい」のだ。
80年代から90年代はじめにかけて、「文藝」の表紙は、まだ、時代の先端的イメージだったコンピューター・グラフィックスを使用した戸田ツトムのデザインが採用され、そこではクローム・メッキをほどこされたように光る金属の管が手ぬぐいやリボンのように自由に曲げられたり結ばれていて、当時のCGとしては制作に時間がかかる作業だったとは言え、中西夏之の手間のかかる手順を必要としたオブジェのアナログ的物質感を、(文芸雑誌という同じカテゴリーに属する雑誌の表紙に印刷されているものであるだけ)、ある意味デジタル的世界が「現代美術?」とでもいった風に嘲笑しているかのような印象を受けたものだった。
そして、話しは前後するが、1970年と1971年の、加納、中西と続いた現代美術を田中一光が構成というかレイアウトした表紙(と言っても、表紙の上方左に「海」という誌名の文字、中央に刊行月を表わす数字、右には三行に分けた横組で中央公論社、文芸総合誌、1月号――6月、7月と9月は特大号――とあるだけの、いたってシンプルなデザイン)は、翌74年から休刊の86年までの十二年間(!)、ラピスラズリという高価な岩絵の具を多用した月とかラクダがいたのかもしれない、群青色オリエンタルな、おぼろ気な記憶の他に何の印象も残っていない、平山郁夫の絵(「文藝春秋」であれば、ハイヤーで特製風呂敷を持って、編集者がお伺いするタイプの)が続くことになるのだが、それをきっかけに田中一光のデザインも排除(?)されたようだ。しかし、雑誌の内容というか執筆者の顔ぶれは、ほとんど変らず「海」的な内容が続いている。
2006年、「中央公論社創業120周年記念企画」と称して、中公文庫編集部編による『文芸誌「海」精選短篇集』『文芸誌「海」子どもの宇宙』の二冊と、『精選対談集』(これはなぜか大岡玲編)が出版されたが、この三冊の文庫の編集は、あくまで編者の狭い見識を示しているだけのように私には思える。あるいは、全体像がわかりやすくなる第二弾を考えていたのかもしれないが、多分、売れ行きがよくなくて、中止されたのかもしれない。
たとえば、71年新年号は当時の他誌のように、金や銀の特色も使わず、特集は「ケレーニとギリシア神話」で、大家から新鋭の短篇小説がズラリと並んで文運隆盛を祈って新年をことほぐわけでもなく、評論も小説も含めて、執筆者の名をあげれば、倉橋由美子、レヴィ=ストロース、山田宏一、中井英夫、渋沢孝輔、清水徹、海老坂武、高橋睦郎、稲垣足穂、吉本隆明、石川淳、塚本邦雄、野坂昭如、武田泰淳、辻邦生、というライン・ナップである。7月特大号では、高橋和巳の追悼特集にページが多くとられ、4月号は「呪われた幻視者セリーヌ」の特集に加え、塚本邦雄、中井英夫、唐十郎、入沢康夫という文芸雑誌では決して見ることのない名が並び、2月号には本邦初訳のハンナ・アレントの「暴力論」が載り、8月号には、アラン・レネの「映像と言語――フイヤードからロブ=グリエまで」とマンディアルグの短篇「プラトン的立体」が、ごくあたりまえのように、特別なことをやっているという気負もなく、並んでいるという、自由さなのだ。
1971年(昭和46年)12月号には、広津和郎の娘、広津桃子一人が同年11月に亡くなった志賀直哉について書いているが、当時、最も保守的な印象の強かった文芸雑誌「新潮」12月号(11月号は創刊八百号記念特大号で川端、小林、大江等の名が並び、多数の執筆者が登場している)の「志賀直哉追悼」には、学習院の同窓で二つ年上の武者小路実篤はじめ13人の執筆者が追悼文を寄せていて、編集部は二号分続けて大変な労力を要しただろうことが、今さらだが偲れる、というものだが、「海」では、前記のように広津桃子一人である。「新潮」同年1月号は、前年の11月、市ヶ谷の自衛隊駐屯地で演説の後、切腹自殺した三島由紀夫が、その前日に編集者に渡したという「天人五衰――豊饒の海 最終巻」の最終回が掲載され、1月臨時増刊号も出ているのだが、「海」の71年1月号には(それ以後も)三島の追悼は載っていない。(つづく)

