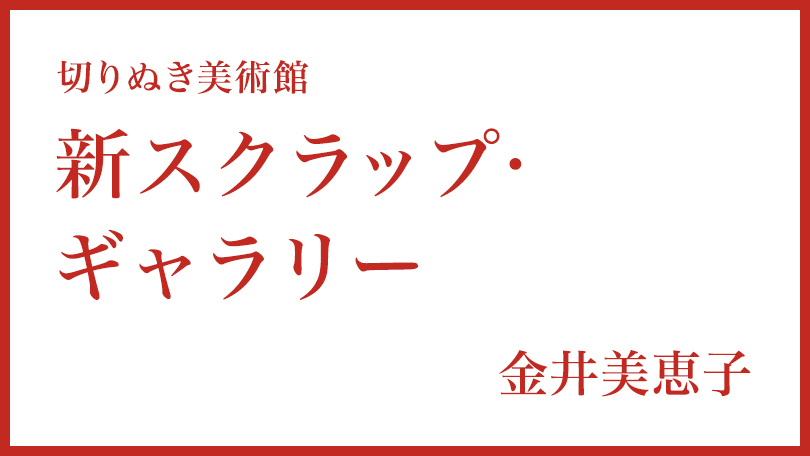
第22回
「机上芸術」と正座の人たち 清方と雪岱|1
[ 更新 ] 2021.05.17
「月刊太陽」(1977年1月号)表紙/鏑木清方画「築地明石町」(昭和2年)
文学史の年譜に目を通していると、それが歴史的な事実なのだから意外であるはずもないのに、あっ、と驚いて、どこからとも知れない溜息の出ることがある。
たとえば、1873年(明治六年)泉鏡花が生れた年(一年前の明治五年に樋口一葉が生れた)にランボーの『地獄の季節』が上梓されているのを目にした時である。なんと言うべきか。何かの――多分、時間とか時代の錯誤と違和感?
この頃、日本でどういう書物が出版されていたか、『新潮日本文学小辞典』の巻末年譜上の記述で目につくというか書名を知っているのは『学問のすゝめ』や成島柳北の『柳橋新誌』なのだが、むろんそれは言うまでもなく私の文学史的知識の狭い範疇を示しているわけである。
天保生れの特異な漢詩人、維新前は「二千石の騎兵頭」、文明開化後は新聞記者、随筆家となる柳北の名を知っているのも、中村光夫の短篇集『虚実』('70年)に収められている「パリ・明治五年――成島柳北の『日記』」を読んだからにすぎないのだが、柳北の滞欧日記は、たとえば山田風太郎の明治の開化物小説に、ミイラが展示されているルーブルで、柳北がフローベールとモーパッサンの二人連れとすれ違うというフィクションをとり入れさせるような魅力――いきいきとした好奇心が発揮されることの――があるのだろう。
鏡花の生れた年が、ランボーの『地獄の季節』を上梓したのと同じだという、感覚的に奇妙な時間の錯誤を覚えずにはいられない事実から、中村光夫の「パリ・明治五年――成島柳北の『日記』」(以下、「パリ・明治五年」と略)を、なぜ思い出したかと言えば、この短篇の印象深い最後の文章が記憶にあったからである。
『柳橋新誌』の書き手らしくパリでも遊興的な日々を送りつつ、西欧に「ひけ目」を感じる柳北は、サーカスを見物に出かけ、美少女の曲馬芸を見て、幼い時から歌人で、漢詩もはやくから学ぶ教育を受けている者として、ごくあたりまえのように「一詩がおのづから成」るのだが、その出来には不満で、念頭にもなかった情景と言葉が「詩」を作ろうとすると、「自然と顔をだす」ことに困惑する。幕府の儒臣の家に生れ、八歳の時には和歌集を著わしたという柳北にかぎらず近代化以前の日本語の歴史の厚みが、別の世界を表わさなければならない事態に直面したことで経験する困惑である。「余の心はただ空虚であり、なかを黒い悍馬に乗つた美少女が走りまはる状態を、無限に快く感じてゐただけだ。これを文字にする術が、西洋にはあるのだらうか。」と、「パリ・明治五年」は終わる。明治五年は西暦で1872年、その十五年前、安政四年にボードレールは『悪の華』を上梓している。
さて、今手もとに1976年12月発行の「太陽」('77年)新年特別号がある。特集は「鏑木清方――回想の明治」なのだが、この頃、鏑木清方の絵にも文章にも特別関心があったわけでもないし、雑誌の類いはほとんど保存しておかないので、なぜこの号が本棚の片隅に、いわば取り残されていたのか不思議な気がする。その行方が長いこと不明になっていた清方の名品「築地明石町」が、たしか二年程前だったか、所在が明らかになって話題になったが、私の家の限られた分量の本を収める書棚の清方の特集号の「太陽」は、つい二週間程前、書棚から何を探そうとしていたのかは忘れてしまったのだが、探し物の途中で不意に、その一センチ程の幅の背に印刷された「特集・鏑木清方」という文字として、飛び込んできた、とまでは言わないが目に入ったのだった。清方の幻惑的な美しい別世界について語る前に(そう、小村雪岱の展示を三井記念美術館という、日本橋にある資本主義=西欧の〈近代〉という価値観のデザインとして表わされた建物に見に行ったばかりでもある)、明治という時代の奇妙さについて、少しばかり触れておきたい。
清方の「築地明石町」の背景に描かれているという築地居留地のことなのだが、なにしろ私はこの絵が再発見されて公開された時にも見ていないし、清方の画集も持っていないので「太陽」の表紙の顔と襟もとの部分と本文中の「新富町」のノド側の隣に小さく「浜町河岸」と並んだポチ袋大の大きさのものしか手もとにないのである。昭和二年に描かれた「築地明石町」には、「外人居留地を背景に描かれた、近代美人画の代表作」と説明文があるが、庭の位置を示す木の柵とからまった朝顔と黄色い花は見えるものの表紙の顔の背景には霧に包まれているのか、ぼんやりと何かが見えるばかり......。
そこで思い出したのが、日本橋蛎殻町生れの谷崎潤一郎「幼年の記憶」(昭和二十二年)である。築地の居留地の大きな洋館に住むイギリス人サンマー家の四人の娘たちが夜学のような形で英語を教えていた「築地のサンマー」に鹿鳴館の時代より数年後の「所謂文明開化といはれた時代」で外国の居留地区は「そこへゆくと本當に外國へ行つたやうな感じだつた」明石町に明治十一年生れの谷崎は通っていたと書いている。「近所の家の垣根から、中に遊んでゐるイギリス人の子供に相手になつて、からかつたりもしたもの」で、イギリス人の子供たちの遊ぶ様子は、築地界隈で幼年時代を過した清方の「築地川」のシリーズにも描かれていて、「築地明石町」の印刷では見えない背景を想像することが出来るわけである。
鏑木清方画「築地川」(昭和16年)より「明石町」
ところで、「幼年の記憶」には、その頃「兎に角大變な御馳走であつた」テンプラが有名な銀座の「天きん」では「可なりおそくまで、小僧が全部チョンマゲを結つて」いて、それが一つの名物だったのだろうが、いつ頃までだったか「天きんの主人に聞いてみるとわかる」だろうと書いている。この小僧さんの結っていたチョンマゲというのは、谷崎全集第十三巻の「春琴抄」の春琴と佐助を描いた口絵(和田三造画)の佐助の髪型のようなものだったのだろう。『新版 日本史モノ事典』(平凡社)で調べると、「竹の節」と呼ばれた丁稚小僧の髪型だと思われるのだが、この事典には、女性の髪型は数多く載っているのだが女の子の髪型が載っていないので、私の世代が子供の頃「巡礼おつる」としておなじみだった(『傾城阿波の鳴門』)のさし絵で覚えている少女の髪型(少女の春琴の髪型と似ている)や、明治二十八年生れの小倉遊亀の「故郷の人達」(昭和四年)に描かれた小さな少女の頭のてっぺんに輪っかのマゲを結った髪型が、残念なことになんと呼ばれていたのかわからないのだが、「天きん」のチョンマゲについては、後に「銀座百点」誌上の座談会「明治の学生作家」(昭和三十七年、谷崎の他に久保田万太郎、戸板康二、池田弥三郎、車谷弘)の冒頭で、池田の生家であるテンプラ屋の「天金」(こちらの表記が正しい)のチョンマゲが話題になり、国文学者の池田弥三郎は「親父と叔父(劇作家の池田大伍)が小学生の時に結っていたそうで、自分たちが実際に見たのは銀座通りでブドウ餅を売っていたおじいさんが震災までチョンマゲだった」と語り、久保田は浅草公園であやめ団子を売っていたおじいさんについて話しているが、明治は遠くなりにけりの明治は、その頃江戸が含まれたうえでの地続きの空間であり風俗だったわけである。
ここで話しは横にそれるのだが、清方と雪岱の絵について書く前に、77年当時の「太陽」(新年号ということもあるにしても)の執筆者たちと、広告の豪華さについて触れておきたい。
金力と多少の文化度の高さをともなうステータスを表わす商品の広告(高級アルコール類、以下高級は省いて、時計、万年筆、カメラ、遠近両用レンズ、どちらもメーカーはニコン、宝飾品、家具、航空会社PAN AM――アメリカ西海岸へ。国際通勤できる、複々線――化粧品、和菓子、銀行、デパート、紳士服、そして、もちろん平凡社から出版されている国民百科事典全17巻、その他の書籍)の変遷についてである。
「太陽」だけではなく、グラビア・ページがあり、読者が中年以後の女や高収入の男にターゲットが絞られた雑誌の広告でその頃、目(いや、鼻か?)についたのが、凝った写真とレイアウトとしゃれたコピーの見開き二ページを使ったサントリー・オールドをオン・ザ・ロックで和食(今月の懐石シリーズ)にあわせるというシリーズだったが、この号は新年号とあって、「源平」と名づけられたエビ入りの大根なます。大仰な塗りの松に鶴、笹、それにアオイの紋のある螺鈿の器に入っている。器の背面には梅の螺鈿もあるのだろう。サントリー・オールドのグラスはバカラ(高級クリスタル製品の名をそれしか知らないので)、というところか。「紅白の材料を用いた料理を『源平』と呼びます」というコピーに続いて、「それは日本の旗の色。いさぎよい出発のしるし。平和な新しい年を願い、昔の男たちのロマンを語る酒席に、やはり最もふさわしい日の丸の色」というお目出度さに尾鰭を付けたコピーが書かれている。だいたい、エビと大根のなますにウイスキーのロックがあうだろうか? ウイスキーは食後にしな、と言いたい。
「月刊太陽」(1977年1月号)掲載の広告頁より
さて、しかし、それから四十四年が過ぎ、サントリーと言えば、現在では、ほとんどの人が思い浮かべるのは、ウイスキーではなく、「抽選で一万名様」に無料で一カ月分がプレゼントされる、グルコサミンのサプリメントだろう。
そのコピーにいわく。
長年ひざに悩んでいる妻。
最近はついに私にまで
ひざに違和感が...
すぐにでも
対策しないと。(傍点はもちろん引用者)
説明するまでもなく、自己中心的な、じじい中・後期の男の姿が目に浮かぶではないか。昔は、サントリー・オールドの広告を見て、妻に紅白なますを作らせ、このエビ、どこで買った? などと文句をつけていたのである。自分の「ひざ」の心配はするが、妻の「ひざ」はどうも二のつぎらしい口ぶりから推し量るならば。

