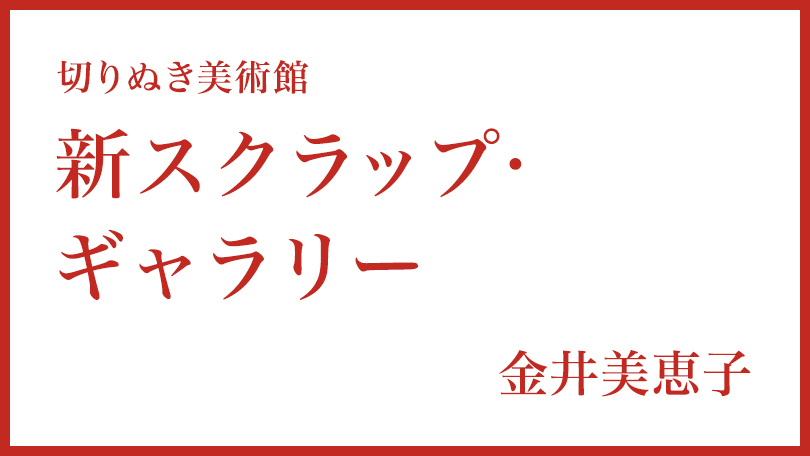
第20回
子供の領分と絵の空間 青柳喜兵衛と小林猶治郎|1
[ 更新 ] 2019.06.07
青柳喜兵衛『天翔ける神々』1937年 油彩・キャンバス
大きな赤い耳の、民芸品のオモチャ然とした虎(張子製なのか、それとも焼物か縫いぐるみなのかは不明)にまたがって、人形がくくりつけてある笹の枝だろうか、片手に持ち、バンザイをするように両の腕を伸ばしている子供は、男の子のようにも女の子のようにも見える。赤と青と黄色の山地を虎は人間の子供を背に子虎と一緒に駆けているようにも空(くう)を飛翔しているようにも見え、輝く雲の浮かぶ青空には富士山形の山の並ぶ山脈、吹き流しと四匹の鯉のぼりが薫風に吹かれて勢い良く泳いでいる。
友人からとどいた絵葉書きに印刷されたこの「天翔ける神々」(1937)は、二〇一八年、北九州市立美術館で「没後80年 青柳喜兵衛(きひょうえ)とその時代」という回顧展に出品されたものだったので、早速図録を取り寄せ、はじめてその輪郭に接したのだったが、鮮やかな原色と幼い子供の成長を象徴する鯉のぼりや親子の虎といった遊びと玩具の愛らしくにぎやかなモチーフが、もう一人の、画家の魅力的な絵を思い出させた。
「小林猶治郎展―超然孤独の風流遊戯」(二〇一三年、練馬区立美術館)ではじめて知った猶治郎(一八九七~一九九〇)と喜兵衛の絵に共通するのは、いわば《子供の領分》と呼びたい世界の遊びの要素を持つ、いかにも伸び伸びとした自由な作風の絵を描いていることだろう。
現在はすっかりすたれているのだが、時々、時代感覚のずれたスキャンダルが新聞に載ったりして驚かされることのある美術団体(私たちの小学生の頃には、東郷青児で有名だった二科会のジュニア公募展というものがあって、開高健の児童画教育界を素材にした『裸の王様』が'57年の芥川賞を受賞していることからも、美術団体や美術教育が当時の文化的話題であったことが推し量れるというものである)が、画家たちの活動と関係深かった大正から昭和初期にかけて、美術学校ではなく、慶応出身の喜兵衛も、七歳年上の早稲田出身の猶治郎も太平洋画会展、槐樹社展、光風会展といった共通の団体展に絵を出品していて、なかでも槐樹社という団体の影響が大きかったらしいことが二人の年譜からうかがえるし、両者の絵の伸びやかなタッチや大胆な原色を使った、遊びの要素のある玩具的な作品や、子供の描いた絵を自作の中にとり入れた愛らしい作品の試みにも二人の共通点がある。
回顧展図録の表紙にもなっている「天翔ける神々」は幼くして死んだ次男を追慕して描かれた「坊也童心」(赤い重厚な紋織りのテーブル掛のかかった卓の上にビーズの飾りが傘の部分についたランプが置かれ、壁には武者絵のタコ、幼い息子は藤椅子に座って、少し怒っているような表情で眼を見開いている)(註・一)と対になっているのだが、喜兵衛の絵には様々な日常的な物をテーブルの上いっぱいに置いた静物画と、豊かなたたずまいの緞通の敷かれた洋室の卓を中心に、一人のあるいは複数の女性を配した構図の作品が数多く描かれていることに注目すると、いわばそこには絵の中心と言えるものが失われているというか、拡散してあふれている印象がある。本来中心であるべき死んだ子供は、山地の凹凸や風をはらんだ布製の鯉のぼりや張子の虎と同じ強さで描かれて――紙製の虎の親子の顔の方がいきいきしているような――いるし、「坊也童心」は室内を飾る布地や凧(たこ)に描かれた絵やランプと少年は、ほぼ同等のものとして置かれているようではないか。
青柳喜兵衛『紙風船』1935年 油彩・キャンバス
もちろん画題が一つの物や人物にはっきりしぼられている小品もあるのだが、キャンバスが少しでも大きくなると、喜兵衛の絵は中心を消してしまおうとするかのように、幾つもの四角を重ねあわせたような構図の細長い布地のシナ服を着た女や、花の絵の描かれたシナの屏風、彫刻のほどこされた背もたれと座面が四角い椅子、丹色に桃の実の柄が織り出された緞通に埋めつくされ、「紙風船」('35)というタイトルの絵には、たしかにふくらませた物一つ、折りたたまれた状態の物の三つの紙風船が描かれてはいるが、黒い塗りに金色の装飾の描かれた卓上には、玉ネギやクワイやズイキといった野菜と、紙箱に入った緑色のアレクサンドリア、洋ナシ、草がいけられた白い陶器の花びん、カット・グラスのデキャンタとグラス、黄色のホーロー製のポット、裁ちバサミ、赤、緑、黄の色紙、白水玉模様に見える布帛と赤と白のテーブル・マット、猫よけの金網を被せた四角いガラスの金魚鉢とその中で泳ぐ赤い金魚、張子の虎といった、静物画に描かれる物としておなじみの物たちが、セザンヌ的な複数の視点の構図も取り入れて描かれている。
猶治郎の静物画も急須や茶碗やワラ編みの農具、縁の欠けたツボやらが物置の片すみのような雑然さで置かれた「静物雑居」('27)、蚤の市で買い集めた西洋骨董品のような壁の釘に引っかけてある懐中時計(壊れているのかもしれないが針は10時15分を指している)や、壁に打った二本の釘の上に載せて飾られているスプーンとフォーク、パイプ、手前には、化学実験道具が入っているのかもしれない木の箱、その上にランプ、小さな乳ばち、糸ノコ、肉たたき棒、六個の盃と二合入りの徳利、ひょうたんに似た変った形の急須、木靴が壁面とたな板の上に雑然とがらくた然と配置された「がらくた」('34)の、民具的力強さも印象的だが、練馬区立美術館の回顧展(二〇一三年)に展示された62年間にわたって描かれた多様な数多くの作品の中で、私が強く惹きつけられたのは、子供の遊びと密接な、子供たちの描いた絵から直接的な触発を受け、その自由な描き方で表わされた色彩と形の愛らしさと一体化したような作品群である。
小林猶治郎『がらくた』1934年 油彩・キャンバス
子供が自分の眼と頭と腕と指を使って、そこにある世界の一部を切りとり紙の上に絵に描くという行為の、いわば初々しく野蛮なところのある楽しさと興奮を画家(喜兵衛にも長女の描いた女の子の顔の絵が何枚も壁に張られた「千子の壁」('36)という作品がある)自身が再体験するように引用しながら描いたという、幾重にも重なった体験としての描く喜びが息づいているのだ。
「童心双六」('37)の九つの四角い枠を彩っている赤い線やボール紙にクレヨンや墨と油絵具の描かれた小さな絵「群像」('35)、「果物盡し」('35)の赤い手作りの額、そして、45センチ四方ほどの一九二四年に製作された三部作(「小鳥」「金魚」「戯具」のうち「戯具」は現在所在不明で、「金魚」のオリジナルは青みがかったガラス入りの額に入っていたが破損)にも、猶治郎的世界の子供の領分が感じられるだろう。「小鳥」の銅線の金網が張られた正方形の枠は動物園の鳥舎のように見え、画面中央の木の枝には幾つもの鳥の巣がかけられ、色とりどりの小鳥たちが止っている。キャンバスに正方形は珍しいから、キャンバスの枠も手作りで三枚の絵が並ぶ構成だったのだろうが、現在所在がわからない「戯具」は図録で見るかぎり、金色と黒のプレードの縁飾りのついた紫色の縞の赤いバラの花が刺繍されたクッション(ほぼ原寸大の45センチ四方の変型キャンバスに描かれている)の上に色鮮やかな玩具が置かれている。金魚は、様々な方向に泳いでいる金魚と水草が入った水槽の上部から水が差し込み、細い一筋の水が水面にハネをとばしながら注入されている様子が描かれ、破損する以前の完全な形では、水槽の一面に見える薄青いガラス越しに内部の水の世界を見ることになっていた。
三枚つづきの絵として完成時の姿を想像すると、関東大震災で焼け出された猶治郎が身を寄せていた神戸の未亡人の姉一家の子供たちの喚声が響き、輝く目が重なってくるようではないか。ぼくの叔父さんの夢と魔法のような絵と工作――。「ぼくの伯父さん」シリーズのジャック・タチの生家がパリの老舗の額縁製造店だったことを、なんとなく思い出してしまう。
小林猶治郎『童心双六』1937年 油彩・キャンバス
長男の小林敬の回想(「小林猶治郎の生涯」回顧展図録)によれば、「『戦争画』を描いて士気を鼓舞するようなことはなく一般庶民として隣組活動に参加し」ながら旺盛に絵を描きつづけていて、「統制下静物四題・米・砂糖・燐火・炭」の戦時下統制品になってしまった最小限の生活必需品が絵画として四品並ぶことで風刺的ニュアンスを持つことになっている四部作や、「國振ひゐな繪展」という展覧会には、あどけない顔のママー人形の看護婦と軍帽を被って白い寝間着を着た人形の傷病兵の組みあわせのひな人形を描いているが、戦前・戦中作られつづけて子供の世界を領していた様々な好戦的軍国玩具とはあきらかに別物であることがわかる。普通の日常的な子供の遊び相手の人形が、戦時下の病院でのいでたちをしているという奇妙な状況が描かれているのである。 (以下、次回につづく)
註・一 喜兵衛は川端生樹というペンネームで同人誌に'35年11月末に死んだ幼い息子への詩を何篇も書いている。
「雨あがりの 熱い 雲の 屋上の 物乾場の あちこちに 片隅に 雨に うたれ 投げすてられた おむつ 風に 吹きよせられ(中略)
灰色の 露に ぬれた 屋上の 物乾竿の 冷めたさに ぼんやりと昇る 朝日の 遠く 富士山は銀白に たそがれてゐる 武蔵野のはて」
と続く詩には、病院の屋上の物干場に「縦に 横に 斜に かけ 渡された」「黄色に 乾された おむつと じゅぼんと ねまきと しつぷの布と たおるの 大きな 影」がゆれている情景が書かれているが、寒々とした風に吹かれて振れる幼児を包んでいた布地の冷たい悲痛さ('29年には長男の喜一郎を二歳で亡くしている)とは対照的に、息子の背後風にはためく布地は鮮やかな色彩の鯉のぼりと吹き流しである。

