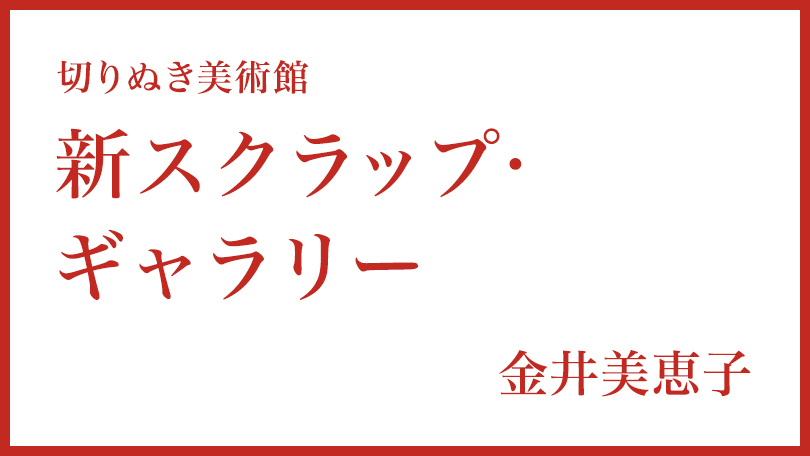
第23回
「机上芸術」と正座の人たち 清方と雪岱|2
[ 更新 ] 2021.09.13

「小説家と挿絵画家」(昭和26年) 絹本彩色 個人蔵
「築地明石町」を「見はらしの
鏡花が清方を健ちゃんと呼ぶのは、もちろん両者の作品世界の響きあいを通しての友愛の情があってこそなのだが、読者としては鏡花が使用するのが珍しい、エクスクラメーション、マークの楽し気な興奮の気配に、文章を読んだ清方がどれほど喜んだろうかと想像してしまう。それは昭和二六年に回想した場面が描かれた「小説家と挿絵画家」を思い出すせいにもよるだろう。
庭を背景に涼し気な夏の座敷でむかいあって座る小説家(鏡花)と挿絵画家(清方)は、清方の記憶では鏡花が『三枚続』の原稿を携えて口絵を依頼するために訪れた場面を描いたものなのだが、後になって当時の日記を見て、口絵の依頼が版元の春陽堂からだったと気づいたというエピソードを紹介しながら宮﨑徹(『鏑木清方――清く潔くうるはしく)は、清方にとって出会いを思い違いするほど二人の関係が「重要な画家の原点のように思えたのではなかろうか。」と書いている。しかし、これは単なるを思い違いというものではあるまい。
文学好きで、ことに樋口一葉や鏡花の小説を愛していた清方が、絵草子屋の美しい娘とオンドリの登場する『三枚続』の挿絵を注文されたことは、満を持して描くべく待ち望んでいた機会であったろう。今では考えられないことだが、小説家の直筆の原稿が渡され、それを読んだ画家が、単なる物語の
鏡花が書いた、原稿、などではなく、この場合こそまさしく「玲瓏たる玉稿」と呼ぶ以外にないものが木挽町の画室に運ばれてきたのだ。春陽堂の編集者が持って来たにしても、おろそかに受け取れるものではない。鏡花の小説の中であれば、若い挿絵画家は「小説家と挿絵画家」に描かれた日本座敷の画室を念入りに清らかに掃除し、もちろん涼し気な井戸のある庭も掃き清めて打ち水をし、夏用の青と白で織られた柄の緞通の敷物(昭和八年の作、涼し気な風が吹きとおり、その後に続く小倉遊亀の魅力的な夏の女客の姿を思い出さずにはいられない「夏の女客」にも、同じ緞通が描かれている)やこざっぱりと涼し気な団扇を用意して、小説家の魂の分身とも言うべき「玉稿」を受けとったのに違いないのだから、鏡花が『三枚続』を携えて画室を訪れたという記憶は、思い違いではなく、魂的に貴重な事実なのだ。
とは言え、淡い色調でデッサンのようなタッチの筆で描かれた絵の中の二人の様子を見ると、茶菓や煙草盆、団扇などが用意され、訪問者である小説家の背後には、被ってきた白いパナマ帽が置かれ、画家は両手で「三枚続」と題名が書かれて綴られた原稿を持ち、少し前のめりになって熱心に何か語っている様子で、絽の紋附の羽織であらたまった訪問であることが示されている小説家は思わず話しに引き込まれて画家を見つめ、膝元からとりあげた煙草入れときせるを手にしたまま、手に何も持っていなければ、共感のあまり思わず膝を打つ場面だ、という表情をしている。と言うことは、清方は春陽堂からとどけられた『三枚続』をすでに熟読していて、その読後感と、どのような口絵を描きたいと考えているかを説明をしているのだろう。明治三六年、件の『三枚続』の装丁、口絵の鏡花との初めての共同作業以来、ほぼ半世紀後の昭和二六年に「小説家と挿絵画家」は描かれているのだが、あたかもその日のうちに日記のように描かれたとでもいった描写性が、この絵の空間に、さわやかな霊気のように漂っている。
鏡花の側から清方の画室訪問を書いたのが冒頭に引用した「築地明石町」の帝国美術院賞受賞を祝う文章なのだが、清方が大正期に自らの作風について語った「卓上芸術」という概念――展覧会場の人ごみの中で、距離を置いて、場合によってはガラス越しに見ることになる大作ではなく、本の装丁や雑誌の口絵などの印刷物や江戸以来の木版版画の持つ、細やかに手に取って眺める絵を見る者との親密な関係の魅力――が、ここでは鏡花流に語られている。鏡花の見た下絵は図版(『鏑木清方――清く潔くうるはしく』所載)で見るかぎり、背景の外国船のマストなどがはっきりしていて、前回に引用した谷崎潤一郎の書いている明石町の感じ――鹿鳴館的な事大主義とは違う身近な、中学生がイギリス人の四人の娘が営む学校で英語を学ぶといったことを通しての、ロマンティックなあこがれの西洋である。ちなみに、鏡花も清方も今でいう最終学歴にあたるのは、英語学校であった――に近いだろう。ペンキ塗りの丈の低い柵と草花と木造の西洋館と、風を受けるマストと蒸気エンジンが共存していた商船を背景に、実在のモデルと言われる女性(清方の妻の同窓で、鏡花の紹介で清方に絵の手ほどきを受けていたという江木ませ子夫人。’77年の「太陽」1月号の清方特集では、当時、未亡人だったませ子夫人の双児の暁星の中学生のフランス語家庭教師のアルバイトを外国大の教授に紹介された高橋邦太郎――日仏交流史――の回想が載っている)は、存在するものの、後に取り組むことになる清方的リアリズムで描かれた肖像画とは異る夢幻的で甘美な淡く濃密な気配(心地良く鏡花の小説の世界が、絵画としてひろがっているような)が漂う。
清方の「卓上芸術」に深く共感する鏡花は、軸物の大作(後に描かれる「新富町」「浜町河岸」と三部作の軸物。173.5×74.0cm)の「築地明石町」の完成作を見ずに、「健ちゃん大出来!」を書いている。
「小さなりんの朝顔の、
鏡花はもちろん、展覧会(評判になって人が押すな押すな状態の)の混雑を好まなかっただろうから、展示された絵を人の肩ごしにアゴを載せるようにしたり、人によってはオペラグラス持参で離れた舞台のように絵を眺めたりする様を、群集のたてるほこりを物ともせず水際立って濁りのない絵の中の
ところで清方の絵の中の美女たちは、「清方三部作」と呼ばれる物をはじめとして、鏡花流の言葉でいうならば「水際立った女」と言うべきだろう。鏡花が考えるそうした女は、小説と芝居という

「女役者粂八」(昭和29年) 絹本彩色 鎌倉市鏑木清方記念美術館
茶と青の二本が霧か靄のように滲んで、壁面と床の区別がつかない背景の描き方によって、宙に浮いて座っているようにも見える女役者(絵のタイトルのように、中性的な印象の粂八は役者なのだ)は七三の割りあいの横わけの髪を何の飾りもなく無造作に後でまとめ、藍地に淡い青色で浮かびあがるコウモリの中形の柄の浴衣に
和服を着て畳の上で座る生活をしていた時代の芸人や小説家の肖像画なのだから、当然描かれた人物は正座をしている。写生によるのではなく、事物のリアリズムと記憶と想像力によって描かれた最初の肖像画「三遊亭円朝像」(昭和五年)は、清方の父親の経営する「やまと新聞」に創作咄を連載するため、しばしば鏑木家で高座をもった円朝の姿であり、「小説家と挿絵画家」は肖像画のような繊細、重厚な内面的描写とは違う軽やかな会話体のエッセイのようで、大正八年の全29図の絵日記「夏の生活」や、昭和二三年の記憶の甘美さが映画のような視線で描かれた一連の作品の系列に属しているのだが、そうした肖像画の中で女性が描かれているのは、おそらく樋口一葉と女役者の粂八の二人ではないだろうか。
幼い頃から芝居になじんでいた清方には、歌舞伎を題材にした絵も多く、小説の挿絵の発想も、物語が肉体によって演じられることによって進行する役者の動き方が、大きな動機の一つになっていたと思われるのだが、そうした体の動き方がここぞという瞬間に見せる、鏡花流に言えば「水際立った女」の姿――清方の「築地明石町」の絵の中の
「太陽」から清方を思い出し、何冊かの画集を手に入れて、たとえば「一葉女史の墓」(明治三五年)と昭和一五年に描かれた「一葉」との間に流れた時間と、役者の演じている舞台上の演技の形の美しさ(もちろん計算された手のこんだ独特の衣装を含めて)を描いた美人画と挿絵の物語性の混りあった世界(役者の衣装の描写などは、写実といってもよいだろう)と粂八の肖像との間に流れた時間が生み出した画面の持つ厳しさに眼を向けることにしよう。
その前に、ちょいと触れておきたいのが「鏑木清方と鰭崎英朋 近代文学を彩る口絵」展(太田記念美術館)に出品されていた鰭崎英朋の『

