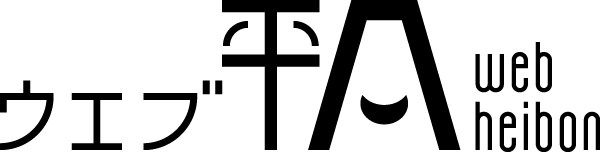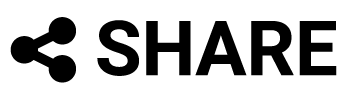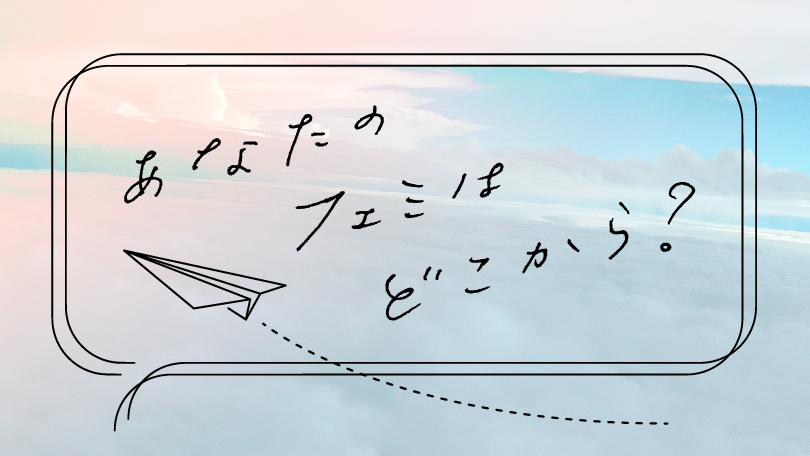
第16回
私のフェミはどこから。 上田久美子
[ 更新 ] 2025.01.10
一人で生きていくと決めてやってきたわけではないけれど、結婚しようという努力もしなかった結果そうなった。結婚や出産に対して社会の同調圧力を最も強く受けた世代の中にいる専業主婦の母親が、女の子でも経済力を持って自分の思うようにできたほうがいいし結婚はどっちでもいい、というようなことを子供の私に言っていたからかもしれない。今は、どこへ向かうかわからない人生を楽しんでいる。私は先が見通せる人生が苦手で、困難に立ち向かうことが好きな性 質 なのだ。高度経済成長期の恩恵があったことにより、この生き方を可能にする教育や資本を与えてもらえた幸運には感謝している。
私は新卒で東京のとある企業に就職したが2年ですっかり嫌になり、なかばやけくそで演劇の世界に身を投じた。
そこからのキャリアの中で、歳をとって上の立場になっていくと女性という属性が障害になることをひしひしと感じてきた。女性より優れていなければならないという強迫観念を刷り込まれた日本男性たちは、自分より立場や能力の高い女性に対して劣等感を持っている場合が多い。酒場のカウンターで隣の男性に話しかけられたとき、会話を続けたければ素性を言ってはいけないと緊張してしまう自分がいる。私は演出家でパリにアパート借りてます、と言えば、相手はたいていそれ以上話しかけてこなくなる。「お芸術」をやっており「おフランス」に住んでいるなんて、自分なんか見下されてしまうと思うのかもしれない。
経験不足の若い女性であることで男性社会の中では収まりがよくて、フェミニズムの問題に気づかなかった時期を過ぎた今、男性を人間の規格として成立してきたこの社会、特に企業文化に、女性にとってだけでなく男性にとっても重大な問題を私は感じていて、これから変えていかなければならないと、意識を新たにしていた矢先。
友人があるネット記事を転送してきた。「ソフトガール」が、男女平等化社会の最先端をいくスウェーデンで物議を醸しているという記事だった。「ソフトガール」というのは、TikTok発のトレンドで、女性がキャリアの追求よりもスローダウン、セルフケア、ウェルビーイングを重視する精神性を指し、スウェーデンでは「女性が仕事を辞めて、男性パートナーに経済的に依存するライフスタイル」として若年女性に広がっているそうだ。「専業彼女」あるいは「専業主婦」を目指す「ソフトガール」のファッションは、「優しそうに見える」ことが重要で、メイクも淡いピンクなどふわふわしたイメージが中心だ。これは私の母親世代に強いられた、従順でフェミニンで適齢期のうちに結婚市場で売れる女性像の演出を想起させ、私を心底ぞっとさせた。
スウェーデンでは、「ソフトガール」希望者の増加はフェミニズムの後退としてフェミニストたちから批判される一方、伝統的で女性らしい(女性らしさをそのように規定するのもどうかと思うが)生き方を選択する自由があるはず、という反論も多く、論争が起きているそうだ。当事者たちは、キャリア形成のためストレスを受ける祖母や母たちを見てあんなふうになりたくないと思ったのだという。
日本ではどうなのかと「専業主婦 希望者」とインターネット検索すると、真っ先にヒットするのは結婚相談所のサイトだった。その婚活サイトには「専業主婦希望者は多いが望みを叶えるのは難しい。ハイスペック男性を狙わなければいけないが、そういった男性には多くの女性が集まるので、若さや容姿などの高いスペックが求められる」とある。そして、専業主婦になるために「ハイスペ男性」をつかまえるための注意点などが事細かに書かれていた。
「欧米ではフェミニズム運動がすでに第四波を迎えているにもかかわらず、日本ではさざ波さえ起きていない」「No Wave」などと揶揄されるように、日本はフェミニズムに対してあまりにも意識の低い国だ。「日本版ソフトガール」は昔からずっと存在し続け、昨今の社会経済の沈降による労働への虚無感・忌避感ゆえか、専業主婦志望者がさらに増えているとしても、それがなんらかの変化として驚かれたり批判されることは少ない。今の日本の若い女性のファッションを見るとまさに判で押したような「ソフトガール」路線で、婚活サイトでお見合いのために指南されているのもそういうファッションだ。電車に乗れば、淡い茶色の髪をゆるく巻いてプルプルの唇をすぼめて突き出した女性の顔写真に「粘膜ピンク」というキャッチコピーのついたリップグロスの広告が堂々と掲示されている。これは露骨に、若く艶々のヴァギナを想起させる粘膜のピンク色を、露出したパーツである唇に移植して、オスたちに自身が生殖可能な若く健康なメスであることをアピールすることを推奨しているに違いない。
寄稿のためにこれらのことを考えているうちに、どうしようもなく疲労感が増し、気が滅入った。
私の周囲には、男女格差の煽りをうけた有能な女性がたくさんいる。私は京都大学の文学部を就職氷河期真っ只中の2004年に卒業した。親しいクラスメートの男性たちは一様に大手のマスコミに就職が決まっていったのに比べて、女性のクラスメートたちは就職活動が思うようにいかず、司法試験を受けたり医学部に入り直したりして手に職をつける人、非正規で働くようになった人、第一志望ではない企業に就職してすぐに転職し、その後も職を転々とする人などがいた。ごく少数、マスコミの広報など花形部門に内定した女友達がいたが、その人たちはずば抜けてモテる社交上手の美女で、早いうちに商社マンや広告マンと結婚して、退職して専業主婦になった。
つまり私は、他の男性クラスメートたちと同じ大手企業の土俵で仕事を続けた大学時代の女性クラスメートを一人も知らない。そもそもその土俵に立てたのも、男にモテる美女たちだけだった。
専業主婦になって幸せという人や、弁護士や医師になるために学び直す資本に恵まれた結果、生涯が保障された人々は別として、今も転職組として企業や公的機関で働く女友達は、一様に周囲からの仕事の評価も高く、もし男性だったら今よりいい条件で仕事につき、パートナーの男性との格差もないだろうと思われる。
私はこういう女友達に会うたびに、この社会に対する鬱憤を感じてきた。彼女たちは私と家庭環境も能力も似ていて、私自身のありうべき姿だからかもしれない。
そして、私のフェミはどこから来たか辿るなら、頭が良くていつも一生懸命で才能があった我が母が、専業主婦になり未だ幸せになっていないことについての、どこにぶつけていいかわからない不条理への悔しさからだろう。
そんなわけで、ソフトガール志望者たちに対して、あんたたちがそんなんだから女性の立場はこんなふうに最悪のままなんだ、他人に自身の生涯を託すなんて危険すぎる賭けだ、と苛立ちそうになるが、むこうにすれば、あんたみたいな「強者女性」から言われたくない、「名誉男性」から言われたくない、といったところだろう。
結局のところ、今の社会で、仕事の才覚があり、働くほうが男性に養われるよりベターな結果を得られる女性はそれを目指すだろうが、女性としての魅力という資本を活かしてハイスペ男性と結婚して働かない方が豊かに生きられるタイプの女性が「ソフトガール」を目指すのも止められない。誰だって、自分の資本を有利に使ってサバイバルする権利がある。
「ソフトガール」たちの男性への期待――自分たちはアッパーミドル層の男性を支えるので、男性は組織の中で出世して家庭に安泰をもたらしてくださいね――は、「強者女性」の求める男性中心主義社会の転覆と全く相反する。
だから、既存の男性中心主義を支え再生産する女性たちと、フェミニストな女性の間で分断が起きて連帯できないとはよく言われる話だが、そうならない変革があると私は思う。
「強者女性」が求めるように現行のシステムの中で女性の機会を均等にしても、そこでもストレスを多く受けるのは女性であり、スウェーデンではそれにNOを言いはじめたのだ。この問題は、労働における時間管理の制度も、言説のルールも、すべて男性の身体やコミュニケーションを規格として形作られてきたことに起因すると私は考えている。
「健全」とされた一部の男性の身体を規格として設定されてきた労働やコミュニケーションのありかたを見直していきたいというのが私の立場で、それができれば、競争に加わりたい女性だけでなく、すべての女性にとって、また男性にとっても、もっと生きやすい社会になるはずだ。現在進行中の「時間の起源と終焉(仮題)」というダンスパフォーマンスは、このテーマを探究するためのプロジェクトだ。
コロンブスがジェノバから出航し金融資本主義が幕を開けた時代に、人間が機械時計で時間を計測しはじめて以来、1秒は万人にとって客観的に同じ1秒になり、それまでは神のものだった時間は人間個人が所有できるものになり、それは貨幣と交換可能になり、転じて資本家たちは人々を時間で支配することができるようになった。この機械で測られた時間は、人類の何十万年の歴史の中でたった500年ほどしか存在せず(日本では明治以降なので200年も経っていない。明治時代に来日した西洋人は、日本人の時間へのルーズさにおかんむりだったという)、現代人が生まれ落ちた時からあることになっている1分や1秒は、人為的に策定された新しいルールなのである。日の長さの変化や、出産などによる身体の変化に伴い、あるいは子供の没入的な時間感覚に親が寄り添って、本来は伸び縮みする時間と共に生きてきた人間にとって、無情に冷徹に1分1秒が前に進み人々を従わせるルールの中で生きることが、心身にどのような作用を及ぼしているのか。
こんな疑問から、「時間の起源と終焉(仮題)」というパフォーマンス作品を計画しているが、本稿は、私のフェミはどこから、がお題なのでここで筆をおきたいと思う。
上田久美子
劇作家・演出家。奈良県出身。製薬会社勤務を経て、2006年宝塚歌劇団演出部に入団。脚本・演出を手掛けた「星逢一夜」で第23回読売演劇大賞、優秀演出家賞を受賞。ショー作品「BADDY―悪党は月からやって来る―」、日本物ミュージカル「桜嵐記」などの話題作を手掛け、2022年に退団。翌2023年に、人間界と植物界の二重構造を描いたスペクタクルリーディング「バイオーム」にて岸田國士戯曲賞にノミネート。2023年、「道化師」「田舎騎士道」で初めてオペラ演出。2023~2024年、新進芸術家海外研修制度でフランスに滞在。