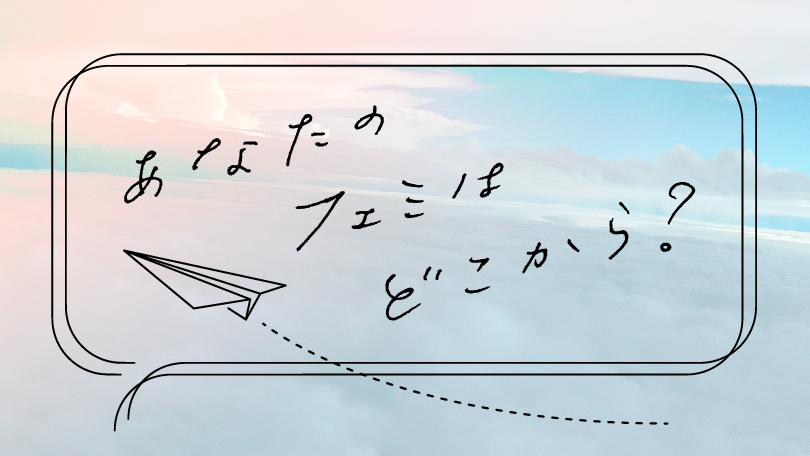
第6回
わたしが千なら、フェミニズムはハク。 長島有里枝
[ 更新 ] 2024.06.28
きっかけは幾つか思いつく。わたしを苛つかせ、戦慄させ、疑問でいっぱいにしたのは例えば、アートの企画で常に「フェミニズム担当」を担わされる違和感。あるいは、男ばかりの審査会や講評で、発言が「女性の」意見と受け取られること。期待に応えるつもりはないのに、「わたしがやらなきゃ」みたいな自負がどこからか現れ、結局は優等生っぽい(「女性ならでは」の)リアクションをしてる自分に呆れ、惨めな気持ちになる。フェミニストだからっていつも連帯できるわけじゃないけど、ネットで激しくやりあう人たちには心が折れる。いや、きっと議論や批判自体は大いに交わされるべきだ、でも、そんなふうじゃなくてもよくない? と思うことはある(オーディエンスがいるときは特に)。フェミニストの名言やフェミニズムそのものが、広告や人気集めやプロパガンダに使われている場面(しかも、解釈が間違っているか、正反対のことがほとんど)にぶち当たるたびうんざりし、どっぷり疲れる。
個人的に、戦争や差別や不平等の解決策として最も有効なのはフェミニズムだと思ってきた——そんなに期待すんなよぉ、と別のわたしがTシャツの裾を引っぱりながら忠告してくるにも拘わらず。そう、いつだって失望するのは過度な期待のせい。それに、わたしを苛つかせるのはフェミニズムそのものじゃなく、フェミニズムを利用する人たちだ。フェミニズムの力は、もっと違うことに使われて欲しい。フェミニズム理論の幾つかは、崇拝しすぎないよう気をつけなくてはならないほど美しい。それらは積もりに積もったわたしの小さな問題——自分がバカなだけかもとはぐらかし、きっとわたしが悪いんだと諦め、飲み込んできた——を見事に言い当て、違和感がわたしの勘違いじゃないことを論理的に、スマートに、知的な言葉で説明してくれた。フェミニストの本に書いてある言葉は、自信がなく、落ち込みやすく、クヨクヨしがちなわたしに前を向く力をくれた。ときどき、こんな素敵な考え方があるのに、どうしてムカつく出来事はなくならないのか考える。きっと、わたしが死んだあとも何百年、何千年、人類が存在し続ける限り、クソな事態はなくならないんだ。そう思って絶望する日もある。自分の望む結果がすぐに出ないからといってやさぐれるのは、ぜんぜんフェミニズム的じゃない。でも「世界、気に食わねぇ!」と思うことはあっていいし、それはわたしの性格や育ちが悪いから(まぁ、それもある)じゃないよと励ましてくれるのもフェミニズムだ。
上野千鶴子さんに、あなたは根っからのフェミニストね、という意味のことを対談で言われたことがある。褒めてもらったからじゃなく、こっそり自負していたことを言動から見てとってもらえたことが嬉しかった。それ以来、そもそも自分がフェミニストなのかどうか、そうだとしたらいつ、どのタイミングでフェミニストになったのかのような質問に答えづらいと感じるのは、自分がBORN TO BE A FEMINISTだからだと思うことにしている。保育園時代の記憶に遡ってさえ、わたしの考えかたはフェミニスト的だった。子どもに昼寝をさせるためには恫喝も厭わない担任の先生に対し、泣き止まないことで断固抗議した記憶(結局、体調を崩して保育園を辞め幼稚園に移った)、幼馴染みと同じように立っておしっこがしたくて練習した記憶。言うことを聞けとか、女の子だからとか、理由が納得できないことは簡単に受け入れたりしなかった。
そのうえ、3月生まれでもある。学校は子どもを「学年」という枠で区切る。3月生まれにとって、同じクラスの4月生まれとの成長の差は大きい。クラスいちのベイビーだったわたしはいつも、どこでも誰よりも鈍臭かった。身支度から徒競走まで、身体的行為を伴うすべてのことが人よりできない。大きい女の子の意地悪に言い返せず、ピンクレディごっこではいつも付き人役だ。掃除の時間になってもヤドカリみたいに、身体と一体化した椅子と机を引きずりながら給食を食べる。でも、その経験は、なにかが苦手な人や遅い人、力が弱い人、動物、その他の存在に理解を示し、寄り添おうとする性質を育んだと思う。
わたしは自分が「女」であることを、当時からよく理解していた。なぜなら、周りが逐一わたしをそう扱うのに気づいていたからだ。昼休みや放課後に男子と遊ぶと、自分だけ違うやり方で接されているのがわかる。彼らは優しいが、わたしを正式な仲間とは認めていない。それなら女子は仲間かというと違う。彼女たちは気まぐれにわたしをハブる、謎の存在なのだった。帰属できる集団がわからないまま、「女」になっていく自分に恐怖や気持ち悪さを覚えながら成長した。1980年代後半、わたしの生きていた小さな世界では、いまほど多様なジェンダー・アイデンティティは「存在しない」ことになっていたから、性自認が「女」じゃないなら「男」、だから性的対象は「女」というのが一般的な知識だった。男の子みたいな体つきでいたかったわたしはブラを拒んでダイエットをし、セックスは気持ち悪いと思いながら、子どもを2人産みたいと思っていた。18歳の終わりにはすっかり自分がわからなくなり、わたしにはなんの価値もないという考えから抜け出せなくなった。19歳でシモーヌ・ド・ボーヴォワールと臨床心理士に出会い、美術と向き合うことで絡まりまくった糸をちょっとずつ巻き取った。
いまでは多くの人が、フェミニズムは女性だけのものじゃないし、女性の問題だけを扱っているわけでもないと主張している。ベル・フックスは、論文では扱いづらい「愛」の重要性を訴えているし、ジョアン・C・トロントは経済活動の代わりにケアを中心に据えた、新しい民主主義を提案する。社会に出た1990年代、わたしは「失われた10年」のXジェネレーションと呼ばれた。いま、あの頃よりさらに多くの人が、さらに少ないお金と時間をなんとかやりくりして暮らしているように見える。じっとしていても世界中から届く大量の情報が、わたしの心と身体をフリーズさせる。わたしたちは簡単に奪われるし、大切なものを間違った名前で呼んで、自ら捨ててしまいもする。つまり、わたしが千なら、フェミニズムはハクだ。
自分を慈しみ、楽しみながら生きられる世界を目指して働こうと思えるのは、フェミニズムという学問や運動を発展させたフェミニストたちがいたからだ。人生を賭けて活動した彼女たちのおかげでいま、挫けそうになってもわたしは一人じゃない。
長島有里枝(ながしま・ゆりえ)
1973年東京都生まれ。1993年、現代美術の公募展での受賞を経てデビュー。2001年、写真集『PASTIME PARADISE』で第26回木村伊兵衛写真賞受賞。2010年、短編集『背中の記憶』で第23回三島由紀夫賞候補、第26回講談社エッセイ賞受賞。2020年、第36回写真の町東川賞国内作家賞受賞。2022年、『「僕ら」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ』で日本写真協会賞学芸賞受賞。日常の違和感を手がかりに、他者や自分との関係性を掘り下げる作品を制作しつづけている。著書に『Self-Portraits』『テント日記/「縫うこと、着ること、語ること。」日記』『こんな大人になりました』『去年の今日』など。

