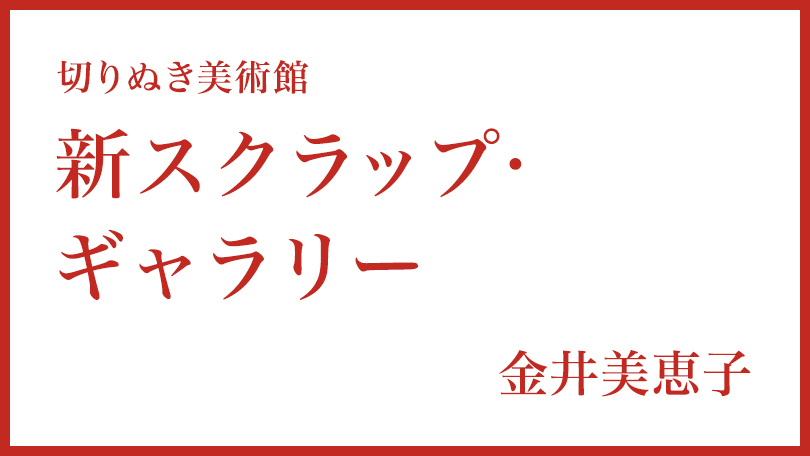
第10回
いわゆる「文芸雑誌」の表紙について ――石本正の場合――
[ 更新 ] 2016.12.07
石本正「舞妓」1968年
文芸出版社の社史で、今手もとにあるのは新潮社(『新潮社一〇〇年』平成17年)なのだが、そこで奇妙な程〝冷遇〟されているのは、本や雑誌のカヴァーや函や表紙を飾った画家たちである。はさみ込みのカラーページには、社にとって歴史的な出版物(単行本、雑誌)の写真が載っているものの装画家の名は記載されていない。「芸術新潮」を発行し、新潮芸術大賞という賞もあった出版社なのだが――。
文藝春秋の社史(『文藝春秋七十年史』平成3年)には、カラーページの「表紙にみるクロニクル」があり、「文藝春秋」「文學界」「オール讀物」「週刊文春」その他の雑誌の創刊号からの、表紙のデザイナー、画家、写真家の名も記されていて、変化と歴史がざっと見通せるようになっているし、手もとに資料はないが、講談社の社史でも、戦前から、高名な日本画家を使用した「講談社の絵本」が著名だし、野間美術館という施設もあるのだから、画家の名はきちんと記されているはずだと思う。
表紙は雑誌の「顔」と呼ばれもしたのだが(「タイム」の表紙を飾った時の人の「顔」を、戦後の人間は思い浮かべるかもしれない)、どのように「顔」としての画家が選ばれているのか、「文藝春秋」の「表紙にみるクロニクル」の名を列挙すると、雑誌名を中心にデッサンが使われていた大正時代から戦時下の昭和までが、恩地孝四郎、小杉放庵、川合玉堂、鏑木清方、梅原龍三郎、藤田嗣治、竹内栖鳳、川端龍子、戦後は、伊原宇三郎、小林古徑、安田靫彦、安井曾太郎、と戦前からの画壇の大家が並び、そして、昭和31年から61年までの超長期間を杉山寧、その後、高山辰雄に変って「現在(平成3年)に至る」のである。(註・1)
「文學界」は発行元が何度か変わり昭和11年に文春が発行元になるのだが(その間の経緯は中村光夫の『文学回想――憂しと見し世』にくわしい)、表紙は青山二郎ののびのびしたデザイン風装画で、戦後24年の復刊から、猪熊弦一郎、横山操、香月泰男、三岸節子、須田剋太、佐藤敬、脇田和、野見山暁治、等へと続くのだが、大きな特徴の一つはこうした名の知れた画家たちは、他の出版社の同じタイプの文芸雑誌や中間小説雑誌(判型は同じサイズである)の表紙画も描いているので、雑誌の中味の文章の方を受け持っていたのが〈文壇〉で、表紙の絵および目次カット(中間小説誌の場合は本文のさし絵も)を受け持っているのが〈画壇〉と呼ばれていたと誤解しても、一向にかまわないのではないかという気がするのである。もちろん、その頂点は両者とも芸術院会員、文化勲章である。
「海」が三島由紀夫特集を組まなかったことは、むろんある意志の表明として評価すべきことだと思うのだが、当時新聞の文化欄に今よりずっと多くのスペースが割かれていた文芸時評では、それをどう扱ったのだろう、と気になりはじめると、またまた横道に逸れるので、〈表紙〉に戻らなければなるまい。
とりあえず、1971年2月号の文芸雑誌(五誌あったのだが、通例文芸三誌――「新潮」、「群像」、「文學界」――という言い方が通用していたようで、「文藝」と「海」は、なんとなく――無意識に――除外視されがちのようだった)の表紙のコピーを集めてみる。
A5サイズ(ほぼ、150×210ミリ)の天から6センチ幅のスペースに横組で、漢字一文字から三文字の雑誌のタイトルがそれぞれ少しずつ異なる書体の大きな明朝活字で置かれ、残りのほぼ正方形の中に画家たちの絵が収まるというレイアウトが、戦後に定着したらしく、総合誌、中間小説誌、判型は異なるが週刊誌も、レイアウトの基本は同じ形式である。
1971年2月号の文芸誌の表紙は、「群像」大沢昌助(抽象的な版画家)、「文學界」野見山暁治(デッサン風の抽象)、「文芸」(註・2)仲谷孝夫(具象日本画)というもので、「海」の中西を除いて、違いがあるのは、日本画の加山又造を採用している「新潮」だろうか。それ以外(と言っても3誌だが)は、〈洋画家〉の範疇に入る画家で、中間小説雑誌の表紙画が具象の女性像が圧倒的に多い('71年「群像」の大沢昌助は、「オール讀物」では、女優なのか銀座のホステスなのか、といった美女の顔を描いている)のや、総合雑誌が具象の日本画であるのとは意識の高さが違うのだ。このささやかな違いは違いとして、雑誌というメディアの〈表紙〉は、画家たちの絵を通して〈顔〉と呼ばれた時代があったことを改めて思い出させる。
若い新人作家だった頃の私は「海」の二年間分を除けば、文芸雑誌の表紙などなんの関心もなかったし(一部の作家の書いたもの以外、文章方面も)どれもこれも同じように見えていたもので、その点では『新潮一〇〇年』の編集方針と同じだったと言えるだろう。同書の百年分、月ごとの年譜には、雑誌の執筆者の名は記されているが、表紙の画家の名は書かれていないのだ。
石本正「新潮」1970年3月号
さて、石本正(しょう)という日本画家の表紙絵(「新潮」1970年1月〜2月)を今回見るのは、加山又造や横山操と同世代の日本画家なのに、なぜか名前を知らなかった画家が、どういう絵を描いているのか興味を持ったからである。1月、初日の出と松の枝、2月、紅梅の枝、5月、青空を背景に鯉のぼり、12月は雪山と枯木、と挙げると、その、愚鈍と呼びたくなるような歳時記的感覚が、たとえば、雪が降ったら、その翌月の文芸誌には随筆ばかりか小説にまでも雪について書かれた文章があふれる、と、蓮實重彦がそう時間のたっていない何年か後に文芸時評に書いていた状況というか事態と、表紙も中味も見事に一致していると言えそうである。
しかし、眼をひきつけられたのが、3月号の、抽象化された細い木の枝に止まって向きあっている2羽のふっくらとした銀白色のおかめインコ(頬にあたる部分に赤い丸い飾りがある)で、12枚中の3枚がそれぞれ種類の違う2羽の鳥の描かれた絵で、小さな画面に、それぞれ異なるタッチで一種、荒々しいデッサン風の線描が、鳥の体の持つ丸みを繊細な愛着でいとおしむように(いわば、指で鳥の体を見ているかのように)描かれているのだ。
村越画廊の桜井美穂子さん(隣人なのだ)に石本正のことを訊ねると、御存知なかったとは意外だという答えで、彼女は子供の頃、画廊主の父親に連れられて京都の石本先生のアトリエを訪れて遊んでもらったこともある、と言って、舞妓の特異なヌードで有名だという画家の画集を持ってきてくれたのだった。
石本正「新潮」1970年6月号
年譜によれば、1971年51歳の時、新潮社第3回日本芸術大賞と第21回芸術選奨文部大臣賞を受賞するが、以後、すべての賞を辞退する、とある。画集(「石正美術館開館記念展」カタログ2001年)の解説を書いている梅原猛(哲学者)は、選考委員をつとめる京都市文化功労者という表彰制度を、石本が辞退した理由を市の担当課長が次のように語ったと記している。なんとなく拙い口調で要約されているのだが、引用しておこう。「私は毎日女性の裸体を見ている。もしも絵描きでなかったなら、裸体を見るためには風呂屋をひそかにのぞかねばならないが、そういうことをすれば警察につかまってしまう。私は警察にもいかず、毎日裸体を眺めている。こんな幸せなことをして賞をもらうのはもったいない」。
さらに梅原は、石本正を「川端康成がもっとも愛した画家」と書いている。また芳賀徹(京都造形芸術大学学長)は、石本が「牡丹」(1989年)を描いた時、「氏はなんとオーストリアの『世紀末』の劇作家シュニッツラの作を映画化した『輪舞』を連想していたのだという」と、専らシュニッツラーという名に驚くのだが、芳賀の引用している石本正のイタリアの広場に響く鐘の音について書かれたエッセイ(「ピサの斜塔と『舞妓』」)の、スタンダールの小説を連想させる、いきいきとした短い文章に触れただけで(印刷されたものとは言え、石本の絵も見ているのだし)、『輪舞』が、シュニッツラーの原作ではなくマックス・オフュルスの映画であることに納得がいく。2羽のおかめインコをヌードの舞妓の乳房や尻のような丸味を持つように描き、舞妓を美しい鳥のように描きもする画家は、オフュルスの映画の女たちの華麗に花開く退廃の中の力強い可憐さが、女優たちの肉体を通してロンドのように渦巻く美しさに見惚れたのだろう。石本の牡丹は、丸谷才一が感嘆する木下利玄の名歌「牡丹花は 咲き定まりて 静かなり 花の占めたる 位置のたしかさ」とは対極にある。なにしろ、あのオフュルスの女優たちの輪舞である! オフュルスは、同じ一人の女優を、成熟した貴婦人や娼婦にも少女にも撮ることが出来る映画作家だったし、『快楽』('52年)では、ダニエル・ジェランの演じる画家に、シモーヌ・シモン(石本正の舞妓に似た短く丸い顔立ちの)の肉体の動きの素晴らしさを語らせる。『快楽』を批評してゴダールは「まさにこれこそが映画なのだ! ほれぼれするほど美しい女を出演させ、その相手役に《あなたはほれぼれするほど美しい》と言わせるということ、これが映画なのだ。これほど単純なことがほかにあるだろうか!」(奥村昭夫訳)と書いていたのを思い出した。オフュルスは女優たちに特別に信頼された映画作家でもあった。石本正の舞妓の丸いお尻や乳房やお腹は、石本が愛する、これほど単純なものがほかにあるだろうか、という感動で描かれているのだ。
註・1 文藝春秋では、画伯たちの表紙画を受け取るためにハイヤーで、タクシーでは失礼なので、しかるべき風呂敷も持参して担当編集者が伺ったそうである。もちろん、15センチ四方のスペースに収める表紙画は実際の寸法はともかく、絵画としては小品の部類に入るだろう。
註・2 「文藝」は現在では、この正字表記だが、当時は「文芸」という表記を採用していたのである。2016年、創業130年を迎えた河出書房新社には、正式の社史が無いそうで、そのかわりというわけではないのだろうが、『「文藝」戦後文学史』(佐久間文子)が同社から上梓された。カヴァーに「文藝」と「文芸」の表紙の図柄が載っているが、何年何月号かも画家の名も書いてないし、本文は一貫して雑に「文藝」と表記されている。

