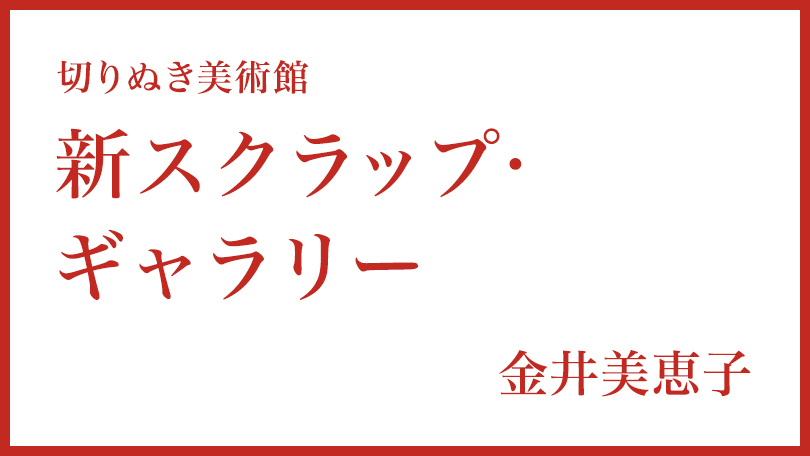
少女たち・女たち
描かれた少女の強い視線がこちら(描いている画家を通して絵を見る者)に、はっきりと向けられているのは、高山辰雄の場合「明るい日」(制作は1934年頃)のみかもしれない。
後に結婚することになる同じ少女をその二年後に描いた「砂丘」(1936年 東京美術学校日本画科を首席で卒業した卒業制作)で、少女は、波のような風紋の描かれた砂丘の斜面に横たわろうとしているのか、それとも横たわった姿勢から腕を支えにして起きあがろうとしているのか、夏のセーラー服の紺のスカートに膝は隠れているが白い革靴に白いソックスをはいた足は砂の上に完全に伸ばされているわけではなく、軽く膝を立てて曲げられているので、立ち上がりかけているようにも見え、画家はやや高い位置にいて、少女の姿をとらえている。
少女の視線はまっすぐこちらに向けられているのだろうか? やや上の方を見ていることは確かなのだが。砂色の背景のせいで曇り空のような印象の光の中で切れ長の一重瞼の眼の茶色がかった瞳を光らせている白いハイライトが、この、少女を上方からの視線で描いた大画面の絵(235.0×181.3cm)を見る位置によって、強く光る意志的(しかし、どのような?)なまなざしのようにも、うるんだまなざしのようにも見えて、見る者はこの絵の前で立ちどまることになる。
「明るい日」は横長の画面に、緑色の様式化されて描かれた優美な草むら(酒井抱一の「夏秋草図」の引用であるかのような)に「砂丘」と同一人物のように見えるまだ幼さの残る少女が描かれているのだが、この二つの写実的でしかも理想化された少女像から私たちが連想するのはバルテュスの描いた少女像だろう。
シンプルでモダンな白い袖なしのワンピースに白いソックスに白いメリージェーンを穿き、ブルーのリボンが巻かれた白い鍔広の帽子は脱いでかたわらに置かれ、少女は横たわって膝を曲げた左足の上に右足が載っている。首を横にむけて少女は真っ直ぐ(まるで何かに対して怒っているかのような強い視線で)こちらを見ている。
その後の高山辰雄の描く女性や少女たちは正面からこちらを強く見つめる視線を失い、いわば砂丘の砂の持つ無限の可変性と曖昧さが混りあっているかのような造形(言ってみれば線による造形を拒否しているかのような)とでも言ったものに飲みこまれていくようだ。「夕べ」(1942年)の幼い少女の何を見ているのかわからないような眼どころか、戦後、日本画滅亡論ということが言われたという時代に描かれた、モダンな構図と色彩の「たべる」(1946年)や「少女」(1948年)は、蒸したジャガイモを無心に「無我夢中で食べている」幼い少女には、細い線としてしか眼が描かれていないのだし、日本画的な写実描写は、少女が手に持っているジャガイモの載った九谷焼の小皿に残っているだけのようだ。
戦後も六〇年代後半の現代美術から「美術」に興味を持った青春時代を過ごしてきた者としては、「日本画」というのは、いわば圏外のもので、たとえば、現代美術批評家の東野芳明(1930年生れ)が、むろん冗談混じりだったのだろうが、川端龍子をたつこと読んで女流画家だと思い、女流画家片岡球子をきゅうしと読んで男性画家だと思っていたと「美術手帖」に書いていたのを、高校生の時に読んだ世代である。
「文藝春秋」や「中央公論」、文芸雑誌の表紙、あるいは子供時代であれば講談社の絵本と結びついた、いかにも古めかしい戦前的文化のように思えたものだが、この連載は美術批評ではなく、私が魅力を感じた好きな絵を画集や雑誌から切り抜いて集めた手帖のようなものなのだから、日本画の美術史は無視して、前回と同様に小倉遊亀の描く女性像を見ることにしよう。
1895(明治28)年生れで百歳を越えてなお絵を描きつづけた(2000年没)小倉の初期の絵には、清楚で愛らしく利発そうな、普段着の着物姿の小さな少女たちが描かれている。利発そうな集中度で身をかがめて草花を写生していたり(「首夏」1928年)、農婦たちに見守られて鉤針で毛糸を編んでいたり(「故郷の人達」1929年)、きちんと正座して真面目な、音曲のお稽古を受けているような表情で麦笛を吹いていたり(「麦笛」1931年)、やはり正座して、茹であがった豆の味を想像しているのか幸福そうに微笑みながら空豆の莢をむいていたり(「童女」1938年)、後年に描かれる中年の女性像(「夏の客」1942年)とそっくりな格好で白い無地のうちわを持った手を、正座した膝の上に置いた着物姿の大きな眼の少女(「童女」1931年)たちは、いわば、記憶の中の自画像なのかもしれない。
女性像の描き方のスタイルに、年を重ねるごとに大胆な自由さを発揮する小倉遊亀なのだが、描かれている女性たちの日常的な仕草から一瞬を切りとったようなポーズを見ていると、戦前の無声映画の時代から映画を撮りはじめ、戦後のある時期までその時代時代の風俗を背景に撮りつづけた映画作家の様々なシーンの記憶が重なってくるのである。
高山辰雄の戦前に描かれた二枚の魅惑的な少女像がバルテュスを思いおこさせる(少女がこちらを見ている絵は、バルテュスにも少なくて、ミロとその幼い娘の肖像をはじめ、描かれている対象の名がはっきりと記されている「肖像画」がそれである)のは少女の着ている服の描写、スカートとスカートに覆われて見えない部分と露出しているところのある足のせいかもしれないのだが、私たちとしてはジャン・ルノワールの『ピクニック』(1946年)のシルヴィア・バタイユが草むらに横たわって顔をこちら側に向ける圧倒的に官能的なシーンを思い出しもするのである。輝かしい人生の春の惑いの出来事であると同時に、シルヴィア・バタイユの超クローズ・アップされる眼は、ヒッチコックの『サイコ』の浴室で殺されたジャネット・リーの大映しになる見開かれた眼への連想を誘いもするのだが。
小倉遊亀の描く女性たちのたたずまいから私が思い出すのは成瀬巳喜男の映画の女優たちである。下町の芸者の置屋を舞台にした『流れる』(1956年)で、もう若くはない二人の芸者(山田五十鈴と杉村春子)が、時代や男や金銭に流されつつ、向きあって常磐津の三味線をお座敷よりも真剣な表情を見せてさらうシーンにみなぎる張りつめた空気を思い出すのだが、小倉遊亀の描く若い、あるいは中年や初老の女性たち(その中に昭和35年当時のスタア越路吹雪の肖像画も含まれるのだが)は、今までやっていた作業の手をとめて、休息というか、〈一服〉している様子で描かれているものが多い。

座敷に座っている麻の青に紫の柄のある着物に紫と白の縞の帯をしめた女性(「O夫人坐像」1959年)のかたわらには、夏物の縫いかけらしい布地と握りに赤の塗装のしてある、いかにも使いこんだ感じの裁ちバサミ、ラベルのダルマ糸のマークまでがくっきりと描かれた白いミシン糸が何気なく置かれている。O夫人の銘仙判の小ぶりな座ブトンに正座して両手を膝に載せているやや緊張した様子から、縫い物の途中で、何かかなり重大なことで家人に話しかけられている、とも考えられるのだが、とは言え、そこに流れているのは、「夏の客」(1942年)や「婦女」(1948年)もそうであるように、一種の張りつめた緊張感ではなく、日常的な、少し気の張る女性同士の訪問にまつわる微妙な意地悪をユーモアの混ざった観察力によって描いている。谷崎潤一郎の『少将滋幹の母』の挿絵のようには知られていないが、河出書房新社の挿画入りというのが売りだった『カラー版日本文学全集』(1970年)の『細雪』の線描の挿絵は谷崎の描写と小倉遊亀の女性像が見事に一致した魅力的で楽しいものである。明治、大正、昭和の三代を同時代人として生きた小説家と画家の女性的風俗に対する関心と興趣を楽しむことが出来る。
遊亀は、日本画の定番とも言える芸者と舞妓の舞う姿を描いてはいるのだが、それよりも座って、ふと横を向いた美しい衣装を身につけた少女像としての「舞妓」(1969年)の方が、なぜか魅力的だ。しかし、この静かな魅力は、越路吹雪を舞台に立つスターとしてではなく、大胆なたて縞の浴衣に半幅の帯というより柔らかなへこ帯をサッシュ・ベルトのように巻きつけた姿で脚を組んでデッキ・チェアに横たわった〈休息〉として描くのとは違っている。

