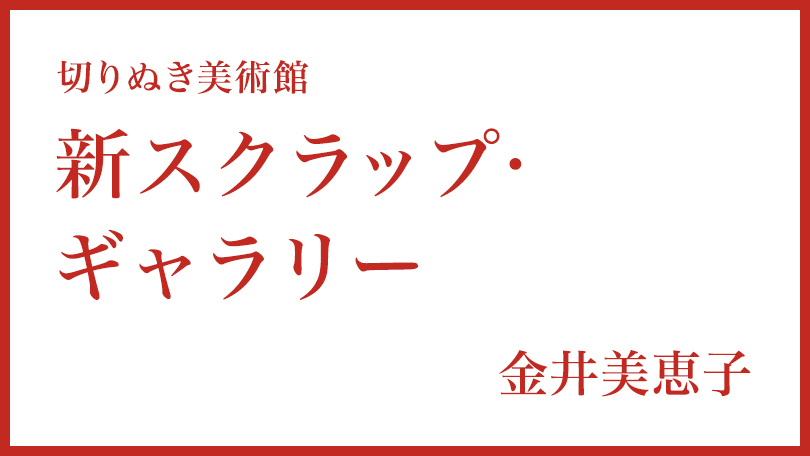
台所と画室
桜井さんは小学生の頃、父親と一緒に訪ねて、仕事の話しをしている大人たちを尻目に広い芝生の庭で柴犬と遊んだり、画室の隣室の六畳程の和室より一段低い張りの洋室に設けられた二階の休息室に通じる白い小さな螺旋階段がとても魅力的で昇ったり降りたりして遊んだそうなのだが、私たちを驚かすために、お寺のゆるやかな坂の途中にある小さな池の左手をしばらく行って斜面を横に入ったところに砂岩の丘の切通しがあって、その二、三十メートルはあるような印象の、水溜りがところどころに出来たトンネル(入口には一本の竹竿が受け木に差し渡してあって、この先には入れないことを示している)を通り抜けたところに砂岩丘を覆った緑に包まれた明るい空間が開け、心地の良さそうな木造の柔らかな印象の住居とアトリエが建っていることを黙っていたのだった。
すべりやすい山の斜面や濡れた道を歩くことになるので、当日はハイキング用の靴をはくようにと、桜井さんには前もって注意されていたのだが、アトリエが北鎌倉のお寺の広大な地所の中のどのような場所にあるのか説明されてはいなかった。
もちろん、何も知らずに初めて見て、驚きながら洞穴の奥に明るい緑の光が見える薄暗い切通しを歩くのと、それがあることを前もって知らされているのとでは、驚きはするものの驚きの度合というか質がまったく違うはずで、いかにも桜井さんらしい配慮(知的で、しかも子供っぽい好奇心とでも言うべきものを持つ者にしか出来ない心づかい)のおかげで、私たちはあたかも、トンネルを通って特別な空間の中を訪れたような経験をしたと言えるかもしれない(註・二)。
家に戻って、『百歳記念 小倉遊亀展』のカタログの見返しのアトリエの写真や、家族が増えたのにともなって画室に接して増築されたらしい応接室とアール・ヌーヴォー風デザインの洋間に孫たちとその母親がスナップ・ショットのような親密な自然さで並んでいるところを描いた「兄妹」(1964)を見たり、空間の関係を整理するために住居と画室の簡単な間取り図を描いているうちに、直接的なつながりはないのだけれど、ふと気になって読みかえしたのが『成瀬巳喜男の設計』(1990年 中古智/蓮實重彦)である。
このインタヴューの中で映画の空間設計の知性と知恵がつきない興趣で語られる『山の音』が鎌倉を舞台にした映画だということもあるのだけれど、小倉遊亀の描く女性たちの姿が成瀬の映画を思いおこさせるからでもあった。二枚が一組になっている「夏の客」(1942)、麻の着物姿の生意気そうな表情のいきいきとした若い娘が籐椅子に背中をもたせかけて足を組んでいる「娘」(1951)、縫い物の手をとめて、画面には描かれていない相手の言うことを耳にして座り直したかのような「O夫人座像」(1953)、萩江節(自身が"友亀"という名前を持つほど熱心に稽古をしたという)の、家元夫人がテープレコーダーから流れる音曲にあわせ膝の上で手に持った扇子で調子を取る姿の「聴く」(1974)、明るい茶色の塗りの盆に置かれた古九谷の大鉢に生けた河原ナデシコの三分の一程が画面の左端ですっぱりと切れた構図に、斜めの位置から描かれた老婦人は藍色の麻の着物に鬱金(うこん)の軽そうな夏帯(右袖の陰から微かに見える御太鼓帯は、鬱金と藍の織目が透きとおるリヴァーシブルのようだ)を着てゆったりと、しかし端然として、画のタイトルそのものの「涼」(1973)という姿で正座している。
私が思い出すのは、無声映画の『君と別れて』の吉川満子(この映画で、彼女は縫い物をするシーンで、女優には珍しいことに、着物の裾をくけるのではなくちゃんと運針をする)や、『鶴八鶴次郎』や『流れる』で三味線を弾く山田五十鈴や杉村春子、『歌行燈』のお三重の役で能の舞いを舞う山田五十鈴、『流れる』の栗島すみ子や高峰秀子、あるいは、小津の映画の時よりも、その運動神経の良さと動作の美しさが際立つ演出でいきいきとしている原節子(『驟雨』(1956)や『めし』(1951)での編物の針の使い方の素早い手つきや紙風船を打ちかえす動作!)といった女優たちである。
『流れる』(1956)で年配の芸者を演じる山田と杉村が向いあって長唄の三味線をさらう場面の高度に張りつめた空気は、まるでそれ自体が芸を競いあう者同士のみが知るお互いの力を認めあう仕事のドキュメントでもあるかのようで、かつての『鶴八鶴次郎』や『歌行燈』の持つ芸事の技術の競いあい的メロドラマの形式的な美しさとは異る、リアルな「芸」を新しく演じる者としての「女優」の強さが画面から響いてくるのだが、小倉遊亀の女性像(夏の着物の布地の持つ柔らかな薄さと繊維の持つ強い張りが、それを着る女性の存在感を際立たせている)には、どういう体勢で描かれているにせよモデルたちは自然な体の動きの連続性を、一瞬、切り取ったように見え、モデルの女性の強さと向いあう画家の姿が、『流れる』(幸田文の原作ではなく、成瀬の映画の)の山田五十鈴と杉村春子が三味線をさらうシーンの、いわば超越的な瞬間の緊張感のように眼に浮かぶのである。
小倉遊亀が戦後間もない頃に自分で設計して改築した、さっぱりとつつましく、しかも合理的な台所は、一日中画室に入って仕事をしている遊亀にとっては「時々はエノグの乾く間を見つけては食べものの工夫がしたくなる」という一休みのための空間であり、ちょっとした縫い物や読書、煙草の一服、来客のもてなし、家族との食事、窓の外に広がる庭の樹木(もちろん梅である)に眼をやって休む場として自らが設計したのだったが、家族が増えたことにともなって、画室に接続するように増築された玄関、和室の応接間、タイル張りの洋間、さらに画室と引戸一枚で廊下の介在なしにつながっているダイニング・キッチンも、その精神というか空間に対する感覚は、つつましく合理的で美しい「わたくしの台所」とまったく同じなのだ(註・三)。
ところで、ここで一見関係のないように思われる川端康成邸の話になるのは、『成瀬巳喜男の設計』で語られている『山の音』撮影時のエピソードとして、美術監督ならではの細やかな観察力で中古智の語る鎌倉の川端邸の描写が興味深かったからである。
「案に相違して」と中古智は語る。「古い書院形式の骨太の、剛毅簡素というか、重厚みのある建物で、床の間にはいつか美術雑誌で見た記憶のある池大雅の山水画が掛かって(中略)お座敷の左端に当たる庭の奥に、亭々とそびえる黒松の大木の数本が」立ち並ぶ前庭「大玄関」を裏に回ると「山裾が一面に迫ってきていて、お勝手口のあたりの山の斜面には石塊が臥龍のように立ちはだかり、他方の岩層は水気を含んだ苔や山草が生い茂っている」といった文学的な語り方をするのだが、言うまでもなく、この川端邸の空間は男性的なもの(案に相違していたにせよ)として美術監督の中古智に意識されているわけで、小倉遊亀の住いとアトリエを見た後で、この中古智の語っていた空間について思い出したのは偶然ではなく、鎌倉と北鎌倉の違いはあっても、地勢的にはほぼ同じ山と谷の起伏の一部をしめている土地に建つ男の文学者と女の画家の住む家が、くっきりと相反しているからなのだった。
川端邸の亭々とそびえる黒松や臥龍のような石塊、池大雅に対して、小倉遊亀の「新しい友だちのような」梅、玄関から切通しまでの間にある狭い通路が面している山の斜面の積石の間には可憐な岩タバコが咲き、大雅の山水ではなく、日常の生活の中でも料理や果物や花を盛る陶磁器(富本憲吉の作や、師である小林古径の遺蔵品が含まれている)である。
中古智の語る映画美術の奥深さと驚きにみちた細やかな感性の魅力については別の機会に触れることがあるかもしれないが、それはそれとして、川端邸の描写を通して、小倉遊亀の住んだ空間の持つ女性性はより際立って感じられるのだ。
私たちは、1895年(明治28)から2000年(平成12)の105年を生きて描いた女性画家の鋭い観察と描写があたたかなおかし味(ユーモア)を生みだす、いきいきとして美しい絵を見るために、その背景となった一世紀にわたる時代の女たちの風俗――動作や仕草や表情、むろん身につける衣類――を、実際には知らないのだから、イメージを補うため、サイレント時代にデビューし、1967年の『乱れ雲』にいたるまでほぼ一貫して女性映画を撮りつづけた成瀬の映画に登場する女優たちの肢体の美しくなめらかな動きを思いおこすのである。
四面の屏風に描かれているので、畑に植えられたやや湾曲した苺(いちご)の畝(うね)がより立体的な奥行を見せ、白い絣(かすり)に藍の三尺をしめ鶴の描かれた手拭で頭を覆った若い農婦が腰をかがめて上体と腕を伸ばし、赤い小さな苺(まだ実になっていない白い花も咲いている)を摘む「苺」(1932)は、いわゆる屏風画に描かれる題材とは大きく異っているだけではなく、ジグザグに屈曲した形で床に置かれる屏風の空間的性格が見事に生かされて、若い農婦の優美でのびのびした動きが、軽やかなどっしりさとして伝わるという意味でも、映画を連想させるのである。
小倉の描く女性たち、小さな少女から年配の和服姿の女性(自画像も含めて)、洋服を着た若い娘や、夏服でくつろぐ家族たちの情景、裸婦、芸妓や舞妓にしても、彼女たちにまつわる、いかにもそれらしい物語を連想させるいわば文学性といったものとは違って、画家の前でポーズをとるちょっと前に何をしていたのか、ポーズの休息に、どのように軽く溜息をついたり、伸びをして体を動かしたか、といった一連の連続する時間の流れの中で彼女たちの自然な動きと緊張が描かれているかのような時間性の中に存在していると言うべきだろうか。
そして、それは陶磁器と共に草花や梅の枝や果物の描かれた静物画でも同じことなのだ。小倉遊亀の安定を拒否するような構図の静物画の空間には、女性たちが描かれた空間と同じように、時間が流れているのである。
註・一 プルーストは「もし手仕事を余儀なくされたら」どうするかという質問(1920年の新聞のアンケート)にこう答えている。「貴下は手仕事と精神労働を切り離して考えておられるようですが、私はこの区別に賛成できません。精神が手を導くのです。私たちのシャルダン翁が(より巧みに)こう申しておりました――〈描くさいに動かすのは指だけではない。心を使うのだ。〉やはり絵画について語りながら、レオナルド・ダ・ヴィンチはこう言いました――〈これは《cosa mentale(コーサ・メンターレ)》(精神の営為、作品)である〉と。肉体の運動、たとえば愛についてさえ同じことが言えます。時として愛があれほどの疲労をともなうのはそのためです。」(『プルースト全集15』岩崎力訳)。ところで、「肉体の運動、...」以下の文章は新聞掲載に当って「謹厳ぶった記者の配慮」で削除された、と訳者による注にある。
註・二 鈴木清順の『ツィゴイネルワイゼン』(1980)には鎌倉の切通しが異界への通路のイメージとして登場したが、むろん、この切通しはそういったものではない。この映画では切通しの向うにあるのはロケとして使用した鎌倉の里見弴邸の、重厚な木造のいかにも男性的たたずまいだが、小倉遊亀が宗教哲学者の夫君鉄樹の住む北鎌倉の茶席の建物(京都仁和寺の飛濤(ひとう)亭の写しだという)も、むろん、男性的な精神の質実な簡素さのうかがえる建物だったことだろう。
註・三 台所と言えば、ルネ・マグリットはまさしく台所で、あの女性と幻惑とのコンプレックスの空間を描いたそうだし、実在の画家ではないが、ジャン・ルノワールの『牝犬』と、そのハリウッドでのリメーク作、フリッツ・ラングの『スカーレット・ストリート』でも、主人公の素朴派の素人画家(後に高く評価される)は台所で絵を描くのだったし、トリュフォーはルノワールのことを「良家の台所育ち」と書いていたが、ジャンの『わが父ルノワール』には、オーギュストの描いた若い娘たちがモデルになりながら、ストーヴにかかったポトフの鍋の煮え具合を注意し、幼いジャンをあやしたことが語られているし、アメリカのポップ・アーチストのジャスパー・ジョーンズはアトリエで画材のエンコスティックを煮溶かすかたわらでミート・ソースを煮ていたそうだし、そもそも、と言うのも妙なものだが、画家たちは、「台所」を愛しているのだ。フェルメールもシャルダンも台所で働く女たちの親密で自然な姿を描いている。
それらは、何かを意味する象徴としての人物や静物ではなく、そこにある、まさしく食欲をそそる食物としての静物画や、部屋に飾られた陶器や花の軽やかで確かな、しかし別の空間としての存在なのである。
ところで、『山の音』という小説のタイトルを書いていて、ふと思い出したことがある。語り手の信吾は、妻、長男夫婦、出戻りのひねくれた娘と鎌倉で暮しているのだが(もちろん、女中もいる)、出戻り娘は万事にしまりのない性格ということになっていて(映画では中北千枝子が演じた。ちなみに彼女は『流れる』では山田五十鈴の出戻りの妹で、五十鈴の置屋に娘と二人で厄介になっている役を演じた)、ホーレン草のお浸しを作ると、ゆで方がグチャグチャに柔らかすぎて、手で握って水気をしぼった時の指の跡がついている、と書いてあったのを思い出したのである。
もう一つは、原節子の演じた嫁の菊子が難産で生れた子で、胎児の額に鉗子(かんし)を引っかけて引き出して生れたものだから、額にうっすらと傷が残っているというエピソード(能の菊慈童の面を主人公が見る時に額の傷が語られるという記憶がある)に結びついているのだろう。これは後年、シャトーブリアンの『ルネ』を読んだ時、主人公のルネが「ぼくは母親のいのちとひきかえにこの世に生れてきたのです。ぼくは母のおなかから鉄の鉗子を使って引き出されたのでした」と語るところがあって『山の音』を思い出したのだった。両者にはなんの関係もないのだが、フランスの十八世紀の半ばにはすでにそうした外科手術があったのか、と思ったまでである。それとも、このやや異常な出産で誕生した二つの存在には、何か川端的な文学的関係があるのだろうか?


