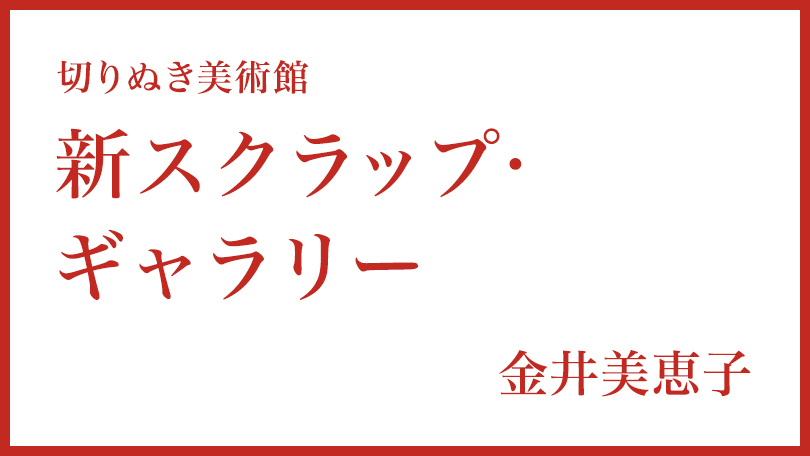
第9回
文芸雑誌「海」の表紙④
[ 更新 ] 2016.11.09
ところで、私は「三島由紀夫事件」をどう知ったのか。
姉の記憶では現代詩の雑誌の編集者から電話で知らされ、舞踏家の笠井叡からも電話があったそうで、画面を見るには、チャンネルをあわせて固定しておくためにダイヤルの隙間に消しゴムをはさみ込むという特殊なコツのいる古い白黒テレビのスイッチを入れたら、市ヶ谷の自衛隊駐屯地に楯の会のメンバーと一緒に乱入して、正面入口のバルコニーで演説というか、檄を飛ばす三島の姿が映っていたのだが、はっきりした記憶は、ほとんどないのだ。姉はさらに、前の日に遊びに来て泊っていた山田宏一がいたと言うのだが、それは確かに思い出した。
私たちはテレビで中継されている映像を見はしたが、何のリアリティも持てず、そうした意味でショックさえ受けなかったはずだ。後に三島の『憂国』を思わせる、日本陸軍の軍服姿で日本刀を持って踊ることになる笠井叡は、電話で衝撃を受けて緊張した声で話していたのに違いないのに、それもはっきりと覚えていないのは、山田宏一がもちろん面識などない三島由紀夫からもらった、映画『憂国』('66年)を各方面、海外のジャーナリズムを中心によろしく紹介してほしいという内容の(普通なら、プロデューサーとか宣伝係が書くものなのだろう)律儀で丁寧な手紙をもらったことがあったのを思い出し、引っ越しにまぎれて無くしてしまったけれど、手紙を取っておけばよかった、と言ったのも思い出した。
自衛隊員へ蹶起をうながす檄にも「作家の自殺」という19世紀的な文学的テーマにも、私は今でも興味がないのだが、当時(23歳になったばかりで、いわば無知な子供のようなものだ)はさらに稀薄だったはずのところにもってきて、現実主義者とは言えないけれど、スクリーンに映し出された世界――ことに女優中心の――以外には文学的夢想(自殺だの天皇だの)などとは無縁な山田宏一と一緒にニュースに接したのは、実に幸運だったと思う。
さらにその頃、私の住んでいたアパートの近くには、文化人類学の西江雅之が住んでいて、喫茶店で会ったら大きな声で、これからはアメリカやヨーロッパの会議で外国人がゴチャゴチャ言ったら、日本人は問題を解決せずにハラキリをしますって言って、おどしてやれますよね、と言い、周囲の客たちから顰蹙した顔で見られたりもしたことも思い出した。メディアは、ハラキリどころか「切腹」という言葉さえも使わず「割腹」と言っていたらしいのだ。
どちらかと言えば居心地の悪い滑稽さが28分という上映時間の全体を領していた『憂国』は、アートシアター新宿文化でルイス・ブニュエルの『小間使の日記』と併映されたのだが、私が二十歳頃まで住んでいた高崎では、東宝系映画館でなぜか新藤兼人の『鬼婆』と二本立て上映されていた記憶がある。いかにも悪趣味な日本映画における併映同士ではないか。(註・1)
1966年、映画が封切られた年に三島は「週刊文春」('66年5月9日号)で大宅壮一と対談をしている。大宅が「あれじゃ、もうかり過ぎて、たいへん」だろう、興行収入は併映の『小間使の日記』と半々なのかと訊くと、三島は短篇なので、「分け前は、ウンと少ない」と言い、アート・シアター系以外はフリー・ブッキング(自由上映)制なので「初日の入りで、地方の上映館の買値が倍になってくるんですよ」と、興行の「バクチのおもしろさときたら、たいへんなものですね」と発言していて、安い製作費で撮った映画を最初にパリのシネマテークやツール短篇映画祭で上映し、日本でも大当りしたことについて、わざとらしい程のプロっぽい大胆な率直さで「切腹場面というのは登場人物がたった一人の大スペクタクルで、カネもかからないし、それだけでお客が来ますからね。前にも、小林正樹さんの『切腹』という映画があるけれども......。いろいろな手があるんですよ」と語っている(『三島由紀夫映画論集成』山内由紀人編 ワイズ出版)。両人は、ブニュエルの『小間使の日記』について何も触れていないが、当時私としては『小間使の日記』を見に行ったら、『憂国』が併映されていてギョッとした観客が多かったはずだと書いておきたい。誰もが切腹好きではないし、まして三島の切腹というスペクタクルを見たいと思ったわけではあるまい。
ついでに、『小間使の日記』についてトリュフォーの言葉も引用しておくことにしよう。ジャン・ルノワールの『小間使の日記』を見て「逆説を弄するわけではないのだが、このアメリカ時代のルノワール作品は、その狂暴さゆえに、ルイス・ブニュエル版そのものよりもブニュエルに近い。ブニュエル版のほうはといえば、ちょっとのんびりしていて、おおらかで屈託のない感じが、まるで戦前のジャン・ルノワール風なのである」(『ある映画の物語』山田宏一訳)
と、トリュフォーは屈託のない調子で書くが、しかし、ブニュエル版は、労働者階級というか使用人階級がファシスト化する戦前の社会の陰惨な悪意を不気味に感じさせつつ犯罪映画の側面を持っていると見るべきだろう。ただ、小間使いのセレスチーヌ(ポーレット・ゴダード)が働いている家の隣人モージュ大尉(バージェス・メレデイス)の笑いを誘う子供っぽい乱暴さは、ブニュエル的とも言えそうだが、しかし、これこそいつものルノワール調ではないか、と思うのだが、それを若き日のトリュフォーは「おおらかな屈託のない感じ」と見たらしい。
表紙が当時(そして、現在も)いかに特異であったかを書くつもりだったのに、「海」が三島由紀夫の「事件」を扱わなかったことから、他の文芸雑誌がどうそれを扱ったか調べることに時間とスペースをとられてしまった。
『二つの同時代史』の中で埴谷雄高は、三島が編集したペンギン・ブックスの『ニュー・ライティング・イン・ジャパン』というアンソロジー(本が上梓される直前に三島は死んでしまったのだが)について説明している。埴谷の『闇の中の黒い馬』の一部、稲垣足穂、吉行淳之介、安岡章太郎、大江健三郎、安部公房、秋山駿、田村隆一、吉岡実、塚本邦雄などが入っている「不思議なほど広い範囲にわたった三島好みの編集」と埴谷は書いているが、この、「不思議なほど広い」と埴谷に言わせる「好み」に一番近かったのが「海」の編集方針ではなかっただろうか。少なくとも、稲垣足穂、塚本邦雄を載せる文芸雑誌は「海」以外になかったと思われる。
1971年1月号から1年間、「文學界」が野見山暁治、「群像」が大沢昌助、「新潮」が加山又造、「文藝」が仲谷孝夫(表紙構成は亀倉雄策)という実力派の中間画家たちが表紙の作品を担当している。「文藝春秋」は三島の岳父の杉山寧、「中央公論」は麻田鷹司(目次カットは赤瀬川原平、岡本信治郎)で、文化的に順当と言えば順当な穏当さなのだが、臨時増刊号となると「総特集 三島由紀夫の死を見つめて」の「諸君!」は、種野晴夫による楯の会制服姿の三島の本気ともパロディとも判断のつきかねる赤を背景に額縁におさまった銅像のような肖像画、「新潮」の「三島由紀夫読本」は、倉橋由美子の本のカヴァーや新潮文庫の『若草物語』、ジャン・ジュネの『花のノートルダム』や『泥棒日記』の表紙の絵も描いて、「若草物語」は、とりあえず許せるとしても、どうにもズレている印象を与える村上芳正の、薔薇族系とも、ヘタウマ系とも呼べそうな、装飾的と言えば言えるのかもしれない、感想の言葉の沈黙を「......」と表記する通俗小説の会話を引用したくなるような絵で装われていて、大岡昇平の日本文学の国際性というか世界性の有無という観点から、三島がノーベル賞をもらっていたら、川端の受賞はなかったから、二人とも自殺しなかったかもしれない、と書いていた知的な判断も何もかもが虚しくなる一方、目次を見ると、まあ、この表紙でいいかという気持になって、浅田彰が三島を評したキッチュという言葉を思い出すのであった。文芸雑誌は(「諸君!」もだが)切腹あっての「一人の大スペクタクル」としての雑誌と化したのだった。
文芸雑誌は「海」を除いて市ヶ谷の自衛隊駐屯地のように、三島によって、一瞬、占拠されたと言ってもいいだろう。
(註・1) 山田宏一は、アートシアター新宿文化の事務所で、ぱりっとした服装で立派な革鞄を持った三島が収益金の集金にやって来たのを目撃したそうである。

