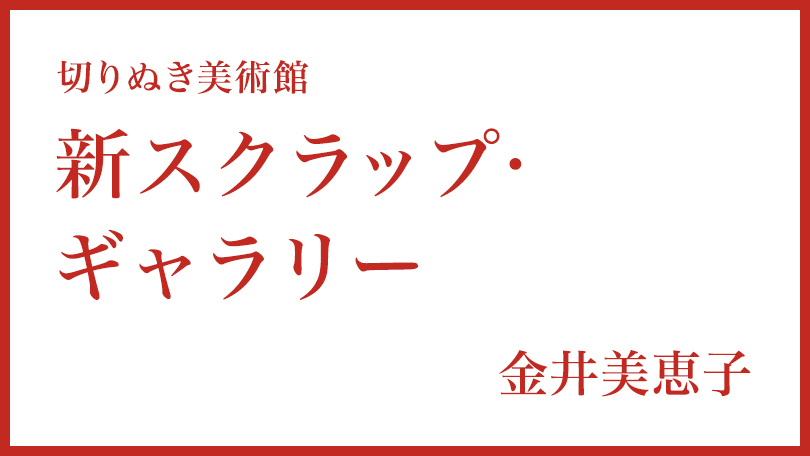
第1回
猫の浮世絵とおもちゃ絵1
[ 更新 ] 2015.11.24
歌川国利 流行ねこの温泉 明治14年(1881) 個人蔵
大きな黒トラで、立派なシッポの片目のオス猫を、片山健は絵本の中でそれがごく当然(あたりまえ)であるかのように、「タンゲくん」と名づけたのだったが、考えてみれば、その名の、いかにも自明に思われる由来を知る年代は、すでに70歳以上の高齢者である。
林不忘原作の丹下左膳と並んで、戦前から戦後の一時期まで、時代劇映画のスター的ヒーローだった鞍馬天狗も、むろん過去の存在だろうし、ヒーローの産みの親で、知的な大衆作家だった大佛次郎のことも、若い(という程ではなくとも)読者にはほぼ無縁と言うべきかもしれない。
ちなみに、「大佛」は「おさらぎ」と読み、戦後に書いた長篇時代小説『赤穂浪士』は連続テレビ・ドラマ(昭和54年)にもなっていて、主題曲は武満徹の作曲だった。後にやはりテレビ・ドラマ『夢千代日記』(吉永小百合が原爆症[と、川端康成の『雪国』のイメージも]を背負った、ものさびしい北陸の町の、はかなく美しい芸者を演じて、大評判だった)の主題曲も武満は作曲したのだったが、両者がそっくりの旋律なので、びっくりしたものだったが、それはそれとして、猫好きで名高い大佛次郎(戦後生れの者としては、大佛ではなく、新字の大仏でなじみがある)の随筆集『猫のいる日々』(初めて読んだのである)に、明治初期にさかんに作られた子供の「おもちゃ画」の「猫の湯屋」のことが出て来る。
猫のお湯屋と言えば、もう何十年も昔、浅草仲見世の江戸趣味玩具の助六の奥に、ひっそりというわけではないのだが、特別な非売品というおもむきで、20センチ四方にもみたない愛らしい湯屋のオモチャが置いてあったのを見て、すっかり魅了されたのだった。
この4月(2015年)、名古屋市博物館の猫を描いた浮世絵とおもちゃ絵を展示した「いつだって猫展」にも、平成に作られた助六製「猫の湯屋」が展示されていたけれど、昔のおなじ店の湯屋は、いちいちの細部にわたって、もっとずっと繊細な細工で、なにしろ、職人のモデルになった猫たちが、今時の部屋飼いの猫なのだろうか、栄養過多で大きすぎるのである。
さて、大佛次郎がおもちゃ絵の「猫の湯屋」について書いているのは、昭和46年の新聞に連載したエッセイの中で、私が仲見世の助六で「猫の湯屋」を見て、あまりの愛らしさに興奮したのも同じ頃だった。
大佛は築地の病院に入院中、湯島の画廊に、大の猫好きという共通点もあって親しかった画家木村荘八の小品展を見に行き、木村の描いた猫の湯屋を買い求めて、病院の壁に飾ったのだった。
木村は、明治初期にさかんに出版された子供の「おもちゃ画」(猫の湯屋や婚礼や、おさらい会や、町角の店などいろいろ)を集めていて、亡くなった後、夫人がそのコレクションを、鎌倉の大佛氏の家にとどけてくれたという間柄だった。
ところで、病院の壁に飾った「猫の湯屋」の絵を見た若い看護婦諸嬢にはそれが「何の画かいっこうにわからない」ことに大佛は大変ショックを受けたらしい。大佛次郎、74歳の頃である。自分とは「世代も数段違う」彼女たちは「猫が銭湯へ行く洒落を」「不合理で非民主的と考え、こんな画を壁にかけて喜んでいる患者は、軽度の精神病科へ回すべきだと診断したのではないか」と冗談まじりに書いているが、若者の想像力のなさに、よほど頭に来たと見えて、次の回にも「猫の湯屋」について書いている。
若い看護婦さんたちだけではなく、回診に来る医者、「中年からそれ以上の、もっともらしい、もとより学識も高い紳士たち」も「首を傾(かし)げて、これが猫が集まって何をしているのですかと、疑問にせぬ者は一人としてなかった。」し、知りあいの50歳ちかい年齢の国立劇場の理事にも「猫の湯屋」の絵を知っているかと問うと、見たことがないという「如何(いか)にもきっぱりした返事」で、「私を失望落胆のどん底に陥れた」というのである。昭和史年表を見ると、猫関連的には、その前々年には、「黒猫のタンゴ」という、小学生か幼稚園の男の子供が歌った歌が流行していたし、赤塚不二夫の「ニャロメ」が大活躍していた時代で、10年後には、小猫に応援団風のガクランを着せた写真の「なめネコ」というものがブームになったのを覚えている。
明治期木版刷りの、言ってみれば千代紙のような子供の手すさび用の猫のおもちゃ絵そのものは、忘れ去られていたとは言え、家の中に我物顔で棲息する身近な(凄く愛らしい)ペットであるばかりか、たくましい野良猫であったり(大衆芸能史的には化猫だったり)しながら、「おもちゃ絵」のココロは、どっこい生きていたのである。
実物の生きた小猫にガクラン(にかぎらず、服全般)を着せるというセンスは、どう見ても悪趣味としか言えないけれど、猫には、絵画のうえで、そして、むろん言葉のうえでも、擬人化をさせずにはいられないといった魅力があるのだ。
しかし、そんなことを言ったら、「鳥獣戯画」はどうよとすぐさま反論されるだろうし、「西遊記」の猿、豚に河童、神話や民話的にはオオカミだって犬だって熊だって、それにもちろんキツネのルナールがいるし、リスだって立派なトリック・スターになるし、猫を天敵とするネズミにおいてをや? トムとジェリーを見よ、である。
それは、もちろんそうで、猫のおもちゃ絵には、ネズミもそれ相応に愛らしい仕草で登場する。
大佛次郎が、今日では「猫の湯屋」の江戸的諧謔は「不合理」で「非民主的」に見えるのかもしれない、と自らの老齢というか、時代とのズレ感を嘆いてみせた時から40年以上の年月が流れた。今年は戦後70年だったのだが、猫の浮世絵やおもちゃ絵、招き猫をはじめとする猫玩具を展示した美術展は、平成26年夏には栃木県の那珂川町馬頭広重美術館でも行われていたし、名古屋の「いつだって猫展」は大変な盛況だったのだから、平成の今日、大佛次郎は嘆かずともいいことになったわけである。ペットとして飼われている猫が犬の頭数を抜きそうだと言われている今日だが、歌川派の浮世絵に美人とその飼猫の画題が好まれ盛んに登場した江戸時代の日本の町では、犬という動物は今のように家族ごとのペットとして飼われ方をしていたのではなく、いわばある地域全体で、なんとなく飼われていたらしい。落語の『元犬』のシロなどが一つの典型でもあったのだろう。明治維新が犬の飼い方を変えたのだ(『犬の伊勢参り』仁科邦男 平凡社新書)。
ところで、今年、ジャーナリズムでは新安保法制に反対する勢力としての「民主主義」や「言論の自由」がちょっとしたブームだったが(むろん、国会前でのデモも盛んだったけれど)、『パリ燃ゆ』(1964年)で「パリ・コミューンの乱」について書き、『ドレフュス事件』や『鞍馬天狗』の作者である大佛は、昭和46年、「猫の湯屋」を知らない若い看護婦や知的階級の紳士たる医者が、古い猫のおもちゃ画を「非民主的と考え」ていると思ったのだろうか。
13世紀、イギリスの大憲章(マグナカルタ)で制限された王権から派生したコトワザ「猫も王様を見ることができる」を思い出すならば、猫も銭湯へ行く「おもちゃ画」は民主的ということになりはしないか。それはそれとして、60年代の全共闘運動(大学医学部のインターン制度のヒエラルキーに対する批判が運動の重要なモメントだった)がシラケ世代へと移行する71年、非民主的な立場にいたのは、猫ではなく若い看護婦たちだったはずだが、彼女たちは、「非民主的」といった言葉づかいを普通にしていたのだろうか。それとも、老人の思い込みなのか。
明治のおもちゃ絵については、岡本かの子の『女体開顕』の中で、進歩主義的近代主義者の出版人が、猫ニャン犬ワン式の古めかしい子供相手の絵本から脱却せねば、といった発言をするところがあったが、そのおもちゃ絵は海外へ輸出されたのである。(次回へつづく)

