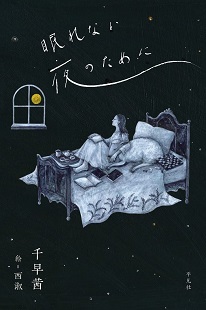第1話
空洞
[ 更新 ] 2023.07.20
隣で横たわる娘はくったりと手足を投げだして、小さな汗ばんだ頭を撫でても身じろぎすらしない。その向こうでは夫の大きなお腹がくろぐろとした山になっている。私以外の家族はみな、深い眠りに沈んでいる。
眠らなくてはと、まぶたを閉じる。けれど、目の奥にすこんとした空洞がある。寝返りをうつたびに、その空洞が鳴る。空っぽの音がからからと響く。
夫のいびきが響く寝室を抜けだし、裸足で廊下を進む。空調の効いたマンションの床は冷たくも温かくもない。窓の外で朝までまたたく、高層ビルの光のようだと思う。温度のない都会の夜。
シンク台の下の棚に腕を差し込む。林のようにならぶ料理酒やオリーブオイル、胡麻油、パスタの細長いタッパー。その奥にある金属の缶にかちんとネイルが触れる。缶はいくつもある。爪先で軽く弾けば、中が空洞かどうかわかる。しっかりと重さのある缶をひとつ出し、抱えるようにしてキッチンのスツールに座り、透明なテープをつつつと剝がす。缶の蓋を開け、はりはりと音をたてる薄い紙をひろげると、バターと砂糖の甘い香りがたつ。
明かりは換気扇の下のぽつんとしたライトだけで充分。長細い窓からは月よりも強い都会の光が入ってくる。洗いものが完璧に片付けられた銀色のシンク台はレフ板の役目を果たし、缶の中にぎっしりと詰まったクッキーたちをぼんやりと浮きあがらせる。ザラメのついた丸いディアマン、レモンアイシングクッキー、長方形のアーモンドサブレ、木苺ジャムサンドクッキー、ココアサブレ、絞りだしクッキー、紅茶のビスケット。さまざまな形のクッキーの隙間を小指の先ほどのメレンゲと細長いビスキュイが埋めている。ざらりとした茶色い世界。揺すっても絵のように動かない。もろいクッキーたちが互いを支え合い、それぞれのおさまるべき場所におさまっている。寝静まった家族の寝室のように。
けれど、その完璧は一枚引き抜けば、もろく崩れる。さく、さく、さく、と私の歯のあいだでクッキーが砕かれるたびに、缶の中の静寂と均整は壊れていく。もう、元には戻せない。あちこち隙間のできたクッキー缶は、揺すればクッキー同士がぶつかり合い、粉々になってしまうだろう。ふたたびクッキー缶に静けさを取り戻す方法はひとつだけ。空っぽにすることだ。
自分の手が口とクッキー缶を行き来する。単調な機械のように。深夜の食欲はぽっかりした穴のようで、食べても食べても空洞がふくらむ気がする。キッチンは静かで、時間も止まっているかのようだ。実家の台所はいつも冷蔵庫の唸りが響いていた。べたつく床はひんやりとして、唸り続ける冷蔵庫は温かく、ごちゃごちゃとものにあふれていて、なんだか安心した。この、私の希望で選んだはずのキッチンはつるりと整っていて、物わかりの良さそうな調理機器たちは大人しく眠ったままで、少しつまらない。秘密のクッキー缶と私だけが異物に思える。
いったい、いくつのクッキー缶をこうして空けただろう。マーガレットの形の丸い缶、黄色と白のストライプの缶、潔い白一色の缶、真四角の銀缶、紋章のエンボスが入った老舗の缶、小花柄や水玉模様……どれも仕切りのない、びっしりとクッキーが詰まった缶だった。こっそりと買い求めて空にした、たくさんの缶がシンクの下に隠されている。
姉と弟がいた私は、子供の頃、クッキー缶をひとりじめできたことなどなかった。年に数回、親が誰かからクッキー缶をもらうと、まずじゃんけんで食べる順番を決めた。ココナッツが入っているものが私にとっての外れで、姉の外れはシナモン味だった。弟はなんでも好きで必ず大きいものを狙った。クリームやジャムが挟まっているものは二枚とみなされた。好きなものばかりを食べると不興を買い、全種類を制覇するには頭を使わねばならなかった。美味しいうちに食べ切ってしまいたいのに、クッキー缶は何日もかけて食べられ、最後のほうは湿気ていた。それでも、缶を開けるたびにじゃんけんになった。食べ終えた後もじゃんけんがおこなわれ、手に入れた空き缶は宝物入れになった。青に白の草花模様が描かれた缶が一番のお気に入りだった。その缶の縁に赤茶色いサビが浮いてきてもずっと手離さなかった。
缶だけではない。リボンも包装紙も紙箱も捨てられない。このレースはきれいだから。これは良い香りがするから。これは頑丈だからなにかに使えるかもしれない。あれこれ理由をつけては溜め込んでしまう。私のひとり暮らしのクローゼットの中を見た、恋人だった頃の夫は言った。
「空き箱や空き缶の数だけ、部屋に空洞が増えるんだよ」
一緒に暮らすようになると、使えない空洞は無駄だとも言われた。もっともだと思う。現に、私は小さい頃にクッキー缶にしまっていたものをはっきりと覚えていない。転校していった友人からの手紙だったか、交換してもらったキラキラしたシールだったか、果物の香りの消しゴムだったか。なんにしろ、きっといまは必要ではないものばかりだ。
でも、空洞はそこらにある。この眠れない夜も、作ったはずなのに思いだせない昨日の夕飯の記憶も、どんどん大きくなる夫のお腹も、ママ友とのお喋りも、空洞みたいなものなのではないか。生活には空っぽが散らばっている。隙間の目立ってきたクッキー缶から顔をあげ、細長い窓を見る。林立する高層ビルやマンションの窓が数えきれないくらいある。あの中だって空洞だ。無数の空洞が浮かぶ夜。
自分の中の空洞をこうばしいクッキーで埋めると、気怠さと共に眠気がやってくる。歯をみがく気力もない。ナッツの匂いのげっぷをしながら、空になったクッキー缶を棚の奥の暗がりにしまう。
指が他の缶に触れた。からん、と小さな音がした。手に持つと、からからと鳴る。楕円のレース模様の缶だった。開けると、苺や星をかたどったビーズをつなげたブレスレットが入っていた。娘が大切にしているビーズだった。
そっと戻して、寝室に向かう。まぶたを閉じても、もう目の奥は虚ろに鳴らなかった。娘の小さな愛らしい秘密が赤やピンクや銀のビーズになって頭の中に詰まっていた。
*続きは書籍『眠れない夜のために』でお楽しみください。
ご購入はこちらから