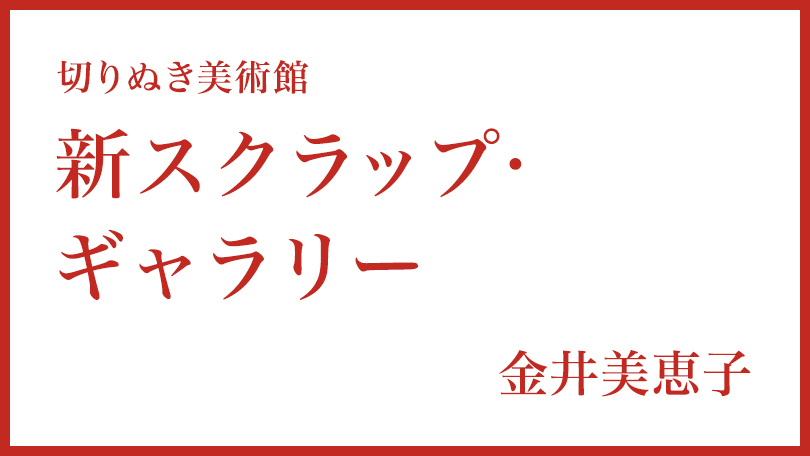
第2回
猫の浮世絵とおもちゃ絵2
[ 更新 ] 2015.12.25

歌川国芳 荷宝蔵壁のむだ書 嘉永元年(1848) 個人蔵
平成26年にあった「福を招く! 猫じゃ猫じゃ展」(那珂川町馬頭広重美術館)の魅力的な内容のカタログを見ていたし、5月にはたまたま横浜の大佛次郎記念館にも行ったことだし、やはり実物の版画を見たいと思って、「いつだって猫展」(2015年4~6月)に、とるものもとりあえず、名古屋市博物館に行ったのだった。
猫の浮世絵の名品も数々のおもちゃ絵や立体の玩具も、大きな公共空間の美術館に展示されたものを一度に大量に見ることになると、疲れるのは確かだし、猫好きを自認してはいても、いささか、もっと端的に言ってしまえば、あきる、のである。
すっきりと区分された各展示室は、まわってもまわっても猫、で、大変な混雑だという評判の「いつだって猫展」は、確かに年寄りから団体の中学生までがつめかけている。
入口から展示室全体のほぼ前半の中頃あたりまでは、中学生から年寄りまで、群がって猫の浮世絵を見ているものの、そこを過ぎると鑑賞者の数が急に少なくなるのは、どうやら、途中であきて帰ってしまうらしいのだ。
たとえば、上下巻で出ている本の場合、たとえ推理小説でさえ、上巻より下巻の売れ行きが悪いのと似ているかもしれない。とかく、大衆と呼ばれる善男善女は老いも若きも子供等も、浮かれやすくあきっぽいのである。
とは言っても、浮世絵もおもちゃ絵も絵草子も、半紙(25センチ×35センチ見当)の大きさに刷られたもので、手にとって眺めたり、絵草子なら頁を繰って読み、おもちゃ絵ならば、鋏で切り抜いて遊んだりしたもののはずだから、小さな版画をあつかっている画廊ほどの空間の壁ならばともかく、美術館という空間とは、本来的にあまりなじまないのではないだろうか。幸い、画集なみの厚さのカタログが両展には用意されているので、家に帰って、カタログの図版の絵のすみずみを手にとってゆっくりと見ることが出来る。
明治時代に作られたきせかえ人形。着物のすそは切り離さずに折り、間に猫の本体を挟んで遊ぶ。
ところで、人々はなぜ、大変な情熱をかたむけて猫を擬人化するのだろうか。
歌川国芳にしても広重にしても、絵を見れば、猫を心底愛していたのが一目でわかる描き方で、絵師として、様々な猫を様々な情景でユーモアを利かせて、細やかに描く洗練された高度な技術的喜びを満喫していたことが伝わってくるのだが、子供相手のおもちゃ絵を見る楽しみはそれとは少し違う。
戦後生れの私たちの世代にとってのおもちゃ絵は、駄菓子屋で売っていた粗末な紙に粗悪な印刷の、洗練とはほど遠いいかにも子供相手(と言うか、子供だまし、という気もしたものだったが)の、ぬり絵や着せかえ人形、家族あわせ、スゴロク、メンコ、子供向け雑誌の付録の切り抜いて組み立てる学習おもちゃのピンホール・カメラや幻燈機、飛行機や自動車といった類いのものだったことを思い出すと、美術館で行われる「猫」展に展示された、江戸末期から明治の初期のおもちゃ絵が、それを買って遊んだ子供たちにどのように扱われていたか、想像がつく。
猫の図柄のものだけでも百種類が現存しているというおもちゃ絵は、むろん、私たちの世代の、紙の学習おもちゃ付録やぬり絵や着せかえ人形たち(すごく時代遅れで野暮ったいケバケバしいドレスや着物を着ていたものだ!)は、アンデルセンの『すずの兵隊』に登場する紙のバレエ人形のお嬢さんもそうだっただろうが、すぐに捨てられてしまうものだった。切り抜くのに失敗したりして、ごしゃごしゃと手で丸めて捨てても、もったいない、といった気持になるような値段のものではなかったはずだ。
森茉莉は子供時代、こづかいで買った千代紙を存分に使っていろいろ作ったり切ったり折ったりして遊んだあげくにすぐ捨ててしまったそうだけれど、妹の杏奴は切ったり折ったりしないで千代紙を大切にしまっておいたそうで、それを茉莉は取りあげようとしたそうである。いかにも茉莉的ではないか。
ところで、『吾輩は猫画家である――ルイス・ウェイン伝』(南條竹則、集英社新書ヴィジュアル版、2015年)によれば、イギリスの19世紀末から前世紀の初頭に人気の高かった猫画家ウェインの描いたクリスマス・カードの図柄が、漱石の「猫」に「何らかのヒントを与えた可能性があると言わなければなるまい」と言うことなのだが、それはそれとして、この本の中に多数収められているウェインが雑誌に発表した擬人化された何匹もの猫たちが、いろいろな格好で思い思いにボートに乗ったり学校に行ったり、いたずらをしたりしているイラストを見ていて、思い出したのが「猫じゃ猫じゃ展」のカタログに掲載されている明治時代に海外への輸出品、土産品として作られた「ちりめん本」である。
カタログに載っている和紙に摺った木版画に縮緬加工をしたいわば一種の工芸品のようでもある二冊の絵本は1888年と1891年のもので、表紙には箱に入れられた犬(これが実は主人公なのだそうだ)を囲んで何匹もの猫たち(彼等は化け猫で、毎年人身御供に村の若い娘を要求する)が、傘を被ったり、手拭いを被ったりして怪しげにクネクネと輪になって踊っている図の『しっぺい太郎』と、ネズミが悪知恵をめぐらして猫を裁判所に訴えるが、結局、猫の正しさがわかるという中国の話しを元にした『老鼠告状』の二冊が紹介されている。
浮世絵がフランスの印象派の画家たちに与えた影響ほどのものではないにしても、猫の浮世絵やおもちゃ絵もヨーロッパに渡っていたはず(なにしろ、輸出用の陶器は緩衝物としての浮世絵に包まれて輸送されたのだ)だし、軍人として訪れたピエール・ロティは、日本の昔話として、一年に一度、猫が夜中に集って頭に絹のハンカチを被って輪になって踊る、というものを紹介している。けだし、手拭いのことだろう。
それから何がおこる、という続きがあるわけでもなく、ただそう書いているだけなのだが、「いつだって猫展」のカタログの「化ける猫」の章には、江戸後期に大流行した歌舞伎や合巻本の化け猫ものが紹介されていて、化け猫たちは、二本足で立ち、長い尾の先が二つにわかれ(こうした尾を持つ猫を「猫また」というのである)、手拭いを頭に被っているから、ロティはこの猫のことを、どこかで眼にして、怪談ばなしの部分を忘れてしまったのかもしれない。
アンリ・ルソーは、面識のなかったピエール・ロティのポートレートを、新聞の記事を読んで想像で描いたのだが、ロティはオリエンタリズムの作家にふさわしくトルコ帽を被り、巻きタバコを指にはさみ(凄く不器用そうにはさんでいる)、画面の手前の丸いテーブルらしき台の上には、気の利かない感じで前あしを広げて座った黒トラの猫が描かれていて、トラ柄というより、この猫は職業が水夫なので横ジマのシャツを着ている、とでもいったように見える。
ピエール・ロティと猫が一緒に描かれたルソーの絵を思い出すと、国芳の「荷宝蔵壁のむだ書」という、当時の人気役者の似顔絵を落がき風の素人っぽいタッチで描いた絵の中央で、大でき、大できと小賢し気な顔で手拭いを被って踊っている白地に黒ブチの猫またの絵の載っているページをまた開きたくなるのだ。
ところで、なぜ、人々は小動物たちに人間と同じようなふる舞いをさせたがるのだろう。絵に描いたりアニメーションを作るくらいならまだしも、ハクセイの小動物たちが人間と同じように宴会を開いて食事をしたり、教室で勉強をしている様子を作って展示したイギリスの美術館となると――。
(つづく)

