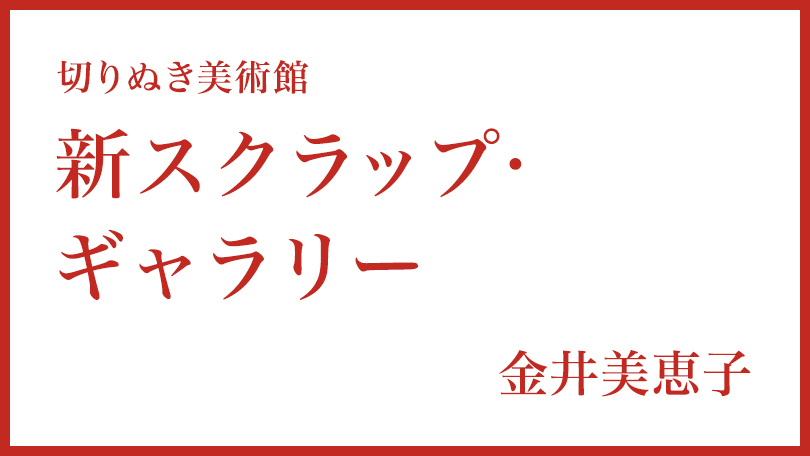
第3回
おもちゃ絵から猫の肖像へ
[ 更新 ] 2016.01.25

浅草田甫酉の町詣 歌川広重 安政3年(1856)
見たくもない、というか、眼にするのもけがらわしく厭わしいと思ったものだから、記事も写真も一瞥しただけなのだが、何年か前、「芸術新潮」のイギリスの変ったミュージアム特集(註・1)に載っていた小動物の剥製を擬人化しいろいろな情景を製作した19世紀の剥製師ウォルター・ポッターのミュージアムは、ネットで調べると、ポッターは、15歳から82歳まで1万体の小動物を擬人化して、まるでビアトリクス・ポターの絵の3D化のような可愛いらしくグロテスクな剥製を制作した、とも言えるかもしれない。剥製の小動物たちには言うまでもなく、ビアトリクスが実際の生きている動物を見ながら描いたいきいきした物語性というものに決定的にかけている。複雑な、と言っても適度に単純な心の闇方面が、それなりの広さと浅さで存在しているのだろうとこの執念の剥製小動物群を見たら誰もが考えるだろう。ルイス・ウェインの猫画は、ポッターの剥製擬人小動物群に似ているところがあるような気がする。簡単に言うと、そこには、人間のペットであるものの野生の生き物でもある猫が時に私たちに見せる生きもの特有の〈孤独〉と〈気高さ〉が欠けているのだ。
江戸趣味的洒落っ気の粋とも言うべき国芳を中心とする歌川一派の猫版画(擬人化された猫たちの芝居絵や団扇絵、文字絵など様々な)やおもちゃ絵は、もちろん、見ていて見あきることのない豊かな巧緻と魅力的な美しさを備えているのだが、擬人化された動物に対して、絵だけではなく、物語も含めて、どことなく疑念と言うか不信の念、あるいは一種の恥かしさ(どこか、なぜとも知れず、何かを馬鹿にされたような感じの?)とでも言ったような、複雑な感情を持ってしまうのは、私たちが近代化されているせいだろうか。
なにしろ、昭和20年代、迷信に関する調査では、キツネやタヌキが人を騙すということを信じる人の割合が20パーセントを越えていたという記述を何かで読んだのを覚えている。と言うことは、落語の「王子の狐」なども、面白おかしく語られてはいるけれど、大筋のところで本当のこと、と信じて聞いていた人たちがいたわけだし、正月と盆に上映される映画の狸御殿ものに登場する狸の若殿や姫君を(市川雷蔵や若尾文子のような、とまでは思わないにしても)、いると思って見ていた大人や子供が20パーセントはいたということになる。
一方、19世紀末のパリで幼い少年だったジャン・ルノワールの場合である。父親の絵のモデルになる退屈さを、女中さんが読んでくれるアンデルセンの童話によってまぎらわせていたのだったが、訪れた客がそれを見て、小さい子供に動物が人間のように話したりするようなコントを聞かせたりすると、ナンセンスを本当のことだと信じてしまいますよ、とルノワール家の教育に対して助言をしたというエピソードが『わが父ルノワール』の中で語られている。
フランスと言えば、動物は、ルナール狐の説話、ラ・フォンテーヌの寓話、シャルル・ペローの童話の中でペチャペチャとお喋りをしているではないか、動物を擬人化した有名な画家たちだっていたのに? と読者は思うのだが、幼児教育について助言したルノワール家の客は、大革命以前に書かれた動物寓話には、アンデルセンのような今風に子供に媚びるものとは違って、ちゃんと立派な教訓が明示されているフランス式合理精神で出来ているから安心、と考えていたのかもしれない。
19世紀のフランスのブルジョワが、動物についてどう考えていたかと言うと、蟻を例にあげるならば「浪費家をたしなめるのによいお手本。貯金箱の思いつきを人間に与えた。」(フローベール『紋切型辞典』山田𣝣訳)というようなものである。「イギリス女」という項目は「彼女らにして可愛らしい子どもを産むとは驚くべし。」というものである。こうしたブルジョワジーを読者とも風刺の対象ともして、ドレやドーミエ、最近、日本でも知られるようになったグランヴィルといった画家たちの風刺画が成立したのだが(ちなみに、『紋切型辞典』の「風景画」の項目は「つねに『ほうれん草料理』」である。樹木や草の緑色ばかりが目立つ絵を、そう言ったわけだ)、ここではフランス19世紀の獣頭人間の風刺画について触れるわけではないのだが、2年ほど前に上梓された『諷刺画家グランヴィル――テクストとイメージの19世紀』(野村正人 水声社)に、1830‐40年代の「ロマン主義挿絵本」の流行を可能にした19世紀前半の「連続抄紙、機械印刷、木口木版」といった技術革新によって相ついで製作されたラ・フォンテーヌの挿絵本についての記述があり、19世紀初頭から末まで多くの画家たちが挿画を描いたラ・フォンテーヌの『寓話』には、1894年フランマリオン社の「河鍋暁翠(暁斎の娘)、狩野友信ら五人の日本人画家を使った和風の挿絵本まで出版している」のである。ここに名は記されていないが、歌川一派の絵も使われていたのではあるまいか。見てみたいものである。
猫 高橋弘明 昭和6年(1931)
さて、前置きが長くなったのだが、今回私が書きたかったのは、擬人化されたり、怪談や寓話に登場したり、美しい細部の描かれた衣装をまとう美人と共に描かれる「猫」ではなく、猫がそれのみで主役として描かれた、あまり数が多くはなさそうなタイプの浮世絵のことだったのだ。
安政4年(1857)というから、死ぬ前年に描かれた広重の「名所江戸百景」の一枚「浅草田甫酉の町詣」には、吉原の遊女に飼われている猫が出格子に後ろむきに座って、外の吉原田甫の道をお酉様の熊手を買って肩にかついだ人々が歩いているのを眺めている様子が描かれている。短いしっ尾だけが黒の、ふっくらした感じの猫で、広重の『浮世画譜』(絵の手本帳)に収められている様々な姿のスケッチに登場する猫たちも、柄こそ違うものの全員しっ尾が短いのは、江戸時代の猫の特徴(長い尾が嫌われて、断尾も行われたという)なのだが、こうやって、窓辺に座って部屋の中から外を眺めている猫の姿には、むろん、「外」への好奇心を感じさせはするのだけれど、それ以上に、なんと言うか一種の孤独感が漂うのである。
住宅街を歩いていると、出窓に座って外を眺めている猫の姿をしばしば見かけるし、自由に外を出歩いていた飼猫のトラーも、窓辺やベランダの手すりに座って、よその猫が自分のテリトリーへ侵入しないように見はるというのとは違う感じで、いわば物思わし気に、なんとなく外を見ていたものだった。
広重のこの絵は、そうした猫の姿そのものなのだ。猫の孤独とは、いわば、ペット化されてもしっかり保持している野生の思考というものに違いない。
それはそれとして、吉原の遊廓から浅草田圃を臨む浮世絵の風景を見て思い出したのは、志ん生の廓噺に使われる浅草田圃の蛙たちが、にぎわいに誘われて、そろって吉原へ素見(ひやかし)に出かけるという小噺である。二本足で立って素見をするのである。蛙なので人間の妓(おんな)の器量はわからないが、水に縁のある八ッ橋の柄の裲襠(しかけ)が気に入って、ずらっと出格子に並んだ中の一人の妓(おんな)の名前を楼(みせ)の若衆(わかいし)に訊くと、うちの花魁(おいらん)ではなくお向いの花魁だと無愛想に言われる。「蛙(かえる)だから、立ったんでね、目が後ろのほうへくっついていた、なんていう...」
そこでまた思い出したのが、河鍋暁斎の相撲をとる蛙たちを眺める美女の『美人観蛙戯図』(明治前半)と『蛙を捕まえる猫図』(明治21年頃。絹本墨画淡彩)である。トラ柄でしっ尾が長く、毛並もフサフサとして、気力の充実したオス猫特有の筋肉に力を入れて、ジャンプして逃げようとした瞬間の蛙を見定めて、素早い前足の一撃でし止めた、孤独とはまた別の、野生の姿そのものの猫の図である。それで今度は、石井桃子の『山のトムさん』の、ネズミ捕獲要員として飼われたはずのトムさんが、まだ若く未経験だった頃、農作業をする著者たちの後を追って田ンぼについてきて、自分の仕事を自覚せず、何匹ものカエルを遊びのように捕えるエピソードが語られるのを思い出した。
「猫じゃ猫じゃ展」のカタログには、大正15年(1926)に描かれた(註・2)高橋弘明の猫の二枚の魅力的な浮世絵が載っていて、一枚はお香箱を作った白猫の絵、そしてもう一枚は実をつけたトマトの枝の根元で、獲物に飛びかかろうとしている白地に赤トラ柄の猫の図である。暁斎のトラ猫のような類いの迫力には欠けるが、地面に半分伏せ気味に、柔軟な筋肉をしならせて、すぐさま獲物に飛びかかれる体勢で体をくねらせつつ音もたてずに静止している猫は、暁斎のすぐにでも化物に変身しそうでもある、虎図的な印象の絵より、はるかに家猫的野生が横溢しているではないか。高橋弘明のしっ尾も中途半端な寸法のブチ猫は、トマトの植えられた家庭菜園(だと思う)で何を狙っているのか、おそらく、小さなスズメとかトカゲといった生き物だろうが、スズメについては、今までも捕獲に何度も失敗しているのだけれど、懲りずにまた狙っている、という印象で、猫としては、トマトの草むらにすっかり自分の姿を隠しているつもりなのである。
野生をひそめた家猫の肖像として、まことにふさわしい絵ではあるまいか。
註・1 2003年8月号で「イギリスの歓び 美術でめぐる、とっておきの旅ガイド」と題した特集が組まれた。「変人たちの森 極私的ロンドン・ミュージアム回遊記」で"ポッター氏の珍宝館"などが紹介された。
註・2 「猫じゃ猫じゃ展」カタログでは大正15年(1926)の記載があるが、正しくは二枚あるうち「実をつけたトマトの枝の根元で、獲物に飛びかかろうとしている白地に赤トラ柄の猫」の絵の制作年については、カタログのミスプリントである。実際には画中文字より昭和6年(1931)の制作であると考えられる。(2016.1.26 訂正済み、註2加筆)

