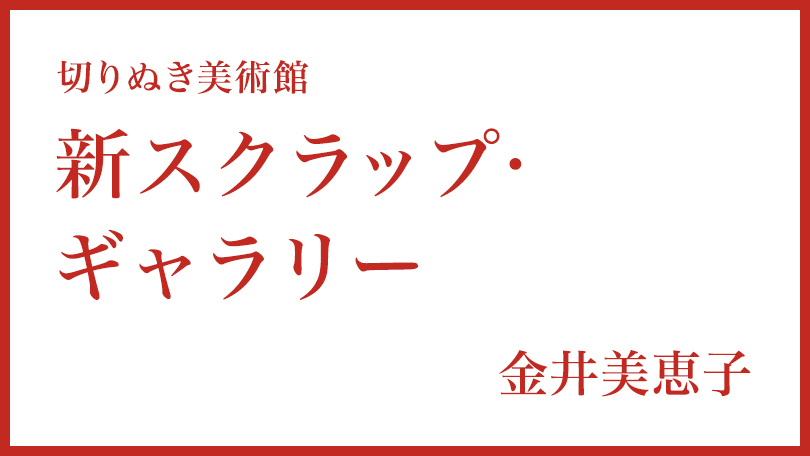
第4回
薔薇色の老人の自画像――ジャン・シメオン・シャルダン――
[ 更新 ] 2016.02.25

買い物帰りの女中 1739年 油彩、カンヴァス
前の回では家猫の孤独と野生について触れたのだから、今回はプルーストの描写する室内の猫を引用することにしよう。
芸術好きの貧しい若者が、昼食が終ったばかりで、まだ食卓の上が片付いていない食堂で腰をおろし、頭の中は「美術館や大聖堂や海や山々の輝かしい」イメージでいっぱいなのに、まくれあがったテーブル・クロスの上のなま焼けの味気ない背肉の食べ残しや、粗悪な出来のナイフが一本転がっている様子を「むかむかしうんざりしながら、吐気に近い感覚と憂鬱に隣りあった感情を覚えながら見」ているところをプルーストは設定する。
そうした耐え難い(若者にとって)情景の残酷さを、食器棚の上のわずかにさした陽を浴びている水の入ったグラスが皮肉にも「この美的ならざる情景の昔ながらの俗悪さを残酷に際立たせている」と、プルーストは書くのだが、執拗で繊細な描写に溺れるといった調子で、まだまだ続く俗悪な室内と若者の描写――読者はこの文章が「シャルダンとレンブラント」というタイトルであることを知っているので、室内の描写がシャルダンの何枚かの絵についての描写でもあることを想像できるわけだが――を決定づけるのが、にくにくしい猫だろう。
「部屋の奥」では母親が、席についてもうさっさと午後の仕事(「赤い毛糸のかせ」を巻くのだ)をはじめていて、その後ろにあるカップボードの上には、いざというときのためにとってある堅パンが置かれ、そのかたわらに「肥ってずんぐりとした猫がちょこなんと坐っているが、これは、家庭生活のこのような凡俗さを象徴する邪悪で何ひとつ立派なところのない精霊のようだ」(粟津則雄訳『プルースト全集』15巻)とまで酷評される猫は、たしかに、昨今の日本の「空前の猫ブーム」と言われて、テレビにもネットにもあふれかえっている映像というより動画の中に、猫自慢の鈍重な飼い主の顔を背後にダブらせて無数にいるのだけれど、それはそれとして、プルーストの書く食器棚の上に置かれた堅パンは、たいていの者が(むろん、私も)、シャルダンの絵として思い浮かべる良く知られた代表作「買物帰りの女中」の中で、今、まさにそこに置かれたといった様子の、どっしりとした存在感のある、あのパンだということがわかる。
いつどこで見たという記憶も定かではないのだが、学校の図書室にあった『世界名画全集』とか、泰西名画を印刷したカレンダーの中でだったかもしれない。それに、はじめてこの絵を見た時、描かれているのが大きなパンだと認識できたかどうかと言えば、もちろん、出来なかった。ああいった大きなパン・ド・カンパーニュが日本でも知られるようになったのは、1970年代であろうか?
「シャルダン展――静寂の巨匠」('12年9月から'13年1月 三菱一号館美術館)の図版カタログに載っているルーヴル美術館名誉総裁・館長ピエール・ローザンベールの論考によれば、忙しい家庭らしくちらかった印象の食堂で、二人の小さな子供に食前の祈りをとなえさせている若い母親を描いた「食前の祈り」の複製版画は、19世紀、「フランスのすべての田舎作りの家の壁を飾り、郵便局発行のカレンダーを彩った」そうである。シャルダンの絵は、その扱う主題の日常的な俗悪さによって大衆的に親しまれたわけである。20世紀、日本ではジャン・フランソワ・ミレーの「種まく人」が岩波書店のマークを飾りもしたが、褐色と黄色と灰色で描かれた暗い絵というミレーの「晩鐘」は、19世紀のフランスにおける田舎家の壁を飾ったシャルダンの人気と似ていたのだろう。けだし、宗教的な敬虔と親密な家庭的な静寂さ――。むろん、わかりやすく通俗的な――。
カタログに載っている「日本におけるシャルダン受容史」を読んでいて、決定的にショックを受けたのは(なにしろ、私はプルーストの、繊細な色彩と光の描写によって書かれた文章を読んで、静物画と自画像を見たいと思っていたので)、1971年に発表された消臭芳香剤「エアーシャルダン」と「ルームシャルダン」という商品名は、日曜画家だった社長がシャルダンの絵に心惹かれ「まだ一般的でなかった「香り」の新製品が普及するように、そして生活にやすらぎとうるおいをもたらすことができれば、という思いを込めて」命名したという記述であった。
もちろん、フランスの19世紀の田舎の家の壁を飾った郵便局のカレンダーや複製版画も、消臭芳香剤会社の社長の理念も同じ思いを込めて作られたのだろう。美術館の学芸員は「積極的な広告活動により、シャルダンの名称はテレビを中心としたマス・メディアを通して広く国内に流布した。」(安井裕雄)と書いているが、しかし、それをどれだけの人たちがあの画家のシャルダンと結びつけて考えただろうか?
この消臭芳香剤の商品名の由来を、思いもよらぬ場所で眼にして、まさしく鼻が思い出したのは、神田川に面したこの消臭芳香剤会社(防虫剤も作っている)の工場から界隈の住宅街に漂っていた、消臭し芳香を発する商品を製造するための化学薬品の強烈な臭いである。70年代の後半だったか、工場のすぐ近くに、プール付きでデパート系高級スーパーとレストランも一階に入っているバブリーなマンションが建ったのだが、姉と私は、防虫剤・消臭芳香剤付き高級マンションと呼んでいたのだった。もちろん、工場界隈の民家は防虫剤など一切使用する必要がなかっただろう。その後、いつの間にか(当然のことに)工場は移転したらしい。
前回に続いて、またフローベールの『紋切型辞典』を開いて、「工場」の項目を引用したい。「危険な隣家」
横道にそれてしまったようだが、シャルダンの絵は、というより、絵の中に描かれている物は、たしかに「猫」なのだ。カップボードの上を自分の居場所の一つと思っている肥ってずんぐりした(パン・ド・カンパーニュのような)、「家庭生活」の「凡俗さを象徴する邪悪で何ひとつ立派なところのない精霊のよう」なものとして「猫」を見るタイプの「芸術好きの若者」は、プルーストによれば、食事を終えて片づけていない食卓の乱雑さ以上に、自分を取り囲んでいるありふれた平凡な「部屋のなかのきちんと整った様子に苛々させられ」るのだそうで(もちろん自分で整えたのではなく、母親が無意識の習慣といった調子の手慣れたやり方で整理整頓するのだろう)、金持ちの趣味の良い芸術作品のように細やかなところまで美しく整えられた部屋を羨み、自分を取り巻く安っぽさにあふれた環境を嫌悪して、オランダだのイタリアだのに行けないのであれば、ルーヴル美術館に展示された「ヴェロネーゼ風の宮殿や、ヴァン・ダイク風の君主たちや、クロード・ロラン風の港などのヴィジョンを求めに行く」のだと言う。しかし、プルーストは若者を「フランス絵画の部屋に連れて行って、シャルダンの諸作品のまえで足をとどめさせる」のである。
静物画は、死んだ自然(ナチュール・モルト)と呼ばれるけれど、シャルダンの絵の中で事物は生きた自然となる。食卓の上に形よく積み上げられた天使の頬のような薔薇色の桃を黒い犬が頭をもたげて見上げている絵(『食卓』)について、「彼は眼でそれらを味わい、その甘美な味のために湿り気を帯びた桃の肌の和毛(にこげ)に蔽われた姿を見て、その味の甘美さを感じとる」と説明するのだが、私たちもこの犬の眼と、犬のヨダレになって桃を見つめるわけである。残念なことに「シャルダン展」にはこの絵も、大きな魚とカキと、いかに食い意地のはった猫が食卓の上をしめている不思議な『赤えい』も出品されていなかったのだった。
引用した文章の中で桃を眼で味わっている「彼」とは犬のことなのだが、それはシャルダン自身であり、絵を見ているプルースト、そして、私たちのことだ。
そして、湿り気を帯びた桃の肌の和毛(にこげ)に蔽われている様子は、おかしく聞えるかもしれないが、シャルダンが71歳の時に描いたパステルの自画像に重なるのだ。
24歳の青年だったプルーストには、仲の良かった祖母を通して「老年」というものに馴染みがあったとはいえ、自分のそれはまだまだ先のことだし、私たち読者は『見出された時』で登場人物たちのグロテスクな老いと話者の老い(ゲルマント夫人の午後のパーティで「つまり彼らは、私が彼らを見ていたように老人として私を見ていた...」とあるのは、なかでも一番遠慮した書き方である)の描写の容赦のない残酷さ(あまりのことに滑稽でさえある)を知ってもいるので、シャルダンのパステルで描かれた自画像を描写するプルーストの文章を読むと、プルーストが死んだ年齢よりずっと年を取っていて、シャルダンが自画像を描いた年に3年足りない私としては、井上究一郎訳の『見出された時』(1989年)を、あらためて、読みたくなる。しかし、その前にシャルダンの自画像について書かれた文章を読もう。
「そうさ、私も年をとったよ」と言っているように見える老画家の「くたびれたまぶたは、使い過ぎた留め金みたいに、縁の方が赤くなっている。身体を包んでいる古ぼけた服と同じように、彼の肌も硬くこわばって(中略)でもその布地と同じようにまだ薔薇色の色合いを保っている」のだが「だらしなく部屋着を着こみ、はやばやとナイト・キャップをかぶった姿のせいで、シャルダンはまるで年とった女のよう」だと、プルーストは書いている。それで、私としては、ある顔を思い出したのだった......(この項つづく)

