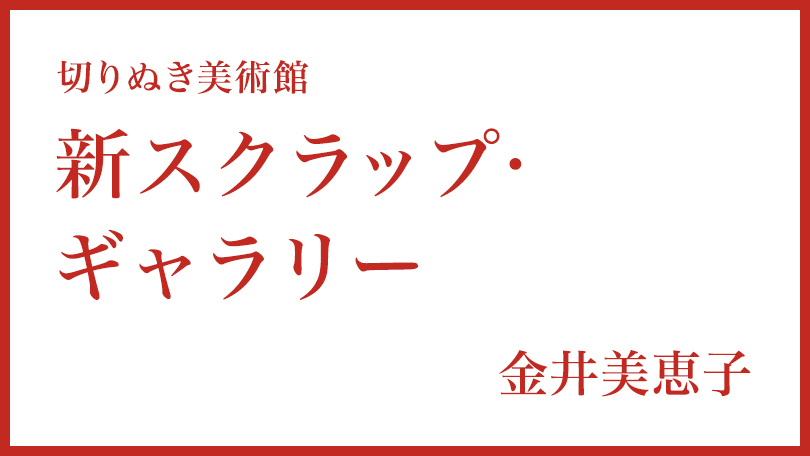
第5回
年齢と果実
[ 更新 ] 2016.03.25
木いちごの籠 1760年頃 油彩、カンヴァス
あれは何をどこで読んだのか、多分、インタビューの中でだったはずだが、それ程前のことではないことは確かなのに思い出せないのは、もちろん、老化現象である。
シャルダンの「鼻眼鏡をかけた自画像」を見て、私が思い出す顔というのは、一つはミッシェル・ピッコリのことだ。シャルダンは自画像の中で頭に被っている薄い水色なのか白なのか、麻布のナイト・キャップをブルーの絹のリボンできっちりと頭に巻きつけ、首には、たるんだ頬のあたりに残っている薔薇色と同じに少し色が褪せた薔薇色のスカーフを結んでカーキ色の部屋着を着ているのだが、それは、プルーストの書くように「年をとった女のよう」に見える。
まるで、この鼻眼鏡をかけた老女の描かれていない腕の先には、膝の上に編みかけの編物(もちろん、赤い毛糸の)が置かれているように見えるのだが、映画俳優のミッシェル・ピッコリは、年を取ってからのことなのだが、仕事上の必要で老女に扮装した時、鏡の中に自分の祖母がいるのを発見したと言うのである。年齢というものは、人にそれがまだ数年から十年くらいまでの間と、数十年以上たった場合とで同じ働きを見せるようだ。
すなわち、人を中性化と言うか女性化するのである。ベビー服に青色と薔薇色で男女の区別をつけるのは、もちろん、見た眼に赤ン坊には、男女差がないからだし、十歳くらいまでの子供も、見た目の性差はまだほとんどないし、年齢を重ねると、おばあさんのようになる男や、おじいさんのようになる女がいて、見た目の性差は、再び曖昧になってしまうのだ。
老年のシャルダンの自画像を見て、思い出すもう一つの顔は、ロラン・バルトである。『彼自身によるロラン・バルト』には何枚もの、家族アルバムに張られていたモノクロ写真が載っている。その中の一枚は、楕円形の鏡形にくり抜かれた、赤ン坊を抱いた若い母親が、赤ン坊ともどもカメラを見ているので、戯れに付けられたコメント〈鏡像段階。「お前が、これだよ」〉がぴったりだし、バルトの母親はこの写真を幼いバルトに見せて、「お前が、これだよ」と言ったのに違いないのだが、見開きページの右側、中年になったバルト、いや、ロランが年老いた母親と一緒にお茶の時間を過している写真の二人と若い母親の三人はそっくりなのだ。次のページには、幼年時代の二枚の写真が載っていて、一枚は編上げ靴にプリーツのスカート(20世紀初頭まで、男の子が早死せずに丈夫に育つように女の子として育てるという風習が世界各地であった。幼年時代ヴィスコンティの写真もスカートをはいているし、ジャン・ルノワール、サルトルも自伝に幼い時の長いカールした女の子のような髪について書いているし、ケストナーも自伝の中で、幼い頃の写真に触れ、長い髪でセーラー服のスカートをはいていたと書いている)、襟付きのセーターでお河童頭のロランである。「同時代人?」というタイトル、写真に付されたコメントには「私は歩きはじめていた。プルーストはまだ生きていて、『失われた時』を仕上げようとしていた。」とあり、バルトは1915年生れで、プルーストは1922年に死ぬのだから、この頃『見出された時』は、どのあたりが書かれていたのか。お茶の写真の手前には、手描きの図柄のある陶器のボウルには洋ナシかリンゴのような果実が入っている。この写真の上には庭でお茶を楽しむまだ中年の祖父と祖母の写真が載っているが、ロランは祖父ではなく祖母にそっくりだ。
ところで、バタイユは『文学と悪』(山本功訳)のプルースト論の中で『ソドムとゴモラ』の一節を引用している。「息子たちは、かならずしも父親に似ているとはかぎらないので(たとえ彼等が倒錯者ではなく、女の尻をおいまわす男だとしても)すでにその容貌において、母親をけがしていることになる」という部分である。プルーストももちろん母親に似た、女性的容貌を持っていたのだ。
配膳室のテーブル 1756年 油彩、カンヴァス
さて、ピントをどこに合わせようとしたのかよくわからない素人の撮ったスナップ写真の陶器のボウルに入った果実をきっかけに、やっとシャルダンの方に戻ることが出来そうだ。
静物画というものは、もともと、宗教的・呪術的な行為として豊饒を祝い願う物として、神に供えられた、狩の獲物や漁でとれた魚介、果実や花や穀物といった季節の物を、いつでも供えることの出来る代替物として生じたものと言っていいだろう。李朝民画の文房具図の一部に描かれた果物や花は先祖の霊への供物だろうし、ボデコンと呼ばれるスペインの静物画があり、生花の豪華ではなやかな山盛りの様式を現わす「スティル・オランダ」という言葉は、もちろん17世紀のオランダの装飾的静物画に由来している。
職人的な達者な、良く訓練された技術で、花弁の上や果物の生毛のはえた表皮の上の水滴が描かれていたり、透明なガラスのグラスやビンやウロコが銀色に輝くお刺身にもってこいのいきのよさそうな魚が、二つ切りにしたみずみずしいレモンと一緒に描かれているものだから、展覧会場には、美術愛好家なのかそれとも単なるヒマつぶしなのか、それとも少しボケているのか、いわゆるおやじが大きな声(ひとり言である)で、凄いなあ、まるで写真みたいだよ、本物みたいだ、と感嘆の声をあげる「静物画」というものが、西洋には無数にある。シャルダンの絵とは似て非なる、紫色と薄緑色の陰気なブドウや、桃色の部分よりクリーム色の部分が多い、全然食欲をそそらない固そうな桃といった、まさしく〝死んだ自然(ナチュール・モルト)〟は、風景画(フローベールの『紋切型辞典』では「つねに『ほうれん草料理』」)と同じように、かならずしもプロによってではなく、アマチュア画家によっても大量生産されたはずである。油でいためて時間がたち褐色に変色したほうれん草料理のように、褐色がかった日本の風景画の油絵(洲之内徹コレクションにことの他多い気がする)というのも無数にあって、見る者をなんとも陰気な気分にさせる点で似ている。
本物そっくりに描かれているので、ある種の人間を感心させる死んだ自然系の静物画とは対極のところに、シャルダンの静物画が、鮮やかとは呼べないが、台所の一偶のテーブルの上でつつましい豊かさで柔らかな光を発しているのは、なぜだろうか。18世紀の同時代人百科全書派のドニ・ディドロは、シャルダンを「偉大なる魔術師」と呼ぶのだし、20世紀の美術史家エリー・フォール(ゴダールの『気狂いピエロ』で、ジャン=ポール・ベルモンドが、お風呂に入ってフォールの『美術史』を読んでいた)は「彼はワトーとともに、宗教なきこの世紀にあって、唯一の宗教画家である。」と書き、プルーストはシャルダンの絵について、その絵の細部を言葉を繊細に選びぬいて描写し、批評するとか論じるというより、作品としての文章の中に光のように溶け込ませてしまいたいという欲望によって書いているようなのだ。
もちろん、私にはシャルダンの絵について語る言葉がない。ただ、シャルダンの絵から思い出される言葉を引用するのみである。そう言うわけなので、最後にフランシス・ポンジュの果実の詩を引用することにしよう。
シャルダンは南の地方で採れるオレンジの絵を描いてはいないのだが、しかし両者はともに物の味方であった。オレンジの中身を覆っている「皮」について、ポンジュは次のように書く。
(...)この湿った厚い台付吸取紙に包まれた、柔かくて脆(もろ)くて薔
薇色をした卵形の球体の外皮に対していだかずにはいられない感嘆の念を
告白しようにも言葉が出ぬままにいるわけだが、この吸取紙の、極度に薄
いが大量に色素を含んで、苦い風味をもった表皮は、果実の完璧な形の上
に、ふさわしく光を捕捉するのにちょうど必要なだけの、凹凸をもってい
る。
(「オレンジ」阿部良雄訳)

