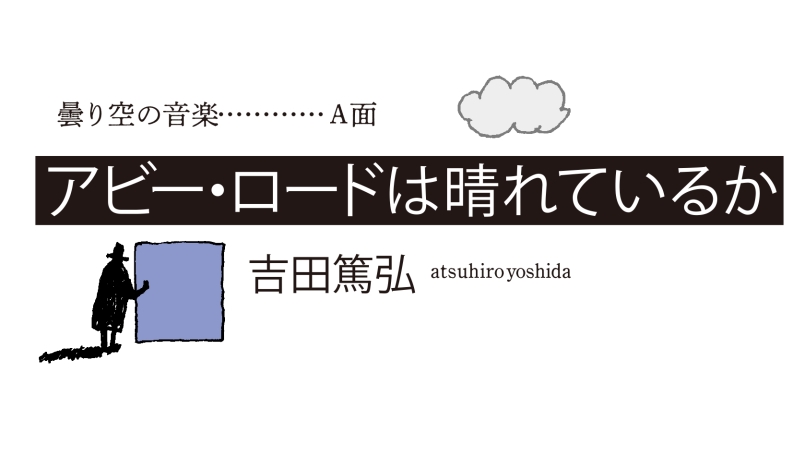
第6回
快いノイズ
[ 更新 ] 2020.04.22
この「プツリ」であるとか、「ポツリ」「パチリ」といったパ行のノイズは、それほど大きな音でなければ心地よく感じられるときがある。これはおそらく、自分のフェチシズムと関わりがあり、それが微細なものであればあるほど、「プチ」「パチ」といったノイズが快く響いたりする。
最初に気づいたのは映画館においてだった。七歳のときだ。怪獣や怪物が夜の都会を破壊していく特撮映画を固唾を呑んで観ていたとき、破壊のあとの深夜の静かな場面で、効果音やセリフではなく、「プチ」「パチ」と小さな音が画面から聞こえてきた。耳にまとわりついた、と云った方がいいかもしれない。大人になってから、それがフィルム自体が発するノイズだと知ったが、耳の中をかすかな刺激でくすぐられて、ともすれば、背筋がぞくりとなった。
快さをもたらすので、それらのノイズがそもそも何であるのか見失いがちになる。レコード盤や映画のフィルムに生じるノイズのもとはおおむね「傷」であり、それらが傷を負ってしまうのは、いずれも、やわらかいからではないかとすでに書いた。
やわらかい複製品である。
このやわらかい複製品は個々のコピーの微妙な差異や特徴といったものを、もともと、そこになかった情報──傷である──を引き受けることで独自に変化していく。
たとえば、ぼくのレコード棚には聴かなくなったレコードや聴けなくなったレコードを集めた一角があり、そのうちの何枚かは、あまりに傷がひどくて、再生不可能になってしまったものもある。
「ゴールデン・ピクニックス/四人囃子」はその顕著な例で、このアルバムは長年の愛聴盤なのだが、最初に買った盤──リリース当時の1976年に購入した個体は、B面にグロテスクなほどすさまじい傷が刻まれている。まともにプレイすることができない。
どうしてそんなことになってしまったかと云うと、そのころ、一緒に暮らしていた白い雄猫が、あろうことか、回転しているターン・テーブルに興味を抱き、再生中にレコード盤に飛び乗るという暴挙に出たからだった。瞬時にして針はとび、猫は33と3分の1回転でまわりながら、四本の脚のすべての爪あとを盤に刻み付けた。
あるいは、AP-8163という型番を持ったビートルズの「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」のA面の5曲目──「Fixing A Hole」のイントロで、パ行より強烈なバ行の「ボン」という破裂音がして、そこから先へ針が進まなくなる。延々と同じ音溝を繰り返しループしつづける。
この傷はかなり目立ち、盤の表面に穴ができてしまったかのような深さを持っている。穴を修繕する歌である「Fixing A Hole」に、よりにもよって深い穴が穿たれてしまったことに苦笑するしかない。これは自分がターン・テーブルに右ひじをぶつけて、著しい振動を与えたためにできた傷だった。何度もループしてしまうイントロを聴くたび、そのときの自分の挙動がよみがえる。
傷というのはおかしなもので、レコードではなく、自分自身の体に負った傷を振り返ってみても、かなり小さな指先の傷をはじめ、顎や脛や腿や肩などに負った、どうということもない傷の記憶をいちいち覚えている。
痛みの記憶はとうに消えている。ただ、自分のやわらかい部分に負った傷のあとが肌に刻まれていまもあり、目にするたび、刻まれたときの様子がただちに再生される。
それは、やわらかいビニール盤に溝を刻むことで、「刻んだときの情報」が正確に再生されるレコードに似ている。
そう考えると、傷によって生じたレコードのノイズは、その個体にのみ付け加えられたもの──レコードがターン・テーブルの上で回転してきた数々の時間の記録でもあるのだと思い至る。
シンプルな言葉で云いなおせば、傷によって生じるノイズは、人や人にまつわる何ごとかの痕跡なのだ。
面白いのは、音楽もノイズも同じひとつの盤に刻まれているということで、傷によって音楽は多少なりとも変容し、大量生産の同一品であったものに、ノイズが個性を加えていく。
さらに飛躍して云えば、複製芸術とは、これすべて美しく刻まれた傷のことにほかならない。
この場合の「美しく」は多分に主観的だが、何ごともなかったプレーンな素材に人が施したものは、どんなものであれ、傷と呼ばれてしかるべきだろう。
もともと、そこには何もなかったのだから──。
何もなかったやわらかいものに、人は傷を刻んで、美しく快い痕跡をのこした。それがレコードだ。
であるなら、ノイズとは一体なんだろう。
すべてはノイズではないのか、という思いも立ち上がってくる。
ましてや、この言葉を日本語にひるがえした「雑音」という二文字の乱暴さは、事態を間違った方へ導きかねない。
ノイズは「雑な音」ではない。むしろ、意図や思惑にとらわれていない純粋なアクシデント=出来事の痕跡である。
ただ、こうしたノイズに心地よさを覚えるのは、前述したとおり、ぼく個人のフェチの表れなのだろうか──。
学術用語としてのFetishismは、霊的なものや魔力を宿したものへの特殊な感受および崇拝を意味している。そこには、理屈や道理がない。自分にとってノイズは、そうした道理を超えたもので、しかし、レコードやフィルムの傷はあきらかに目で見ることができる。「霊」や「魔」といった、目に見えないものとの親和性が感じられない。
まさか、レコードの傷を聖痕などと呼ぶわけにもいかず──。
が、ノイズが、あらかじめ刻まれたもののトレースによるものではなく、いままさにライブな現象として発生していたとすれば、途端に超常的な印象が際立ってくる。
身近な例で云えば、ラジオの電波を受信機でとらえようとしたときに生じるノイズだ。これは、やわらかいものに刻まれた傷が発するノイズとは違い、突発的で、流動的かつ即興的である。
物が傷を帯びるのではなく、いわば、電波が伝わってくる空間の一部が目に見えない何ものか──それらの多くは電磁波である──によってダメージを受ける。ビニールの材質に根ざしたパ行やバ行のノイズではなく、「ジジジ」「ガガガ」というザ行とガ行が入り混じった、どこかつぶやきにも似たノイズをランダムに発生させる。
はたして、オン・エアの「エア」がどのように損われているのか想像もつかないが、これがラジオではなくテレビ放送のオン・エアを損なうノイズとなれば、「ゴースト」と呼ばれるものを呼び寄せることがある。
ゴースト──すなわち目に見えない怪物である。
電波の送り手と受け手のあいだにゴーストがよぎり、よぎったときのそのふるまいによって、「ジジジ」なのか「ガガガ」なのか、ノイズの強弱がうつろう。
そうした予測のできない、うつろうような刺激こそが官能の正体で、官能の先にあるのは、およそ快楽だろうが、わずかながらでも、恐怖や畏怖といったものに傾けば、「霊」や「魔」の領域に参入することもある。
ノイズはそうした秘密めいた領域との交感を含む、きわめて原始的なものであるのかもしれない。
*
いずれにせよ、レコードにノイズはつきもので、そうなると、ノイズなしで音楽を聴きたいという欲求が当然ながら生まれてくる。これに応えたのがテープによる音楽ソフトで、まずはオープン・リールでリリースされ、それから、カセット・テープにレコードと同じ音源を収録して発売されるようになった。
オープン・リール・テープは音の良さに定評があったものの、音の良いプレイヤーは高価であるだけでなく、結構な大きさと重さがあった。そこへいくと、カセット・デッキはじつにコンパクトで持ち運びやすく、テープも格段に小さくなって、もちろん、ビニールを針でトレースするノイズもなかった。
ただし、カセットの再生には、ヒス・ノイズというまた別のノイズが発生し、パ行でもザ行でもなく、「サー」「スー」というサ行のノイズが、テープが回っているあいだ、バック・グラウンドにうっすらとのっていた。ひどいものになると、曇りガラスごしに音楽を聴いているような気分になった。
結局のところ、われわれがソフトとして手に入れる音楽、映画、本といったものは、当たり前の話だが、オリジナルのコピーでしかない。この「コピー」という概念が、カセットの普及によって世に浸透し、ノイズレスな再生機としての側面だけではなく、リスナーが手軽に複製品をつくれるコピー・マシンとしてもてはやされた。
われわれはカセットを通して、音源をコピーするとはどういうことか体感した。たとえば、レコードからカセットへコピーし、さらにそれをダビングして別のテープへコピーすると、コピーをするたび、ヒス・ノイズも倍増して音質が劣化することを学んだ。ノイズはコピーの副産物なのだと理解したのである。
それはやがて、デジタルの時代を迎えて、一新されることになるのだが、その前夜と云っていい1980年代の半ば過ぎに、忘れがたい象徴的なことがあった。
ある日、六本木にあった大型レコード店〈WAVE〉の店頭に、いわゆる「レア盤」と呼ばれているレコード──その中でも「ROCK」にカテゴライズされているもの──が突然、数十点並べられていた。中古盤ではなく入荷したての新品で、いずれもオリジナルは1960年代の後半から1970年代の前半に発売されたものであったから、もし、それらがオリジナルのデッド・ストックであれば、それなりの値段で取引されただろう。
「Gracious」「Asylum/Cressida」「Garden Of Jane Delawney/Trees」「Freak Out!/Frank Zappa & The Mothers Of Invention」「Raw Material」「Spring」「Three Parts To My Soul/Dr. Z」「Swaddling Songs/Mellow Candle」「Ben」「Growers Of Mushroom/Leaf Hound」「Volume One/The Human Beast」──等々。
一枚3800円から4500円で、いずれも、わずか数枚ずつの限定入荷という触れ込みだった。そのころ〈WAVE〉で輸入盤の新譜を買うとなると、LPレコードは一枚2200円から2500円くらいが相場だったので、その価格は特別である。
いまはもう、これらの音源の大半はネット上で水を飲むように聴けるのだが、その当時──指折り数えてみると、およそ三十年前である──は、どのアイテムも簡単に聴けるものではなかった。
そのときの心の叫びを覚えている。
(全部、聴きたい!)
しかし、金銭的な事情から、買えるのは一枚だけで、小一時間、悩んで、どうにか一枚に絞り込んだ。
Moby Grapeの「WOW」だった。
そのころはジャズばかり聴いていたので、60年代のロックにはまるで詳しくなかった。いま思うと、かなりレアなアイテムが並んでいたのに、どうしてMoby Grapeだったんだろうと訝しむが、Moby Grapeがどんなバンドか知らなかったし、単純にジャケット・デザインに惹かれたのだと思う。
その一枚を胸に抱えて地下鉄に乗り、買えなかった他のレコードに思いを馳せながら、幻を手に入れた気分で家路をたどった。情報が少ないということ──いや、少ないどころか、皆無であるということは、この世に数々の幻をつくりあげてしまうのだ。
自分の部屋に帰り着き、部屋の照明を暗くすると、着ていたコートを脱ぐのももどかしく、息をつめて幻に針を落とした。
さて、そのレコードから出てきた音はどんなものであったか。
記憶は二通りある。レコード盤から薄紫色の煙が立ちのぼるような、またとない音楽体験をした──。
もしくは、もはや音楽がどうのこうのではなく、あまりにノイズがひどくて、まともに聴く気になれなかった──。
正解はたぶん後者で、このレコードはすでに売り払って、いまは手もとにない。手もとに置いておきたくなかったくらい、ノイズが耐え難かったのである。
そういえば、この際、しっかり書いておきたいが、レコードというのは入荷したての新品を買ってきても──つまり、一度も針を落としていないまっさらな盤であっても──「パチ」「プチ」「ポツ」と、パ行のノイズに見舞われるのがざらだった。ビニールの質が悪かったり、プレス作業の工程がずさんであったりすると、新品でもノイズが盛大に出た。
稀に一瞬の「パチ」すらない良質なレコードに出会うこともあったが、そんな優秀な盤であっても、ヘッドフォンで仔細に確かめると、やはり、なんらかのノイズが聴きとれた。
そんなわけなので、買ってきたばかりのレコードがノイズをたてることには慣れていたのだが、このときの「WOW」は、ノイズが二重になって聴こえ、ノイズのあるレコードをノイズまじりのスピーカーで聴いているようだった。
(そうか)と気がついた。(これは、コピー盤ではないか)
カウンターフィット盤と呼ばれているもので、何から何まで本物そっくりにコピーしてつくられた海賊盤である。そう思って、あらためてジャケットを見ると、もうひとつ印刷がぼやけていて、紙質も安っぽく、すぐに破れや折れができてしまいそうだった。
結論から云うと、このとき店頭に並んでいた数十枚の「レア盤」はすべてカウンターフィット盤であり、ジャケットも音源もオリジナル盤をコピーしてつくられたものだと、あとになって知った。
前述したとおり、そのノイズまみれの「WOW」は手放してしまったのだが、つい最近、とある中古レコード屋で、どことなくつくりがチープなRoger Nichols & The Small Circle Of Friendsのファースト・アルバムを見つけた。これがどうも、あのときの数十枚のうちのひとつと思われ、コピー盤であると分かっていたけれど、三十年ぶりの再会に嬉しくなって、つい買ってしまった。よくよく隅々まで点検してみると、感心してしまうほど忠実にコピーされている。たぶん、「WOW」のような、いかにも劣化したコピー盤があったり、かと思うと、コピーであるとほとんど気づかないような、よくできた盤が混在していたのだろう。
このRoger Nicholsのカウンターフィット盤は目立ったノイズがほとんどなく、コピー元となったオリジナル盤の状態がすこぶる良かったに違いない。それにくらべて、「WOW」はノイズの向こうにどうにか音楽を確認できるというもので、さすがにそうなると、ノイズが隠し持っている色気のようなものは微塵も感じられなかった。
(ああ、もっときれいな音で聴けないものか──)
ノイズに快さを覚えていたのに、その一方で、ノイズのまったくない無菌室のクリーンさに心ひかれるところもあった。そういう時代だったのだ。デジタル的な考えによってつくられたものに少しずつ包囲され、店や街といった環境からしてクリーンなイメージに向かっていた。
しかし、ここには稚拙なトリックが介在していたように思う。一見、デジタルへの転向はクリーンなバージョン・アップとして映ったが、デジタル化していく現場でデザインの仕事をしていた経験からすると、「デジタル時代」などと云っても、最初は原始時代でしかなかった。用意されているツールはごく限られていて、アナログの成熟期を通過してきた者の目には、あらかた稚拙で大味だった。大味な道具では緻密なものや、微妙なニュアンスを孕んだ「うつろうような刺激」などつくれるはずがない。大味な道具には大味なものしかつくれないので、フラットであることを強調するしかなく、仕方なく、「余計なものを取り払うこと」に価値を見出していた。汚れ、かすれ、にじみ、といったノイズの側にあるものは強制的に消去され、というか、原始時代のデジタルはノイズを除去することがなにより得意だった。そこには当然ながら、「霊」も「魔」もゴーストも介在していない。
これはあくまでも原始時代の話なので、いまはまったく事情が違っている。その違い方も興味深く、フラットで大味な地平から始まったデジタルの風合いは、世の中の変動もあったろうが、いつからか、汚れ、かすれ、にじみといったアナログなノイズを再現するツールを開発するようになった。自らが切り捨てたものを、自らが取り戻すことになったのである。
ようやく気づいたのだろう。
どうあがいてもロボットになどなれず、どこまで進化しても、「霊」と「魔」とゴーストと共存せざるを得ないのがヒトである。そんなヒトにとって快いものとは何か、何が快さをもたらすのか、大味の味気なさに辟易して気づいたのだ。
けれども、1986年の東京でレコードを買っていたぼくは、
(もっときれいな音で音楽を聴けないものか)
と切実に思っていた。「きれいな音」とは、完全にノイズが除去されたクリーンな音という意味である。
21世紀に生まれた人たちは想像してほしい。配信はもちろん、CDすら存在しなかった時代、音楽を聴くことはノイズを聴くことでもあった。ノイズのない音楽を聴く術がなかった。いまとなっては信じられないけれど。
とりわけ愛聴していた昔のレコードは、中古レコード屋で何度も買いなおして、よりノイズの少ない盤を探しもとめた。
(ああ、もっときれいな音で)
と常に願っていたのだ。
そういうところへコンパクト・ディスクなるものがあらわれた。正確に云うと、CDの存在自体は1984年くらいから少しずつ知れ渡っていて、レコード・ショップの隅の小さな一角にひっそりと並べられていた。どういうものかは知ってはいたけれど、買ってみたいとは思わなかった。なによりプレイヤーを持っていなかったし──まだ高価だった──ソフトの数があまりにも少なかった。
様子が一変したのは、1986年くらいからだ。ぼくはそのころ職場が六本木にあったので、仕事が終わると、〈WAVE〉に立ち寄って、ジャズとロックのコーナーでレコードをチェックするのを日課にしていた。ほぼ毎日、新入荷があり、店内は隅から隅までレコードであふれ返って、毎日チェックしても追いつかないほどだった。
そうした中、ほんの小さな一角だったCDコーナーが少しずつ拡張し出し、にぎやかなポップが立ち始めて、「ふうん」と横目で眺めるようになった。日本製のCDだけではなく、輸入盤のめずらしそうなCDが目にとまるようになり、「ふうん」はそのうち「ほう」となって、やがて横目ではなく目を剝いて、「ややっ」となった。ついに手にとって見るようになり、そのあたりから、毎日のように売場に変動があった。毎日、通っていたので、その変化は面白いくらいで──いや、怖いくらいだった、と書いた方が、そのときの実感に近い。
何やら目に見えない力が、毎日通っていたレコード売場に忍び寄ってきて、少しずつではあるけれど、あきらかに目に見える変化をともなって波及していった。それまでの日常が圧倒的な力によって改変されて違うものになっていく。
何にたとえたらいいだろう。
ドミノ倒しだろうか。
いや、オセロ・ゲームでたったひとつ置いた石が、みるみる相手の石を裏返していくような、そういうスピードでレコード売場がCD売場に侵食されていった。もう誰にもとめられないという感じで、ぼく自身もその場に立ち尽くすというより、そのあたらしいメディアの襲来を次第に楽しむようになっていた。
かくして、CDはレコードに取って代わった。
なぜなら、先に挙げた、聴きたいけれど聴けなかった60年代、70年代のめずらしい音源が、かなり早い段階でCD化されて、続々、市場に出てきたからである。
このことも特筆しておいた方がいいかもしれない。
どうして、レコード派があっさりとCD派に転向したかというと、(もっときれいな音で聴けないものか)という希求にこたえてくれただけではなく、なかなか聴けなかったものを提供してくれたからである。
しいて云えば、30センチ四方のジャケットが12センチにまで縮小されてしまったことが残念だったが、いや、これはこれで可愛いじゃないか、と日本人のミニチュア嗜好症が発動されて、これもまたレコード派の反感を買うまでには至らなかった。
で、肝心の音はどうであったか、である。
一応、「よかった」と、まずはそう云っていいのだろうけれど、実際のところは千差万別で、すべてのCDがノイズを除去できたわけではなかった。CD化に際して使われたマスターがアナログであれば、やはりヒス・ノイズがあったし、なにより驚いたのは、マスター・テープが発見できなかった音源は、レコード盤から起こして、針音もそのままにCD化されていたことだった。CDなのに、針がトレースしている音が──場合によっては例のパ行のノイズがそのまま含まれていた。
*
これはCDの黎明期ではなく最近のことであるけれど、1950年代にアメリカでつくられたとあるレコードがCD化されることになり、
「ついては、レコードを貸していただけませんか」
とレコード会社から連絡があった。たまたま、状態のよい盤をぼくが持っていて、レコード会社がリサーチをして──どうして、ぼくが持っていると分かったのかはここには書かないけれど──協力してほしい、とのことだった。
「どういうことでしょうか」
と訊いてみると、そのレコードのマスター・テープを探しているところなのだけれど、もしかすると見つからないかもしれない。あるいは、見つかってもテープが劣化して使いものにならないかもしれない。その際に、あなたの持っている状態のよいレコードから音を起こしてマスターの代わりにしたいのです──という説明だった。
「分かりました」とぼくはレコードを提供し、半年ほどすると、貸し出したレコードと一緒にCD化された商品が送られてきた。
さて、マスター・テープは無事に発見されたのか、それとも、見つからなくて、ぼくのレコードが代わりに使われたのか──。
「見つかったのですか」とメールで訊いてみたところ、
「申し訳ありません。見つかったか、見つからなかったかは、お教えできないのです」という返答だった。なるほど、黎明期には盤起こしのCDも致し方なかったろうが、昨今は、「オリジナル・マスター・テープよりCD化」と謳われていたりするので、「見つかりませんでした」と明言することはできないのだろう。
いや、そうではなく、たぶん見つかったのでしょう。ええ。そういうことにしておきます。
ちなみに、いまはCD化の技術が格段に向上しているので、たとえ針音のするレコード盤から起こしたとしても、CDになったものは、まったくのノイズレスに化けてしまったりする。
件のCDも、無論のこと、ノイズはまったく聴こえなかった。

