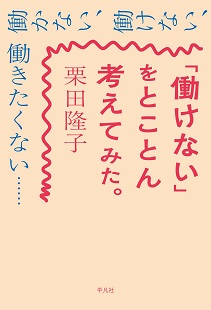第1回
……時代が私に追いついてきてしまったのか?
[ 更新 ] 2022.10.26
うーん、どれもしっくりきそうでこない。
こんなふうに書き出したそのわけはと言えば。
「働かない/働けない」というテーマで、しかも「働かない/働けない 女性 (独身女性)」の視点から書いてほしいという原稿依頼が、運動団体や同人誌からではなく、商業媒体の出版社から届いたからだ。
私は1973年生まれ。就職難であったことから氷河期世代、ロスジェネ世代とも呼ばれるが、それ以前からは団塊Jr.世代とも呼ばれていた(それにしてもこのジュニアという言葉にも女性の存在が感じられない)。この時代の家族形態は核家族が最も多く、結婚している女性の中の専業主婦率も1980年までは増加していた(注1)。それゆえ幼稚園に入ることですらすでに競争だった。私は幼稚園にも落ちたと親から聞かされた。
1980年代。80年代後半はバブルの時代を迎えるが、電電公社や国鉄は民営化、総評は解体。男女雇用機会均等法が出来るとほぼ同時期に派遣法と第3号保険制度(いわゆる第二号保険者の被扶養者になれば年金を支払わなくても年金が受給できる制度)が生まれた。私は小・中学校時代も落ちこぼれでいじめられっ子でもあった。
1990年代。バブルの崩壊、阪神・淡路大震災とオウム真理教の事件が世間を賑わす。私自身はその頃とっくに「カトリック教会」という規模がデカすぎるゆえにカナダの寄宿学校でジェノサイドを起こしてもカルトと呼ばれない宗教を信じていた。オウム真理教の若者(と言ってもこの「若者」世代は私よりも一回り上の世代だった)と違うのは、私がオーソドックスな宗教を選んだか、そうじゃないかであっただけに過ぎないのではとうっすら思った。「ロスジェネ」などという言葉はかけらも存在していなかったが、それでも「企業に50社以上面接した」「女子はやっぱりなかなか通らない」という現実は身近だった。しかもその当時は私の卒業した地方国立大学の女子学生よりも私立4大卒の女性の方により打撃が大きかった。私は大学院に進んだ。今思えばそこで新卒という切り札を失ったわけだが、私自身はそもそも不登校を経験しており、多くの人ができる「普通」のことが自分には無理、という経験を経ていたのに加え、もともと体力も気力もある方ではなかったため新卒でフルタイム、残業も厭わず働き続けられるような人間とは思えなかった。ゆえに、この「新卒」の切り札が初手からなかったことを後悔してはいない。そうして私は2000年代以降の就職活動の結果、正社員として雇用されることに順調に失敗する。
職場の人間関係に耐えきれず自主退職に追い込まれ、あるいは有期契約だからと雇い止めに遭って働けない。健康上の問題から、またはそれらが複合的に重なっていく状況に耐えかねて働けなくなる。そんなあれこれの経験が部屋の隅の目に見えぬ埃のように心身に重く積み重なっていった。そうして働く意欲があるのかないのか、もはや定かではなく、自分でも働けないのか、働かないのかわからなくなる……。私自身は2015年にうつとなり、とりわけコロナ禍以降は賃労働のもとでの労働者として働くことが難しくなった。しかしそのような女性は今や首都圏その他都市部では珍しくないように感じる。
すでに10年以上前から女性の未婚率、そして非正規労働者でかつ世帯主、そして主な稼ぎ手でもある女性は増えていたけれど、それでも10年前だったらこんな企画は通らなかった。楽屋裏的な話で恐縮だが、私の本を出そうという話がかつて出かかったが、結局は企画会議で弾かれたこともある。
バブル期に新卒で入ってきた世代が定年に近い年齢となり、いわゆるロスジェネ世代がバトンタッチで職場の権限を握り、さらに一定数女性が入ってきたことで若干状況が変わったのかもしれない。少なくともロスジェネ世代……私より年下のケースがほとんど……の編集者は、私の状態を他人事と思えないと口を揃えて語る。休職したり、うつで倒れた同僚などの話をしてくれる場合もある。「自分はなんとかなったけれど自分と同世代の知り合いは今どうしているか……」と複雑な面持ちで話しかけてきた編集者もいる。いわゆる正規労働者と非正規労働者は今なお「身分」のように固定化されており、非正規労働者から正規労働者に移動するのは極めて困難である。10年以上前から変わらない。だがそんな時代が長年続いてきたことにより、以前だったら伝えるのに困難な賃労働への私の醒めた感覚は少数派ではなくなったのかもしれない。私たちの世代が会社の中で少ないことでITの導入などさまざまなところで苦労している話も聞く。企業の自業自得としか思えないが、そんな際の皺寄せは私たちを雇用の門前で足蹴にした責任者ではなく、若い社員にいっているのだろう。
そもそも恒常的に賃労働をしている状態が、普通の人にとってかつては空気を吸うように当たり前だった。でも最近問われるのはそもそもこの「普通」とは何かということだ。
実はこの「普通」。「普通」などという言葉で覆い隠されているものの、実は日本に住む日本人、日本語話者、健常者、異性愛者でシス男性、さらには首都圏出身などなどといった「マジョリティの詰め合わせ」みたいな存在だったことが明らかになっている。
総務省統計局が標準世帯モデルというものを公表しているが、その定義はいまだに夫婦のうち一方が第二号年金で子供は二人である(注2)。それらはたとえば年金の計算などにおいて標準的な年金(モデル年金)として、被用者について標準的な被保険者像を想定し、その被保険者が世帯として得られる年金を示したものであり、年金水準を設定したり、制度的に保障される年金の姿を端的に示す際に標準として用いられる概念である。実質夫である男性がサラリーマンで妻である女性が専業主婦という組み合わせ、労働者がそんなの全然普通でも一般でもないじゃないかということに気づき始めたのだ。そういう「 普通」のからくりが明らかになり、バブル崩壊以後、不景気と好景気を繰り返していたはずなのに、結局のところ労働者の給料はこの30年ほぼ上がらず、大企業の内部留保額は2021年度で500兆円もあるのに法人税は下がっている。そのくせ消費税は上がり続け、さらには零細個人事業主から実質的に消費税を搾り取ろうとするインボイス制度が始まろうとしている。だけど福祉も教育も充実するどころか、生保も年金額も確実に下がり続け教育費は増大している。その合間に地震が起こり、原発は爆発し、異常気象に続き災害も起き、疫病が流行り、戦争も起き、その結果物価が上昇し続けているこの現状! 2022年10 月現在、マジョリティの詰め合わせのような人でさえも今後当たり前に働けると思えなくなってしまった時代。労働に対する感覚にも変化が起こっていることは触れておきたい。
そして賃労働という枠組みで働いたり、働けなかったり、あるいはその繰り返しで働く意欲とはなんなのかよくわからなくなったロスジェネ世代の女性(おおむねシスジェンダーでかつ異性愛者)である私。この私の視点からあらためて賃労働を語っていくのがこの連載だ。いや、賃労働だけに限らない。家庭で行われるさまざまな「家事」と呼ばれる雑務、育児や介護などのコロナ以後でいうところのエッセンシャルワーク、さらにはフリーランスの仕事、ボランティア、地域活動や社会運動についても取り上げたい。
さらには病人・障害者であること、いじめや暴力、性暴力の被害を受けてサバイバーとして生きていくことなど、従来なら「仕事」や「労働」に組み込まれてこなかった属性や存在、ケアを受ける側、助けられる側としてみなされ続ける立場だからこそ行いうる「しごと」や「はたらき」についても語りたい。
現在の社会ではアンペイドワーク(あるいは低賃金労働)に据え置かれているケア労働的な「はたらき」や「しごと」が低く見積もられ、ぞんざいに扱われてきたことの意味についてうんと語りたいが、同時に「(賃労働で)働かない/働けない」人間/女性であること、いわば病人、障害者、失業者、無職者といった存在は「はたらき」や「しごと」に無縁なのか、という問いが私の中にはふつふつとある。今までの私の経験からすると、この日本社会から「無職」としか名乗ることを許されていない人たちのその「無職のちから(無職力)」に頼ってきた事例にはことかかない。そんな「無職のちから(無職力)」を示す事例もおいおいこの連載で語っていきたい。その別名は労働力の搾取というのかもしれないけれど。
はるか昔の時空間に想いを馳せる。19世紀イギリス。近代工場労働の過酷な環境。いわゆる「労働運動」はそこから生まれた。マルクス・エンゲルスといったビッグネームたちの作り出したインターナショナル、あるいはウィメンズマーチを生み出したアメリカの労働運動、日本だって戦前から労働運動はあった。ただし戦中に国家総動員体制に組み込まれてしまったが。戦後に復活したものの今は組織率(労組加入率)が下がっている。
だが労働運動というと一貫して、心身元気だが「仕事はできるが解雇される」「仕事はできるが低賃金」「仕事はできるがそもそも(性別・民族・人種・門地等々の属性ゆえに)雇われない」状況への抵抗がメインだったと思う。過去においても現在でも「働いていない人」「働けない人」「働きたくない人」は病人や障害者といったカテゴリーに振り分けられ、労働運動の主体として見做されることはあまりなかった。そして日本のメインストリームの労働運動の主体は男性だった。現在の資本主義社会の下で資産がある人以外は働いて給与を得るのでなければ、福祉制度を使うしかない。お伝えしておかねばならないが、私は文筆業とか文筆家と名乗っているものの別にそれで「飯を食えている」わけではない。障害年金を受給し、親切な知人の空き家を無料でお借りして生きながらえている。そういう点では「障害者」と名乗っても構わないし、こういう話をする際には必ず私がどうやって生きているかを示すためにもまず障害年金の話を伝えることにしている。ちなみに生活保護を受給したこともある。
そんな私が「働かない/働けない/働きたくない」という話をした際に、「そんなのはお金があるからだ/実家が太いからだ/養う相手がいないからだ」などなどとこの10年言われてきた。そのツッコミに対しては現状の生活保護制度が受給できた時点で、自慢にもならないがどれくらいお金がないかがわかろうというものである。生活保護制度はしばしばあまりに金がなくなった時点でしか支給できないことが問題視されている。
ちなみに生活保護受給経験があることを伝えた上で呼ばれたトークセミナーで「どれくらいの貯金額だと生活保護が受給できるのか」と尋ねられた時、「うーん……もはや貯金と言える額とは言えないけど5万円切ったら?」と自分の経験を伝えたところ、静かな声で質問者が「働いて生きていくことを目指します」と言われたのはなかなか感慨深い。「実家が太い」とはどこまでを指すのかわからないが、安倍晋三を殺害した山上徹也容疑者のように親の借金があるわけでもなく、障害年金で暮らしていけることを「太い」というなら確かに太いのだろう。しかし私のことを「太い」とか「恵まれている」と語った人たち全てが親の借金を抱えていた人なのかは限りなく謎である。そんな私だが「文筆家」とか「文筆業」と名乗ることにしている。自分の書いた本に関連した話をするためにトークイベントなどで呼ばれたり、また障害年金だけで暮らしているわけでもないからだ。
先ほど労働運動の主体は健康な人で男性だったという話をしたが、現在健常者/病者・障害者と労働の話をする際に、その二つのカテゴリーがスッキリそもそも分けられうるのかという問題もある。かつて厚生省と労働省に分かれていた組織が厚生労働省になってしまったのは単純にお金を削りたかっただけだからだろうが、2022年の日本社会では幸か不幸か労働問題と福祉の問題を簡単に分けることができなくなっている。労働に対する私自身のスタンスが「働かない」「働けない」「働きたくない」ときっちり分けられない現実は、私自身が既存のカテゴリーにハマれなかったことをも意味している。「働かない/働けない/働きたくない」という表記は、賃労働者としてのアイデンティティも病者や障害者というアイデンティティもはっきり持てない。
……と、この原稿を書いている際にこんな記事がネットに飛び込んできた。
「いよいよ世界中で『働かない人』が激増中…それが経済に与える『深刻すぎるダメージ』」という見出しだ(注3)。この記事を読むとコロナ禍が問題というよりも、コロナ禍以前から脈々と続いている労働そのものの問題が露呈したとしか思えない。「高い賃金を提示しても、職場の環境が良くない企業の場合、容易に人は集まらず、米国の労働参加率は横ばいが続」き、「こうした動きがもっとも顕著となっているのが、いわゆるエッセンシャルワーカーの職場」とあるが、もともとのエッセンシャルワークの仕事が安すぎるのである。エッセンシャルなのになぜ低賃金だったのか。それこそ「人身取引」だと国連から警告を受けている技能実習生の仕事は、建設業の他に農林業や家事労働が多い。人が生きていくのに必要な仕事を「人身取引」いわば「奴隷」として行わせていることに震えるが、アフリカから無理矢理連れてきたアメリカの黒人奴隷にやらせていた仕事が綿花畑の労働と家事労働だったことを思えば、生活に必要な仕事を尊重せず奴隷労働の待遇として扱うことが怖いと思うのは少数派なのかもしれない。労働は、それが生活に必要な仕事であればあるほど暴力的(暴力を振るう側/振るわれる側にふり分けられることを含め)になっているのはなぜなのか……。
初回から内容を詰め込みすぎたが、次回以降、この怒涛の問いを一つずつ私の立ち位置から考えていきたいと思う。みなさん、よろしくお願いします!!
(注1)1980年まで専業主婦率は上昇し続け、1997年には共働き世帯数が専業主婦世帯数を逆転し、2000年代移行はその傾向をさらに強める。
参考資料:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「早わかりグラフでみる長期労働統計:図12 専業主婦世帯と共働き世帯」https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0212.html
(注2)標準世帯モデルとは“標準世帯……夫婦と子供2人の4人で構成される世帯のうち、有業者が世帯主1人だけの世帯に限定したものである。”
総務省統計局「家計調査 用語の説明」https://www.stat.go.jp/data/kakei/2004np/04nh02.html
(注3)加谷珪一「いよいよ世界中で『働かない人』が激増中…それが経済に与える『深刻すぎるダメージ』」
『現代ビジネス』2022年9月7日https://gendai.media/articles/-/99490
*続きは書籍『「働けない」をとことん考えてみた。』でお楽しみください。
ご購入はこちらから